【特集・コロナ危機と大学】
座談会2:ウィズコロナ時代の医学、医療
2020/08/06

-

-
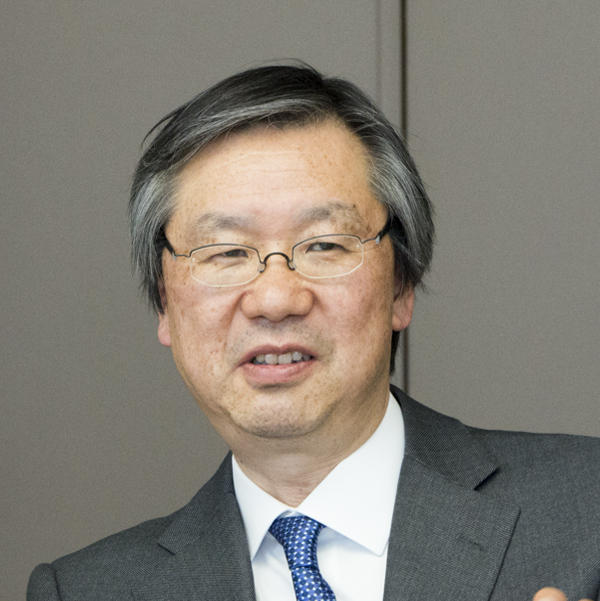
天谷 雅行(あまがい まさゆき)
慶應義塾大学医学部長
塾員(1985医、89医博)。医学博士。専門は皮膚科、自己免疫等。2005年より医学部皮膚科学教授。17年より医学部長。
-

北川 雄光(きたがわ ゆうこう)
慶應義塾大学病院長
塾員(1986医)。博士(医学)。専門は一般・消化器外科。2007年より医学部外科学教授。大学病院副院長を経て17年より病院長。
-

佐谷 秀行(さや ひでゆき)
慶應義塾大学病院副病院長、臨床研究推進センター長
1981年神戸大学医学部卒業。医学博士。専門は腫瘍生物学。2007より慶應義塾大学医学部先端医科学研究所遺伝子制御研究部門教授。
-
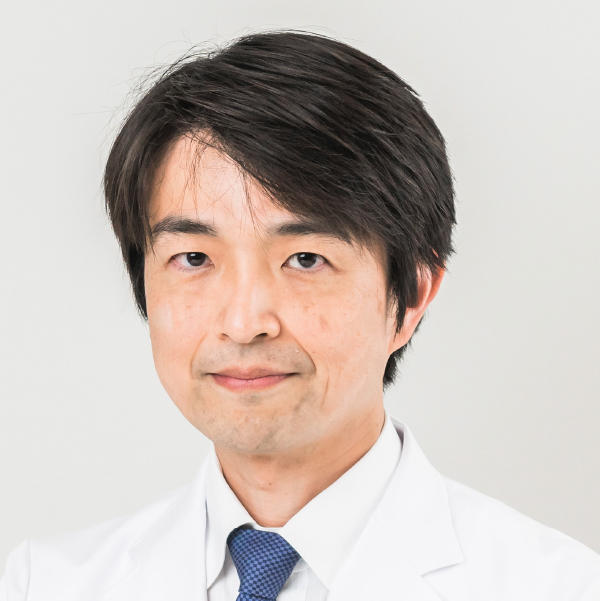
福永 興壱(ふくなが こういち)
慶應義塾大学医学部内科学(呼吸器)教授
塾員(1994医、2000医博)。博士(医学)。専門は呼吸器内科全般。2019年より医学部内科学(呼吸器)教授。病院長補佐。
-

竹内 勤(司会)(たけうち つとむ)
慶應義塾常任理事【病院、信濃町キャンパス担当】
塾員(1980医)。医学博士。専門はリウマチ・膠原病。2009年医学部内科学教授。大学病院長等を経て17年より慶應義塾常任理事。
日本の新型コロナウイルス対策
竹内 今日は「ウィズコロナ時代の医学、医療」というテーマで座談会を行いたいと思います。
慶應病院、医学部にて新型コロナウイルス対策に日夜頑張っていただいている面々に加え、厚生労働省のクラスター対策班で奮闘されている齋藤先生に加わっていただいています。日本のコロナウイルス対策に対する取り組みも踏まえて、これまでの現場の状況、そしてこれからのことについて活発な意見交換ができればと思っております。
この新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を私たちは想像もしていませんでした。昨年12月31日に武漢で原因不明の非定型肺炎が集団発生したと武漢市衛生健康委員会から発表がありましたが、それがこんなにも日本に入ってくるとは思いませんでした。
1月の武漢からの観光客バスツアー、2月初旬からのクルーズ船の問題といろいろなことが起こり、その頃から少しずつ新型コロナウイルスへの不安が増していきましたが、3月末から起こった全国的な感染拡大は想像を絶するようなことでした。4月7日には緊急事態宣言が発令され、日本社会全体、それから慶應病院、医学部、そして慶應義塾も大きく巻き込まれました。
まず齋藤先生から、日本の新型コロナウイルス対策の基本的な考え方についてご紹介いただけますか。
齋藤 私は塾の熱帯医学・寄生虫学教室の出身で2011年から厚生労働省に3年間お世話になった後に今の国立保健医療科学院に来ております。現在、クラスター対策班のほうでも活動しています。
今回の新型コロナの対策について、日本は上手くいったのか、いっていないのかという議論がありますが、私はこれまでは上手くやってきたと思っています。
その理由は、いち早くきちんと患者さんを見つけて、その感染経路の調査をしっかりとやってきた。そして、この新型コロナウイルス感染症はどのように広がっていくか、それをしっかりと認識して戦略を立てて対策をとってきたからです。これはいわゆるクラスター対策と呼ばれていますが、日本の初期の対策の中心的な考え方になっています。
初期の感染者100例ほどを調査してわかったことは、インフルエンザなどのように多くの感染者が次々と感染させていくという感染様式でなくて、いわゆるスーパースプレッダーと呼ばれる、ごく一部の人がたくさんの人に感染を広げていくことがこの流行の特徴だということでした。
逆にほとんどの人は次の人に感染させない。本当にわずかな人が5人、10人と大きく感染させて、それが大きな流行につながっていくことがわかってきました。そのため、いかにこのクラスターをはやく見つけて、その本質を摑み、またクラスターを起こさせないかが重要になります。それから流行が指数関数的に増えるフェーズをいかに早く察知して対策を取るかということに注力してやってきました。
3月中旬、欧米からの旅行者や帰国者に感染者が増えてきて、国内で大きく広がる予兆が見えました。そこでいち早く大阪、東京が県境をまたいだ移動をしないように、週末は外出を自粛するように、といったメッセージを出し、各都道府県でも対策が少しずつ本格的に動き出していきました。
そして4月7日、国が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を行って、社会において人と人との接触を大きく削減するという対策をとり、拡大しつつあった新規感染者の数をかなり減らして、小康状態に戻すことができました。そして、今は第2波に向けて準備を進めているという状況にあると考えています。(厚生労働省HP参照)
竹内 7月1日現在、世界では約1千万人罹患者がいて、死亡者は約50万人で約5%の死亡率です。日本はそれに対して約2万人弱、死亡者約千人です。日本の新型コロナウイルス感染者、死亡者がここまで低く抑えられたのはクラスター対策がしっかり行われたことが1つの原因だということですね。
慶應病院での感染対応
竹内 さて、3月以降、慶應義塾大学病院も新型コロナ感染症に大きく振り回されました。北川病院長にこれまで慶應病院で起こったことについて簡単にご説明いただきたいと思います。
北川 詳しくは本誌の7月号に記載させていただきましたが、当院におきましては残念ながら他院から転院した患者を発端とする院内感染が起きてしまいました。また、市中感染した研修医から「夜の会食」を介して集団感染が起きました。この2つの大きな事案については、皆様に大変なご迷惑、ご心配をおかけしてしまいましたこと、病院長として深くお詫び申し上げます。
私が今、思い起こしても痛切に感じるのは、われわれはこの新型コロナウイルスの典型的な難しい特徴を持った患者さんを経験したのではないかということです。無症候で陽性の方がいらっしゃる。その無症候の方が発症する直前、そして発症直後に感染性が高い。ごくわずかではあっても特殊なスーパースプレッダーが存在するということです。われわれが院内感染の発端者として経験した第1例目の方がこれら全ての特徴を有していました。
入院された時には他の疾患の手術目的で、まったく肺炎症状はなかったのですが、同室者、医療従事者に数多く感染が起こりました。
理論的にいえば、スタンダード・プリコーション(標準予防策)が完璧であれば院内感染は起こらないはずですが、そういう処置をしていても院内感染が起こり得る未知の部分があるウイルスだと思います。
私どものような大学病院、あるいは感染症の専門医療機関でも院内感染が起こっていることを見ても、特殊な患者さんの場合には、感染制御が非常に難しい状況があり得ます。コロナであることを認識しないで医療を行った場合、院内感染が起こりうることを常に念頭において診療を行わなければいけないと痛切に感じています。
また研修医の集団感染は会食という場で広がりました。私どもが日常の診療行為でしっかりとスタンダード・プリコーションを遵守していても、バックヤードでの昼食や夜の会食時にマスクを外して他者と接触する時に感染は起こり得るということです。市中感染は市民生活をしている以上、医療従事者にも起こり得ますので、これを防ぐには診療行為の中だけではなく、生活全般に対して様々な注意が必要であると痛切に感じました。
一方で起こってしまった院内感染に対しては、徹底的な接触者調査、迅速なPCR検査、医療チームの入れ換えなどを講じて制御することができました。ウイルスゲノム配列解析による疫学分析の結果も大変有用でした。このように抜本的な対応を迅速にとることで制御できることも学んだと思っています。
竹内 新型コロナウイルスが流行するにつれ、WHOあるいは様々な医療機関からこのウイルスの特徴についての報道がありましたが、わからないことも多く、その中で現場は対応しなければならなかった。多くの困難を抱えながらウイルスに向き合ってきたという現状があると思います。
特に無症候感染がわかったのはアメリカCDCの報告でも3月30日でした。慶應病院で起こったケースはその前でしたので、無症候者の中にそれだけ感染力が強い方がいるという認識はあまりなかったわけですね。
北川 そうですね。当時、私どもはすでに2月中にPCR検査の体制を整えており、肺炎疑いの患者さんは全員個室入院させてPCR検査を行っていました。少しでも疑いのある方については、しっかりと水際対策はとれていたと思っていた中で、予想外の経路からの院内感染の発生でした。
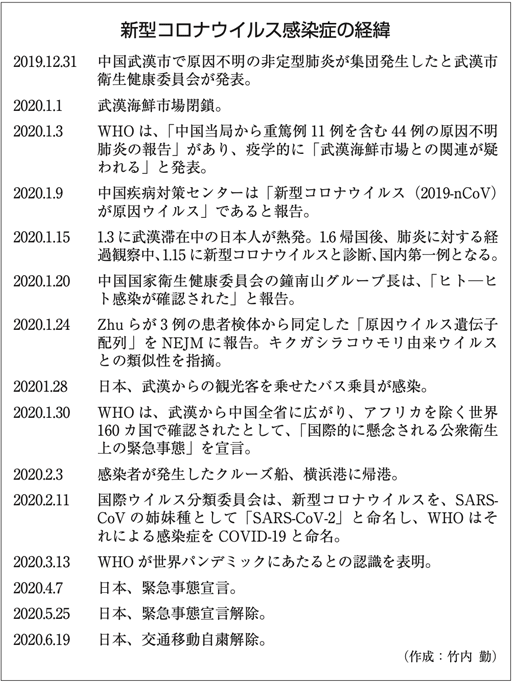
2020年8月号
【特集・コロナ危機と大学】
- 【特集・コロナ危機と大学】座談会1:コロナ危機が教育・研究・国際交流にもたらしているもの
- 【特集・コロナ危機と大学】新型コロナ対策──水をかき出すだけでなく、穴をふさぐ対策も必要/宮田 裕章
- 【特集・コロナ危機と大学】慶應病院院内感染制御の記録/長谷川 直樹
- 【特集・コロナ危機と大学】「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」の紹介/山澤 文裕
- 【特集・コロナ危機と大学】医学生による感染予防指針/門川 俊明
- 【特集・コロナ危機と大学】学生、教職員を守る保健管理センターの役割/西村 知泰
- 【特集・コロナ危機と大学】コロナ禍における体育会活動/山本 信人
- 【特集・コロナ危機と大学】コロナ危機と幼稚舎の対応/杉浦 重成
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

齋藤 智也(さいとう ともや)
国立保健医療科学院 健康危機管理研究部長
塾員(2000医[熱帯医学・寄生虫学])。医学博士。専門は公衆衛生危機管理。厚生労働省新型コロナウイルスクラスター対策班メンバー。