【特集・コロナ危機と大学】
座談会2:ウィズコロナ時代の医学、医療
2020/08/06
「救命診療チーム」の立ち上げ
竹内 日本全体、そして世界全体がそのような状況の中でこの新型コロナウイルス感染症と向き合ってきた。その中で日本は対人口の死亡数が非常に低く抑えられ、世界各国の中では感染対策が上手くいったと評価されているのではないかと思います。
日本は最悪の医療崩壊を免れましたが、3月末から4月、5月にかけては本当に危機感を持ち、慶應病院も戦々恐々として臨んだのではないかと思います。
3月末から4月、患者さんが押し寄せてきて病棟が大変な状況になりました。そして今は少し落ち着いていますが、なにか不気味な動きがある。この現状を踏まえながら、一番現場に近い福永先生はどのようなことをお感じになっていらっしゃいますか。
福永 3月の下旬、転院患者さんによる院内感染が起きてしまった状況の中、病院長からCOVID-19に対する診療体制構築の要請を受けました。それまで慶應病院はPCR検査体制や感染予防対策などCOVID-19に対する準備を着々と進めていましたが、この未知の感染症に対する診療経験はほぼないに等しく、診療体制の構築は急務と感じました。
一方で、我々呼吸科器内科のような限られた専門科の医師だけが新型コロナウイルス感染症患者を診ていくということは、当時の諸外国の様子を見た時に、患者が急激に増加すれば、診療できる医師が不足し、早晩医療崩壊につながるであろうと想像しました。このためにも多くの医師たちがこの病気と早い段階で向き合う機会を持ち、医療に参画する体制を構築することが肝要と考えました。
そこで慶應病院全体の医師から成る、「COVID-19 救命診療チーム」を立ち上げました。感染症診療の経験が多い我々呼吸器内科は病態が不安定な中等症を担当し、重症化する人たちをいち早く見つける役割を担う。そして麻酔科、救急部の先生方には急性期あるいは人工呼吸器を要する患者さんを中心に担当していただく。
人工心肺(ECMO)が必要になった場合に備え心臓血管外科、循環器内科とチームを形成。さらに、これらの重症~中等症チームに内科そして外科から医師を交代制で派遣していただくシステムを作りました。また比較的落ち着いている軽症の患者さんについては、内科、外科以外の院内の科の先生方に軽症チームとして同じく交代制で診療に当たっていただきました。
一方で、この得体の知れない病気を診るということは少なからず医療従事者に大きな精神的負担がかかってきます。そこで精神科の三村將教授を中心に「心のケアチーム」を立ち上げていただき、医療従事者のメンタリティのフォローもできる体制を構築しました。
この「救命診療チーム体制」を通じて、初動の段階からこの未曾有の感染症に対する理解を深めていった医師たちが一丸となってこの疾患に立ち向かったことが、第1波の窮地を乗り越えられた鍵の1つとなったかも知れません。
今後、第2波、第3波が来たとしても慶應病院の医師たちはこの診療チームでの経験を活かし、それぞれの現場の指揮官として他の医療従事者と連携をとりながら乗り越えて行けるのではないかと考えています。
遺伝子を継ぐ「ドンネルプロジェクト」
竹内 慶應は幸いなことにクルーズ船の患者を受け入れた2月中旬から新型コロナウイルス感染症患者の診療をしていましたので、患者が来た場合の体制や検査体制は整えられていました。
しかし、先ほど話があったように不意を突かれた状況もあり、非常に危機感を持ったわけですが、そのような中、各診療科の皆さんが協力して対応していただいたということが、慶應の非常に大きな特徴だったのではないかと思います。
医学部、そして臨床研究推進センターの研究部門も皆、一緒になって対応しました。教員、学生教育、あるいは病院を支えるという立場でのご苦労もたくさんあっただろうと思いますが、天谷先生、第1波が来た頃の医学部の状況についてお願い致します。
天谷 3月下旬、院内感染の事例が発生した瞬間、北川先生、福永先生をはじめとした病院関係者が全身全霊で、皆で何とかコントロールしようとしていた現場を医学部の立場で見せていただきました。
そこで、医学部から何ができるかということを佐谷先生に臨床研究推進センター長としておまとめいただき、自然と基礎研究の方々もどうやってこの緊急時に貢献できるかという機運が高まり、4月2日に第1回会議が開かれました。
そこで集まったメンバーの熱い気持ちが一気に噴き出しました。COVID-19克服のために自分たちにできることはなにかと様々なバックグラウンドの方が情報を共有し、キャンパス内の基礎研究者に伝播するまで時間はかかりませんでした。
具体的な方策に関しては佐谷先生が述べられると思いますが、こういう土壌があったのは慶應義塾大学医学部の、いわば遺伝子があります。つまり、初代医学部長の北里柴三郎が体験したこと、そして大切にしたことの遺伝子が継承されているのだと思います。
北里柴三郎は1894年、アジアでペストが大流行した時、日本の調査隊の派遣団の代表として香港に行き、当時致死率が9割を超えていたペスト菌の原因菌を分離するという偉業をなされたわけです。香港での環境は今の3密どころではありませんでした。研究活動を行ったケネディタウン・ホスピタルでは、8畳ほどの部屋に5人以上の人が詰め、市民に見られることを恐れてカーテンも閉じて蒸し風呂のような状態でした。
死亡例があると、そこから臓器を取り出して染色するというとんでもない作業をして、実際に派遣団から感染者も死亡者も出るという状況でこの偉業を成し遂げました。
慶應医学100年の歴史の中にはそういった遺伝子があるために、このような機運が出てきたのではないかと思います。そして、北里柴三郎のニックネームであった「雷おやじ」からドンネル(ドイツ語で雷の意味)と名付け、基礎・臨床が一体となって新型コロナウイルスについて研究していく「慶應ドンネルプロジェクト」が誕生しました。
竹内 佐谷先生、ドンネルプロジェクトは具体的にはどんな枠組みでどんなことが行われているのでしょうか。
佐谷 今、天谷医学部長がご説明されたように、私たちは「基礎・臨床一家族のごとく」という北里柴三郎先生の言葉にあるように、常に一体化して、基礎医学の研究を臨床に反映するためにこれまでも研究を行ってきました。
私たち臨床研究推進センターは慶應で生まれた基礎研究を臨床に移行することを支援する組織です。今回は特にこの感染症に対して、いち早く研究の成果を診断や治療に直結させることが使命と考え行動しています。基礎研究者も臨床の皆さんとともにこのCOVID-19に立ち向かおうと一体化しています。
実は東日本大震災の際、医療資源が非常に限られた時に、何か基礎の研究者も貢献できないかと、「経験なき医師団」という組織が自発的に立ち上がりました。今回も医学部では松尾光一先生が中心となってボランティアを募ったところ、わずか1週間で100人以上の登録がありました。基礎研究者が臨床の人たちとともに診断、治療に向かって進みたいという熱い気持ちから、ドンネルプロジェクトが生まれました。
今までは異なった分野でそれぞれ仕事をしてきた人たちがその専門性を発揮し、協力してこの新型コロナウイルスに立ち向かっています。
ウイルスに対する抗体や抗原を検出するシステムの開発、そしてウイルスに対する中和抗体の作成などが急速に進んでいます。また分子遺伝学の研究者は、ウイルスゲノム配列解析を迅速に実施し、患者さんのウイルスが武漢から来たものなのか、ヨーロッパ由来なのかを明らかにしました。
また理化学研究所や国立感染症研究所との共同研究もスタートし、第2波のための診断、あるいは新しい治療を行う体制が慶應の中で育ちつつあります。
基礎臨床一体化した研究体制は整い、まさにワンチームでこの感染症に立ち向かっています。
竹内 ドンネルプロジェクトは、公衆衛生学的な疫学の解析のチームもあれば、中央検査部を中心とした抗体検査、PCR検査の検査チーム、そのウイルスの配列を読み取るチーム、新たに抗体検査を開発するチームもある。また治療として中和抗体を抽出して、治療に結びつけようとするチーム、あるいは回復期の患者血清から血清を抽出して、それを治療に結びつけようという、様々なチームがあります。
同時に理化学研究所、国立感染症研究所等とのコラボレーションも進めていただき、4月からのわずか3カ月間で多くの成果を出していただいており、これからもその成果が世に出てくるのではないかと期待しています。
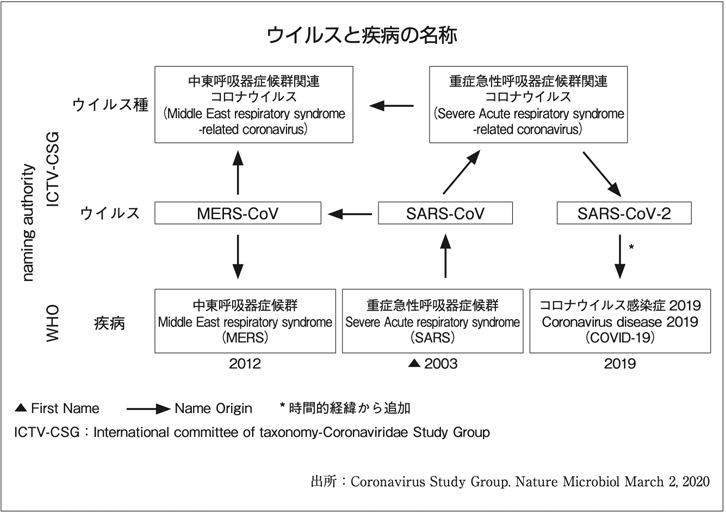
2020年8月号
【特集・コロナ危機と大学】
- 【特集・コロナ危機と大学】座談会1:コロナ危機が教育・研究・国際交流にもたらしているもの
- 【特集・コロナ危機と大学】新型コロナ対策──水をかき出すだけでなく、穴をふさぐ対策も必要/宮田 裕章
- 【特集・コロナ危機と大学】慶應病院院内感染制御の記録/長谷川 直樹
- 【特集・コロナ危機と大学】「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」の紹介/山澤 文裕
- 【特集・コロナ危機と大学】医学生による感染予防指針/門川 俊明
- 【特集・コロナ危機と大学】学生、教職員を守る保健管理センターの役割/西村 知泰
- 【特集・コロナ危機と大学】コロナ禍における体育会活動/山本 信人
- 【特集・コロナ危機と大学】コロナ危機と幼稚舎の対応/杉浦 重成
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |
