【特集:新・読書論】
経験としての読書──環境から見る本の未来/柴野 京子
2020/05/11
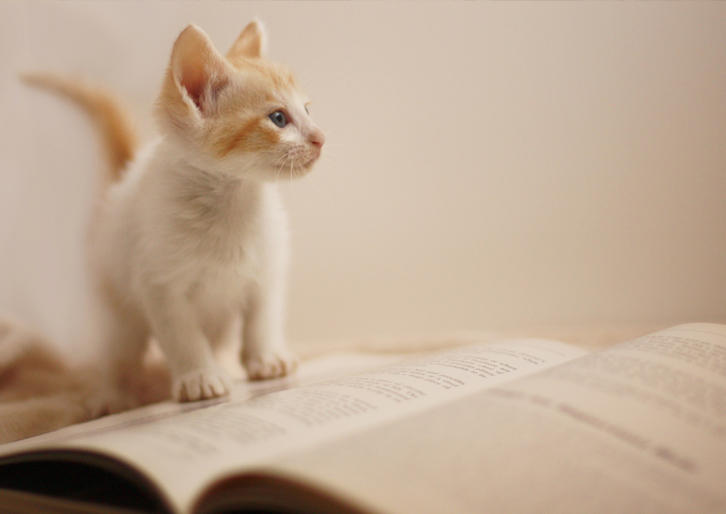
ジャック・チボーという名の友人
極端な寡作ながら、圧倒的なクオリティで独自の時空間を表現する漫画家、高野文子の代表作のひとつに『黄色い本 ジャック・チボーという名の友人』という作品がある。手塚治虫文化賞の大賞受賞作であるにもかかわらず、品切が続いていたが、幸いにして近ごろまた入手できるようになった。
主人公の田家実地子は、雪深い地方の町に住む高校3年生。家には両親と小学生の弟がいて、からだの弱い従妹をひとり預かっている。家事をよく手伝い、編み機の扱いが得意な実地子は、母の友人からの頼まれ仕事なども引き受けつつ、学校の図書室で借りた全5巻の黄色い本、『チボー家の人々』を読み続けている。
とりたてて大きな事件が起こるわけではない。だがそのつましく平凡な日常は、通学バスの中で、小さな子の相手をしてやる合間に、家族が寝静まったあともなお、枕元の灯りをつけて読み進めていく実地子の内面を通して、小説の世界とシンクロする。革命を志すジャック・チボーと仲間たちは、実地子にさまざまな問いを投げかけ、日々の暮らしの中で対話を重ねていく。そして、地元の大手メリヤス工場に就職することを決めた実地子は、自分の選択と意思とを彼らに伝えて支持を受け、黄色い本を図書室に返却するところで、物語は終わる。
2014年に発表された高野の目下の最新作『ドミトリーともきんす』では、朝永振一郎や牧野富太郎など、自然科学の名著が主題にとりあげられている。こちらはもっとストレートに本じたいの楽しさを紹介しているが、原点は『黄色い本』であり、これがすぐれたマンガ作品であると同時に第一級の読書論であることは、もっと広く知られてしかるべきだろう。
読書を成立させているもの
ところで『黄色い本』には、読書にかかわる装置がふたつ登場する。ひとつは実地子が本を借りた学校の図書室、もうひとつは田家家の本棚である。図書館の描写はだいぶ抽象化されているが、作者自身によれば、設定は昭和40年代あたりとのことなので(『ユリイカ』第34巻第9号〈特集・高野文子〉2002年7月)、リノリウムか木の床の、ごく質素な内装だったのではないかと想像できる。実地子が読んだ白水社版全五巻の『チボー家の人々』は、1966年の刊行と注記にあるので、棚の中では真新しく輝いて見えたかもしれない。
いっぽう家の本棚のほうは、押し入れの下段、奥の方に布をかけた状態でしまいこまれている。乱雑に並べてあるのは古い児童書ばかり、病弱で外に出られない幼い姪のために、実地子の父がひっぱり出してきたものだ。
本の背表紙には、グリムやイソップの童話集、偉人の伝記、折り紙・工作、小学生向けの百科事典など、具体的な書名が記されている。むろん創作上のものではあるが、図書館と描き方が対照的なのは、「実ッコちゃんと基根ちゃん(弟の名)が読んだ」本だからである。ずばり昭和の子どもの本のスタンダード、といわんばかりのラインナップだが、この本棚こそ田家家の子どもたちの読書履歴であり、かつてあった身の回りの風景なのだ。
生まれ育った家にどんな本棚があったか。学生時代に夢中で読んだあの一冊は、いつどこで手に入れたのだったか。読書の話をするとき、人はしばしば過去の記憶や個人的なエピソードを本に被せて語るが、それは読書という行為がただ単純に「本を読む」だけではなく、その前後のプロセスや環境をすべて含めた、経験として成立しているからにほかならない。
田家実地子は、ありふれてはいるがそれなりに豊かな本を与えられ、学校の図書室で親の知らない本を借りてくるようになった。よき理解者である父親は、娘に向かって、
「実ッコ、その本買うか? 注文せば良いんだ」と声をかけ、
「好きな本を、一生持ってるのもいいもんだと、俺は、思うがなあ」
とつぶやく。作品には出てこないが、彼らがときおり本を買っている、さほど大きくはない本屋がこの町にはあるのだろう。その気になれば「注文」して世界を広げることができるし、思い切ってそこに出ていくこともできる。『チボー家の人々』と少女時代に別れを告げた実地子が、ふたたびその扉を開くかどうかはわからない。だが彼女の生きる社会において、そうした装置や機会がどのように設定されていたのかが、実地子の読書経験に決定的な影響を及ぼしたことに変わりはない。

2020年5月号
【特集:新・読書論】
- 【特集:新・読書論】座談会:AI時代に古典を読む
- 【特集:新・読書論】「大正知識人」としての小泉信三/武藤 秀太郎
- 【特集:新・読書論】読書論の現在──教育の中の読書/山梨 あや
- 【特集:新・読書論】「完全な読書」が消える未来?/佐藤 卓己
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉電子書籍の現在と未来/松井 康子
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉❝読書会❞という読書のかたち/瀧井 朝世
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉周辺部を読む「古典」/橋本 陽介
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉人類の智慧の宝物庫/藤谷 道夫
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉検索時代にリアルな本との出会いの場を作る/幅 允孝
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典と現在の狭間で/堀 茂樹
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典との対話/阿川 尚之
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉とっぴな楽しみ/湯川 豊
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉子どもと❝本のたのしみ❞を分かち合う/松岡 享子
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

柴野 京子(しばの きょうこ)
上智大学文学部新聞学科准教授