【特集:新・読書論】
〈私にとっての古典〉人類の智慧の宝物庫/藤谷 道夫
2020/05/11
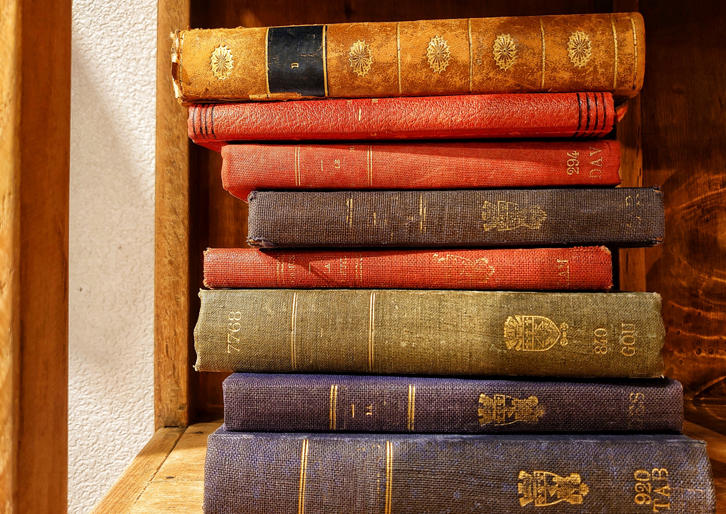
現代は嘘か真か判らない膨大な量の情報に溢れかえっている。ネットを見れば、それこそ無尽蔵の情報の海である。情報過多の最大の問題は、真実や本物の良書が隠されてしまう点にある。悪貨は良貨を駆逐してしまうからである。情報の海の中で現代人は何を頼りにして良いかも解らない状態にある。その時、最も頼りとなる道しるべが《古典》である。
何百年、何千年もの時がふるいにかけてくれているため、間違いがない。最も効率的に良書に出遭える。これが古典を勧める第1の理由である。第2の理由は「すぐに役に立つ本は、すぐ役に立たなくなる」(小泉信三『読書論』)からである。時流に乗って売れる本は、時流が去ると、読まれなくなる。20年、30年前のベストセラーを誰が覚えているだろうか。文豪ゲーテが「エッカーマンとの対話」の中で当時のベストセラー作家の名をあげているが、われわれが知る作家や作品は1つもない。今書店で売れている本は10年も経てば、誰の関心も惹かなくなる。ところが、古典は違う。10年おきに書棚から引っ張り出して読みたくなる。そして読むたびに新たな発見がある。
人間の特性は今も昔も変わらない
古典と現代の書物の違いはどこにあるのだろう。現代の書物は解り易い。現在を舞台にしているので、背景知識や学習が必要ない。一方、古典は時代が古いため、過去にフォーカスするための努力と、ちょっとした感情移入が要る。しかし、それさえクリアーできれば、驚くほど多くの智慧を授けてくれる。なぜなら2千年前であろうが、AIが支配する高度に情報化された社会になろうが、個人の生活は基本的に変わらないからである。
現代になったからと言って、ホメーロスの『イーリアス』を読むために要する時間が短くなるわけではない。人間は昔と同様、生まれ、恋をし、老い(病を得て)死んでいく。どの時代にも夢や希望があり、挫折と失敗、別れと出遭いがある。この基本的特性は人間である限り、いつの時代も変わらない。われわれが直面する様々な個人的な悩みは、これまでの何100億人もの人類が直面してきた悩みと基本的に同じである。古典を知ることで、そうした膨大な叡智に接続できる。われわれの悩みは新しいものではなく、すでに多くの古人が経験したものでしかない。
古人と同じ轍を踏む必要はない。むしろ現代の問題は古人の智慧から学ばないことから同じ過ちを繰り返す点にある。ゲームをしていては経験も知識も広がらないが、読書によって無数の人生を体験することで、1人の生涯が万人の生涯に変貌する。これ以上の宝があるだろうか。
古典はなぜ良書なのか
古典には良書しかない。それは現代の書と違って、古典は無数の詩人や作家が手掛けて出来上がったものだからである。一例を紹介しよう。誰もがシェイクスピアの『ロミオとジュリエット』という作品名は知っている。だが、これはシェイクスピア1人が書いた創作ではない。一番古くは1476年ナポリで出版されたマスッチョ・サレルニターノの『マリオットとジャンノッツァ』に遡る。次にこの筋書きをルイージ・ダ・ポルトが翻案し、1530年『高貴な二人の恋人たちについて新たに発見された物語とその哀れを催す死』という題でヴェネツィアから出版する。オウィディウスの『変身物語』にある「ピュラムスとティスベ」の物語やボッカッチョを採り入れて、筋も登場人物も、後のシェイクスピアの作品にかなり近づいている。舞台もシエナからヴェローナに移り、恋人たちの名前も《ロメウスとジュリエッタ》となっている。
2人は反目しあうモンテッキ家とカプレーティ家の子息という関係であるが、ダ・ポルトがダンテ『神曲』煉獄篇第6歌106行目に登場する「モンテッキ家とカプレーティ家」を、両家が反目を重ねていると誤読した結果である。詳細は省くが、その後、6人の作家たちがこの物語を書き直しているうちにフランス語へ、さらには英語に移され、最後にシェイクスピアが今ある形に仕上げた。現代であれば、著作権の問題からこのようなことはなし得ないが、古典には著作権がないため、多くの作家の手が入り、余分な枝葉は切り落とされ、そのつど洗練されていく。それゆえ、古典は常に完成された美しさをもつ。
ギリシャ神話も同じくオウィディウスの『変身物語』によって完成されるまで800年もの間、無数の詩人たちによって書き換えられ洗練された。無数の書き手が、その都度、自身の経験と智慧を作品の中に注ぎ書き足しているため、まさに智慧の宝庫となっている。ダンテの『神曲』に至っては、それ以前のすべての文学・哲学と聖書の最良の部分を取り込んでいるため、人類が作り上げた最も有機的で完成されたものに仕上がっている。これが古典と現代の作品の違いであり、この貴重な遺産を使わない手はないであろう。
2020年5月号
【特集:新・読書論】
- 【特集:新・読書論】座談会:AI時代に古典を読む
- 【特集:新・読書論】「大正知識人」としての小泉信三/武藤 秀太郎
- 【特集:新・読書論】読書論の現在──教育の中の読書/山梨 あや
- 【特集:新・読書論】経験としての読書──環境から見る本の未来/柴野 京子
- 【特集:新・読書論】「完全な読書」が消える未来?/佐藤 卓己
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉電子書籍の現在と未来/松井 康子
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉❝読書会❞という読書のかたち/瀧井 朝世
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉周辺部を読む「古典」/橋本 陽介
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉検索時代にリアルな本との出会いの場を作る/幅 允孝
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典と現在の狭間で/堀 茂樹
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典との対話/阿川 尚之
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉とっぴな楽しみ/湯川 豊
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉子どもと❝本のたのしみ❞を分かち合う/松岡 享子
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

藤谷 道夫(ふじたに みちお)
慶應義塾大学文学部教授[イタリア文学]