【特集:新・読書論】
〈私にとっての古典〉古典と現在の狭間で/堀 茂樹
2020/05/11
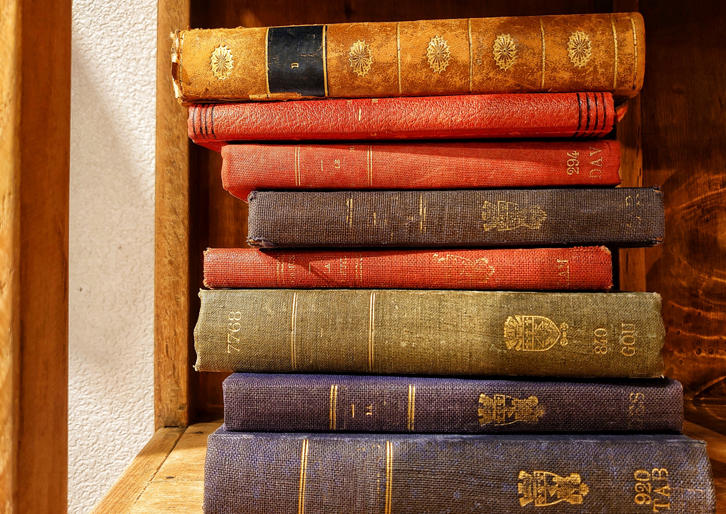
迷走を繰り返すうちに齢を重ねてしまった。近頃は、満開の桜を目にするたびに、自分はあと何回この季節を迎えるのだろうかと自問する。
とはいえ、幸か不幸か、私にリタイア気分はまったくない。昨今のように劣化した日本国を次世代に残して去るわけにはいかないという思いが強く、その思いに重なるかたちで、現代フランスの思想・文学・社会の変貌をもっと正確に深く認識したいという欲望に駆り立てられている。長年アンスティチュ・フランセ東京(旧称・東京日仏学院)で担当している文藝翻訳クラスでは、フランスの若手小説家たちの意欲作を取り上げている。自らセレクトして邦語訳を出してきたのも、主に現代の作品である。このように、私の知的関心の焦点は同時代にある。純粋の学者気質から程遠い私は、厳密な意味では無私でなく、自分自身の実存のフィールドを、すなわち「今、ここ」の現実を理解したいのである。
問題は、「今、ここ」に密着していて、「今、ここ」が理解できるかという点にある。いうまでもなく、事件の現場にいれば真相が摑めると思うのは甘い。現場にいなければ知り得ぬこともあるが、現場にいるがゆえに気づかぬこともある。「時代と添い寝する」などという誘惑的な表現があるが、「添い寝」したって、不透明なものが透明になるわけではない。対象が見えるのはむしろ、少し退き、対象に対して距離を置くときである。また、見ようとする自分自身からも距離をとらなければ、人は自分の見たいものだけを見てしまう。さらに、対象を理解し、判断し、評価するためには、その対象の外に何らかの基準や規準を保持していなければならない。この意味で一般に、人間世界の現在=「今、ここ」を理解するには、それを歴史の中に捉える必要があるといえる。
しかしながら、「今、ここ」は、まるごと完全に歴史に支配されているわけではない。とりわけ芸術や文学は、科学や技術のように歴史とともに進歩するものではない。そもそも美の創造の領域に進歩の概念は適合しないのであって、そこに有効な基準や規準を提供してくれるのは、歴史に想定されるある種の必然性ではなく、過去に生み出されて今日まで残ってきている傑作、すなわち古典の数々にほかならない。
これはいわゆる「古典文学」のことではない。「古典文学」は西洋では古代ギリシア・ラテン文学の謂いで、日本では江戸時代までの文学作品を指すが、ここでいう「古典」は、歴史的価値というより、恒久的で規範的な価値、いいかえれば歴史の事実性を超える価値を認められるに到った作品である。具体的には、西洋文学ではホメーロスの『イーリアス』と『オデュッセイア』を嚆矢とする名作の数々だ。これを味読することは、文学の現在=「今、ここ」を正しく理解するためにも有益な回り道である。たとえばG・スタイナーや、S・レイスや、T・トドロフといった、今は亡き「読むことの師匠たち」は、この回り道を驚異的な健脚で踏破していた。教養として共有される古典こそが、表現の型や作中人物の典型など、多くの確乎たるリファレンスを与えてくれるのだから、その存在意義は、主要な関心が同時代に向かっている私のような者にとっても大きい。
その上、古典にはもう1つ、より一層の注目に値する教育的効果がある。その効果は、逆説的なことに、古典がけっして身近な作品でないという事情に由来する。たとえば、ソポクレスの『オイディプス王』は紀元前5世紀にアテナイで生まれた。今日の日本で暮らすわれわれから言えば、約2500年も前に地球の真裏で初演された戯曲なのだ。当然、主人公オイディプス王の人物像は、われわれの日常世界から隔絶している。それでいて、自ら両眼を抉ったこの人物がテバイの町を去る前に垣間見せる2人の娘への愛情は、われわれの胸をもまっすぐに貫通する。このように古典は、同時代の身近な人の手に成った作品ではないからこそ非常にしばしば、「自分とはまったく別の人間存在の身になって思考すること」(カント『判断力批判』)を通して、読者を自己中心性から解放し、普遍性の地平へと導くのである。
というわけで私は、主に現代文学を扱う翻訳者でありながら、若い学生には常に、当たり外れの多い現代の作品より、まあ騙されたと思って定評のある古典を読めと薦めてきた。慶應SFCに奉職していた時期には、「西洋思想の古典を読む」と題する研究会(ゼミ)で、モンテーニュ、デカルト、ルソーなどを輪読していた。また、講義科目「古典と現在」を担当し、『アンティゴネー』をはじめとする古代ギリシアの悲劇、あるいはヴォルテールの『カンディード』、バルザックの『ゴリオ爺さん』、オーウェル『1984年』、ハクスリー『素晴らしい世界』、プリーモ・レーヴィ『これが人間か』、イヨネスコ『犀』等、定番の傑作を大教室で評釈した。
当時、私のゼミや授業の機会に、「騙されたと思って」自らも古典の中に潜ってみた学生諸君の多くが、イマヌエル・カントの所謂「開かれた思考」に開眼してくることがあったとすれば本懐である。
2020年5月号
【特集:新・読書論】
- 【特集:新・読書論】座談会:AI時代に古典を読む
- 【特集:新・読書論】「大正知識人」としての小泉信三/武藤 秀太郎
- 【特集:新・読書論】読書論の現在──教育の中の読書/山梨 あや
- 【特集:新・読書論】経験としての読書──環境から見る本の未来/柴野 京子
- 【特集:新・読書論】「完全な読書」が消える未来?/佐藤 卓己
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉電子書籍の現在と未来/松井 康子
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉❝読書会❞という読書のかたち/瀧井 朝世
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉周辺部を読む「古典」/橋本 陽介
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉人類の智慧の宝物庫/藤谷 道夫
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉検索時代にリアルな本との出会いの場を作る/幅 允孝
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典との対話/阿川 尚之
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉とっぴな楽しみ/湯川 豊
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉子どもと❝本のたのしみ❞を分かち合う/松岡 享子
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

堀 茂樹(ほり しげき)
翻訳家、慶應義塾大学名誉教授