【特集:新・読書論】
〈私にとっての古典〉とっぴな楽しみ/湯川 豊
2020/05/11
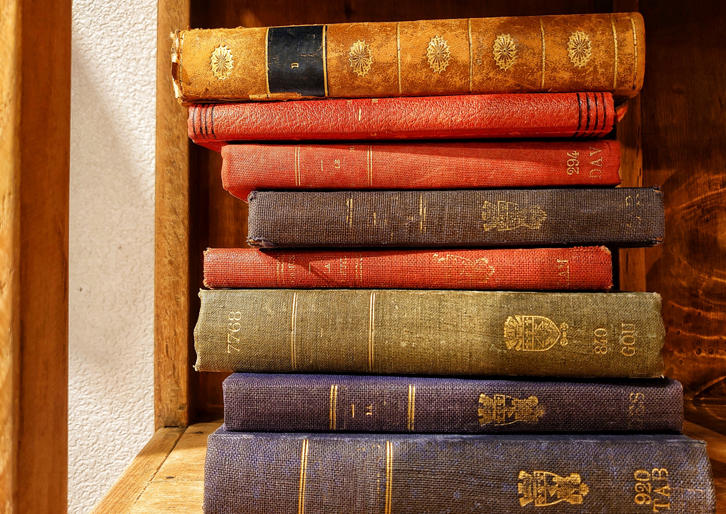
古典とは何か? 私にとっては大それたともいえるこのテーマを、まじめに考えざるを得なくなったのは、妙なことがきっかけになった。
出版社を退職したのち、勧めてくれる人がいて、大学の文芸創作学科の教壇に立ったのだが、そこでのことである。学生たちがあまりにも本を読んでいないのに驚いて、何かの折に「古典を読んでいないんだなあ」と、教室で呟いてしまった。こちらも、まだ教師として慣れていなかったのである。
そのとき、元気のいい男の学生がすっくと立って、「先生、古典って何ですか」と質問してきた。私は無意識で呟いただけだったので、ウーンと答に窮した。そういえば、古典とは何だろう。文学でいえば、長い年月、人びとが模範とし、愛しつづけてきた作品と、辞書ふうの定義はいえるとしても、そもそも自分にとっての古典とは何なんだろうと、基本的な疑問が残ってしまう。私はその場では何とかとりつくろったのだが、自分のなかに疑問が残ったままになった。
そんなふうになったのは、古典を辞書ふうに定義してみたところで、私自身が古典的作品を読んでいない、だから学生にいえた立場じゃない、という気分が働いていたからに違いなかった。
古典を読んでいないという点では、若者向けのライト・ノヴェルを文学だと思っている学生とあまり変わらないという事態が、一瞬脳裡にひらめいたのである。後でそれを確かめるために図書館に行って、たとえば筑摩書房版「世界古典文学全集」などを改めて眺めて、ホメーロスから始まるその全集に照らしてみても、わが古典読書量はじつに寥々たるものだった。
いっぽう日本文学の古典のほうは、高校時代に「古典」の先生に反発して授業をさぼるようになり、先生から落第にすると脅かされた体験がある。その授業は『源氏物語』の一部を取りあげたものだったが、おかげで長いあいだ『源氏』にそっぽを向くことになった。出版社に勤めてしばらく経ってから、ようやくこの大古典に向かいあう気持になったという経緯がある。
『源氏』はまあそれでいいとして、いま岩波書店版の「日本古典文学大系」などのラインアップを見ると、江戸時代の文芸をきわだたせている漢詩、また厖大な量の随想を少しも読んでいない。つまり古典コンプレックスは、日本文学のほうでも続いているといわざるを得ない。
そんなしだいだから、「わたしにとっての古典」を語れという、この原稿など、お引き受けすべきではない。それは承知していたのだが、1つだけ古典について考えていたことがあり、それを問いかけてみたい、と思ったのである。
「古典」の変動ということである。
たとえば森鷗外や夏目漱石は、以前は「現代日本文学全集」に入っていた。明治以降の文学作品は、現代という枠にくくられていて古典ではなかった。それがいつのまにか変動して、鷗外・漱石はむろんのこと、谷崎潤一郎や志賀直哉まで、なぜか古典と呼ばれるような気配になっているのである。古典は、最初に辞書的定義をしたように、「長い年月、人びとが模範としてきた作品」であるとしても、その「長い年月」がどうやら短くなったらしい。それにしたがって、古典が時間の枠組を越えてしまった。
このことをどう考えるか、どう評価するのかは、必ずしも単純な話ではない。
たとえば、20世紀初頭のヨーロッパで生まれた代表的作品、ジョイスの『ユリシーズ』、プルーストの『失われた時を求めて』を、「20世紀の古典」と呼んだとして、何となく座りがいいと感じざるを得ない。その背景には、この2作品が世界文学全体に与えた巨大な影響力があるに違いない。とすると、古典という存在が時間の枠組を越えてしまうのは、自然の勢いとも考えられるのである。
そのような事態からすると、大学の先生がものする文学史のような著作が位置づける「古典」なるものはもう無視して、自分ひとりにとっての古典とは何かを考えの中心に置いていいのではないか、と思えなくもないのである。まあそう思うのは、この年齢になってしまうと、昔の古典文学全集にリスト・アップされたものはもう読む時間がなくなっているからでもある。自分だけの古典は何であったか、あるかを正直に(そしてひそかに)認識して、それを再読したり、その関連書物を読んだりするのが、許されるのではないか。
『源氏物語』の隣に谷崎の『吉野葛』を置いてみたり、スタンダール『赤と黒』の隣に大岡昇平の『武蔵野夫人』を置いてみたりして、誰も共感してくれそうもないとっぴな古典散歩をする。それは楽しみでないこともない。
2020年5月号
【特集:新・読書論】
- 【特集:新・読書論】座談会:AI時代に古典を読む
- 【特集:新・読書論】「大正知識人」としての小泉信三/武藤 秀太郎
- 【特集:新・読書論】読書論の現在──教育の中の読書/山梨 あや
- 【特集:新・読書論】経験としての読書──環境から見る本の未来/柴野 京子
- 【特集:新・読書論】「完全な読書」が消える未来?/佐藤 卓己
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉電子書籍の現在と未来/松井 康子
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉❝読書会❞という読書のかたち/瀧井 朝世
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉周辺部を読む「古典」/橋本 陽介
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉人類の智慧の宝物庫/藤谷 道夫
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉検索時代にリアルな本との出会いの場を作る/幅 允孝
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典と現在の狭間で/堀 茂樹
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典との対話/阿川 尚之
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉子どもと❝本のたのしみ❞を分かち合う/松岡 享子
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

湯川 豊(ゆかわ ゆたか)
ライター・塾員