【特集:新・読書論】
「完全な読書」が消える未来?/佐藤 卓己
2020/05/11
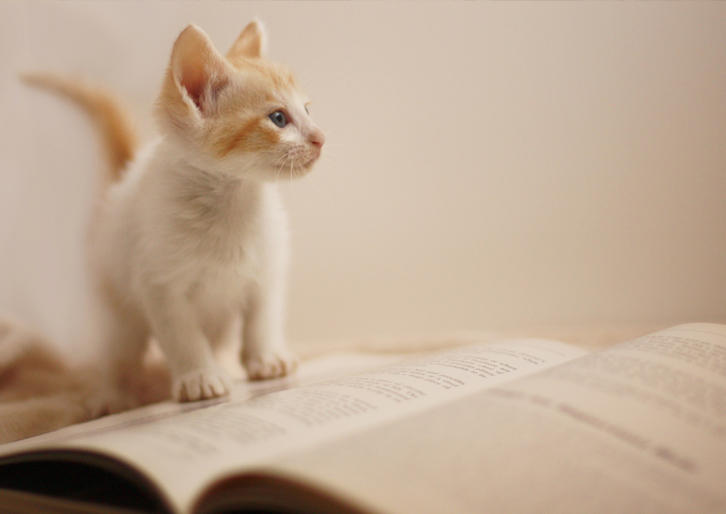
「完全な読書」を求める入試国語
今年の大学入試で出題された拙文の使用許諾願いが「赤本」の教学社や受験予備校から届き始めた。昨年上梓した『流言のメディア史』(岩波新書)は多くの大学で出題された。いずれも「本文の趣旨に合致するもの」を解答させる正誤選択問題を含んでいる。例として、早稲田大学のものを挙げておこう。
ア メディア流言は、特定の時代や状況でのみ生じる1回的な現象である。
イ あいまいで煩わしい情報に向き合うことは、現代のメディアを読み解く上で必要である。
ウ AIによる評価は、正確で客観的に行われるため、社会にとって万能な選抜システムである。
エ 「輿論の世論化」とは、論理に基づく合意形成がなされず、大衆の情動的な感情や意見が主流となることをいう。
オ メディアとしてのインターネットは、情報を瞬時に伝播させることができるが、情報を制御する機能を有してはいない。
アとウがおそらく×、それ以外が〇である。受験生は文中に対応する文章を探し、その適否を判断する。そうした情報処理力は大学での研究にも不可欠である。他方で、こうした受験国語の訓練が「完全な読書」観を学生に刷り込んできた弊害も否定できない。「完全な読書」観とは、書物は最初から終わりまで通読されるべきであり、内容は正確に理解されねばならないという厳格主義である。
受験国語の解法をマスターした私も、学生時代は「完全な読書」の信者だった。蔵書はいずれ全て読破すべきものと考えていた。それゆえ初めて「先生の研究室」で天井までとどく書架の蔵書を目にしたときの感動は大きかった。
「完全な読書」幻想からの解放
いまも脳裏に焼き付いているのは、新入生として京都大学教養部(現・総合人間学部)の野田宣雄研究室で目にした光景である。天井までとどくスチール書架に詰め込まれた洋書、テーブルに山積みされたブルックハルト全集……。そうした読書空間で生活することに私は憧れていた。
ドイツ現代史を学んでいた学部生時代、野田先生の研究室から英語やドイツ語の研究書をしばしば借用した。どの本の余白にも鉛筆でうすく印がつけてあり、先生が読んでいることがわかった。初修外国語であるドイツ語の本は、辞書を引きながら毎日1、2ページを読むのが私には精一杯だった。
「毎日数ページしか読めないのですが、そんなことで研究者になれるでしょうか?」
ソファーに深く腰を掛けた先生はこんな話をされた。その背後の窓からは京大のシンボル、時計台が見えていた。
「君は日本語の本なら本当にすべて理解できていると言えますか。そんなことはないでしょう。でも、ふつうは国語辞書を引きながら読んだりしない。洋書も同じですよ。わからないことがあるのは当然だけど、そこで止まる必要はない。しょせん、論文で使えるのは、自分がよくわかったことだけなのだから。」
もう40年近く前のことだから、その発言を正確に再現できたという自信はない。しかし、この会話で私が救われたことは確かである。いま思えば、それが「完全な読書」幻想からの脱出口だった。むろん、その言葉に説得力があったのは、野田先生のような教養人から書物に囲まれた研究室で聞いたからである。
しかし、今日の学生たちは私と同じような体験ができるだろうか。教員の雑用が増え、「研究室の事務室化」が進んだ。「研究室で本を読んでる暇などない」という、冗談のような本音もよく耳にする。さらにICTが普及すれば、人文系でも理系のようにモニターやタブレットだけの「書物のない研究室」が増えるだろう。今年の新型コロナ危機は、大学における「場所感の喪失」とともに、「完全な読書」とは隔絶した「電子ブックのブラウジング(拾い読み)」に拍車をかけるはずである。はたして、それでよいのだろうか。
『読んでいない本について堂々と語る方法』
これまで私は「完全な読書」幻想から脱する手引きとして、ピエール・バイヤール『読んでいない本について堂々と語る方法』(ちくま学芸文庫)を学生に薦めてきた。ふざけたタイトルと眉を顰めるむきもあろうが、書物というメディアの効果を考察した良書である。
バイヤールは読書の厳格主義を3つの規範──「神聖な読書」、「通読」、「正確な再現」の義務──で定義している。この規範が有害なのは読書への自己欺瞞を生み出すためだという。パリ第八大学教授の著者によれば、プルーストをまともに読んでいないフランス文学者はめずらしくない。むろん、マクルーハンを読んでいないメディア論者もいよう。
正直に告白すれば、私自身、マクルーハン『メディア論──人間の拡張の諸相』を読み切ったのは最近のことで、これまで「摘まみ食い」で済ませてきた。もちろん、私が担当するメディア文化学概論でもマクルーハンに言及する。その意味では、厳格主義の規範からすれば「読んでいない本について堂々と語る」講義を私も実践していた。だが、『メディア論』を熟読する以前と以後で私の講義内容が大きく変わってはいない。どれほど厳密に読んでも内容すべてを記憶しているわけではないのである。読書とは本質的に不完全な情報摂取行動なのだ。流し読みはもちろん、目次を、いやタイトルを眺めるだけでも「読んだ」と言えるのではないか。
こうした「不完全な読書」は悪いことだろうか。まず概論の講義に必要なのは学問領域全体の展望であり、個別の文献に書かれたディテールではない。教養とは全体の見晴らしの良さを意味するもので、それは断片的知識の集積に還元できない。バイヤールはムージル『特性のない男』に登場する図書館司書の次の言葉を、書物間の位置関係という本質をつかむための「能動的態度」として引用する。
「有能な司書になる秘訣は、自分が管理する文献について、書名と目次以外は決して読まないことだということです。」
メディア接触時間に限りがある以上、ある本を読むことは、別の本を読まないことを意味する。蔵書の全体を知る必要がある司書なら個別文献に固執すべきではないはずだ。この姿勢は図書館だけでなく、1冊の書物にも適用できるはずだ。
2020年5月号
【特集:新・読書論】
- 【特集:新・読書論】座談会:AI時代に古典を読む
- 【特集:新・読書論】「大正知識人」としての小泉信三/武藤 秀太郎
- 【特集:新・読書論】読書論の現在──教育の中の読書/山梨 あや
- 【特集:新・読書論】経験としての読書──環境から見る本の未来/柴野 京子
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉電子書籍の現在と未来/松井 康子
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉❝読書会❞という読書のかたち/瀧井 朝世
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉周辺部を読む「古典」/橋本 陽介
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉人類の智慧の宝物庫/藤谷 道夫
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉検索時代にリアルな本との出会いの場を作る/幅 允孝
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典と現在の狭間で/堀 茂樹
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典との対話/阿川 尚之
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉とっぴな楽しみ/湯川 豊
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉子どもと❝本のたのしみ❞を分かち合う/松岡 享子
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

佐藤 卓己(さとう たくみ)
京都大学大学院教育学研究科教授