【特集:新・読書論】
〈読書の風景〉子どもと❝本のたのしみ❞を分かち合う/松岡 享子
2020/05/11
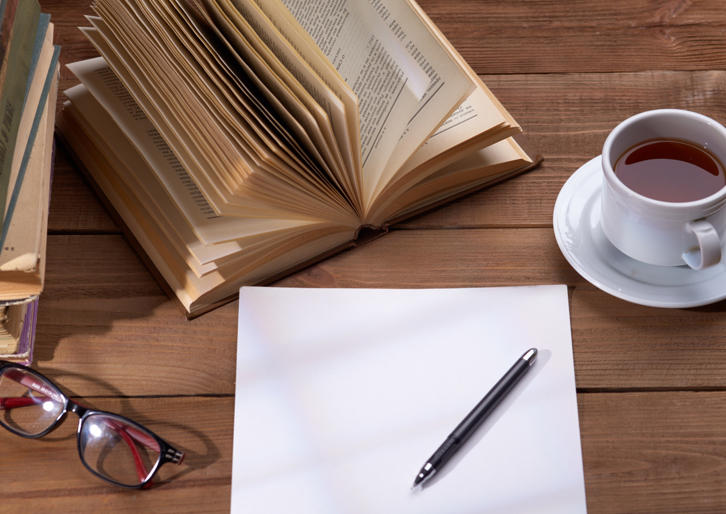
塾の図書館学科を卒業したのは、1960年。もう60年も前のことになった。あの右手に郵便局のある坂をのぼって、幻の門をはいって左、外国語学校の校舎であった木造の古い建物(五号館)の奥、図書館学科の事務室にいきなり飛び込んで、「ここでは児童文学を学べるのでしょうか?」と尋ねた日のことを思い出す。どちらかというと優柔不断だった20代前半のわたしが、「学生募集」の小さな新聞記事だけを頼りに、こんな行動に出たのは、今から考えるとふしぎだ。だが、そこからすべてがはじまったといえる。
図書館というものを知らずに子ども時代を過ごしたわたしが、公共図書館の存在を知らされ、大好きな本と子どもに関わる児童図書館員という職業があることを教えられたのが、図書館学科での2年間だった。これこそわたしがしたかったこと、と胸躍らせたときから今日まで、公立図書館にはじまって、我が家での家庭文庫、そして、法人組織の私立図書館と、活動の場を移しながらも、子どもと本のたのしみを分かち合う仕事から離れずにいられたことは、なんという幸せであろうか。
残念なのは、私立図書館などという無謀な冒険をはじめたために、直接子どもと接する機会が、年々減ってしまったことである。代わって増えてきたのが、大人に向かって、子どもの読書の大切さを訴える仕事である。学校のPTAで、保育園の保護者会で、子ども文庫の関係者や図書館員の集まりで、頼まれては出かけて行ってお話をすることを、ここ何年もつづけてきた。
テレビのリモコンの操作や、スマホをいじることは教えなくてもおぼえてしまう子どもだが、本のたのしみは、だれかそばにいる大人が仲立ちをしてやらないと子どものものにならない。だから、家庭では幼い子に絵本を読んでやってください、字をおぼえた子にも本は読んでやってくださいと、どこへ行ってもお願いをしてきた。それが、子どもにとってたのしいことだし、読書へのいちばん確かな道だからだ、と。
だが、大人を相手にすると、とくに教育関係者を前にすると、それだけではすまなくて、子どもが本を読むことにどんな効用があるかを説かなければならなくなる。いわく想像力をはぐくむ。ことばの力がつく。知識を増やし、視野を広げる。人間と社会への理解を深める。表面的な情報に流されず、深く考える態度を養う。本のなかに理解者を見つけることで心の安定が得られる。読書習慣が身につけば生涯学びつづけられる手段を手に入れることになる。本のなかに時空を超えた友、また師を見つけることができる。手軽で安上がりで、しかも豊かな人生に欠かせないたのしみだ、等々。
これらはみなほんとうのことで、それを証しする例はいくらでも引いてくることができる。身のまわりから、はたまた本のなかから、いくつもの例を引きながら、熱心に説得をつづけてきたのだが、心の底では、いつも「これこれのいいことがあるから」という言い方にはいささかひっかかるものがあった。では、いいことがなければ本は読まなくていいのか、おまえはいいことがあるから本を読んできたのか、と問われると、それは違うと思うからである。
ながいこと子どもに本を勧める仕事をしてきて今思うのは、わたしの場合、本を勧めるときのいちばんの動機は、いい効果があるからではなくて、自分が味わったたのしさをできれば相手にも味わってほしい、という単純で自然な気持ちだということである。
幼い日、本に没入してこの世ならぬ世界を旅して歩いたときに感じたあのふしぎな空気、わが身には起こるはずのない冒険に手に汗した緊張感、心のもやもやがことばで晴れていく快さ、よくはわからないが何か美しく尊いものに出会えたという感動……ひとことでくくれば❝たのしさ❞というしかないあの数々の体験が、わたしが本を読むほんとうの理由だし、それが結局はわたしの仕事を前へ進めるエネルギーを生んできたのだ。
今日、子どもの生活は以前に比べて驚くほど忙しくなっており、そのわずかの余暇を本と争って奪おうとする競争相手がたくさんある。子どもの育ちをやさしく見守るゆとりがない親も増えている。そんななかで子どもに読書のたのしみを知ってもらうのは容易ではない。
児童図書館員としては、大いに頑張らなくてはならないのだが、年を取ったからだろうか、今は読書の効用をしゃかりきになって訴える気にはならない。縁あって自分のまわりにきた子どもたちに、ひとりでもいい、「わたしは本を読んでたのしかったよ」と、そっと、でもしっかりと伝えておきたいと願うだけだ──その子が同じたのしみを見出してくれることを祈りながら。
数は少なくても、本を読む人を何パーセントか内に抱えていないと、社会は健全なバランスを保てないという信念は今も変わらないが。
2020年5月号
【特集:新・読書論】
- 【特集:新・読書論】座談会:AI時代に古典を読む
- 【特集:新・読書論】「大正知識人」としての小泉信三/武藤 秀太郎
- 【特集:新・読書論】読書論の現在──教育の中の読書/山梨 あや
- 【特集:新・読書論】経験としての読書──環境から見る本の未来/柴野 京子
- 【特集:新・読書論】「完全な読書」が消える未来?/佐藤 卓己
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉電子書籍の現在と未来/松井 康子
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉❝読書会❞という読書のかたち/瀧井 朝世
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉周辺部を読む「古典」/橋本 陽介
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉人類の智慧の宝物庫/藤谷 道夫
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉検索時代にリアルな本との出会いの場を作る/幅 允孝
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典と現在の狭間で/堀 茂樹
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典との対話/阿川 尚之
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉とっぴな楽しみ/湯川 豊
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

松岡 享子(まつおか きょうこ)
公益財団法人東京子ども図書館名誉理事長・塾員