【特集:新・読書論】
〈私にとっての古典〉周辺部を読む「古典」/橋本 陽介
2020/05/11
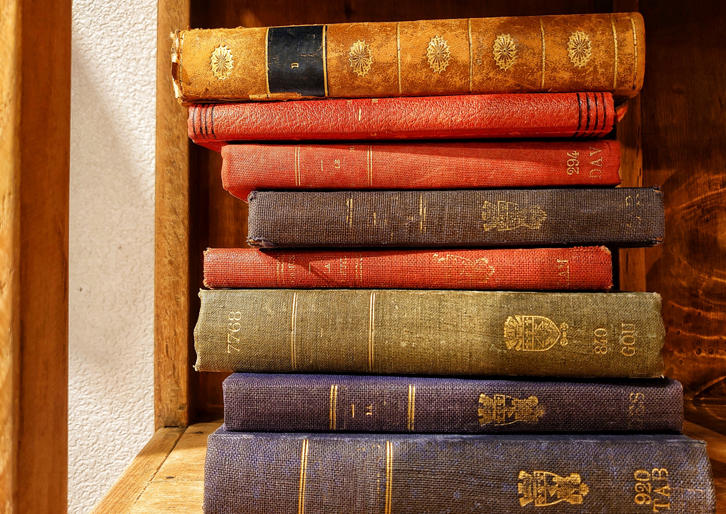
『論語』以外は読まれない古典
「古典」と聞くと、第1に思い浮かべるのは、学校で学習する古文や漢文であろう。古文・漢文と言えば、役に立たないものの代表のように思われていて、教育課程の中でも縮小され続けている。
一方で、日本人は古典が好きなのではないかと思うこともある。例えば『論語』に関する本は毎年のように同じようなものが発売されていて、しかもそのうちのいくつかはベストセラーになっているという。近現代文学でも、光文社の古典新訳文庫ではドストエフスキーが目立って売れていた。
だが、同じ諸子百家でも『論語』以外は全く売れず、海外文学もほとんど売れないという。
おそらく、『論語』やドストエフスキーが売れる現象は、一種の権威主義や滅びかけの教養主義と結びついているのであろう。最低限『論語』やドストエフスキーくらいは読んでおかなければならない。そういう意識が見て取れるように思われる。
古典は時間の淘汰を経て生き残ってきたものだから、それだけでも一定の価値があるとは思われる。だが、「価値のあるありがたいもの」とあらかじめ考えてしまうのもまた、我々の目を曇らせてしまう。フラットな目線で読み、評価できなくなる。それに『論語』のように特に有名な一部の権威だけが読まれることにもなる。私はむしろ、古典の周辺部にも目を向けること、全体を通じて評価することが重要なのではないかと思っている。
「諸子百家マラソン」
私は以前、数年かけて「諸子百家」を通読するマラソンを行ったことがある。通読すると、選び出された「名句」を読んだり、概説を読んだりするのとは違った読みを行うことができた。全体を読むことによって相互の関係性もわかるし、個性も明らかになってくる。有名な部分以外にも、自らの関心を向ける対象が見つかる。
『孟子』の中の孟子は傲岸不遜だ。「五十歩百歩」のたとえ話は、「俺は他国より善政を敷いているのになぜ民が増えないんだ」という王に向かって言い放つ話で、よくこんなことばかり言って殺されなかったものだと思う。
『韓非子』は人間不信が半端ではない。いかに人を信じてはならないかが書かれている。儒教批判も厳しい。「矛盾」は堯舜(ぎょうしゅん)がともに聖王であるとする儒教を批判する文脈で登場するたとえ話である。
『荀子』は礼による統治を主張しただけあって、文章も硬くて官僚的である。まじめすぎて私には面白くない。鬼神の存在・超常現象はすべて嘘だと喝破する。リアリストなのである。
一方、『墨子』は超常現象が実在することを証明しようとする。積極的平和主義を説き、攻撃される側を集団で守りに行っただけあって、詳細な土木マニュアルも書かれている。にもかかわらず、「敵が西から来たならば、これを西壇で迎え撃つ。壇の高さは9尺、堂の深さは9、90歳のもの9人で祭りを司る。白旗に素神、長さ9尺のもの9。弩が9つで9回発射してやめる。」のような珍妙で魔術的な防御法も書かれている。概説本にこうした部分はまず掲載されるまい。
『墨子』がストイックな節約を説くのに対して、『荘子』は、そんなことでは人生面白くないと反論する。『荘子』の文章は皮肉的で演劇的であり、よく一緒にされる『老子』の詩的文章とは趣がことなる。思想的にも『老子』は政治的だが、『荘子』は徹底的に個人主義である。
「ノーベル文学賞」マラソン
ノーベル文学賞を取るような作家の小説は、現代文学の「古典」と呼んでもいいようなラインナップであるが、残念ながらほとんど読まれていない。私は1980年代以降に受賞した作家の作品をすべて読むマラソンを行ったことがある。良質な小説群であるが、ドストエフスキーのようには関心が向けられておらず、 残念でならない。
ノーベル文学賞については、政治的であるとか、偏っているなどといった批判を目にすることがある。特定の人たちが特定の価値観で選んでいるので、偏りがあるのは確かだが、それでも世界中から様々なタイプの作家を選ぼうとはしているように思われる。読まない理由にはならない。
以上、私が行った2つの「読書マラソン」について、簡単に言及してみた。古典とされるものについては、さすがに現代でも読むべき価値を持ったものは多い。ただし、ある特定の、それも一部を読むのではなく、周辺部分を含め、通読してみると、自分なりの発見をすることができるのである。
2020年5月号
【特集:新・読書論】
- 【特集:新・読書論】座談会:AI時代に古典を読む
- 【特集:新・読書論】「大正知識人」としての小泉信三/武藤 秀太郎
- 【特集:新・読書論】読書論の現在──教育の中の読書/山梨 あや
- 【特集:新・読書論】経験としての読書──環境から見る本の未来/柴野 京子
- 【特集:新・読書論】「完全な読書」が消える未来?/佐藤 卓己
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉電子書籍の現在と未来/松井 康子
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉❝読書会❞という読書のかたち/瀧井 朝世
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉人類の智慧の宝物庫/藤谷 道夫
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉検索時代にリアルな本との出会いの場を作る/幅 允孝
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典と現在の狭間で/堀 茂樹
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典との対話/阿川 尚之
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉とっぴな楽しみ/湯川 豊
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉子どもと❝本のたのしみ❞を分かち合う/松岡 享子
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

橋本 陽介(はしもと ようすけ)
お茶の水女子大学助教・塾員