【特集:新・読書論】
〈私にとっての古典〉古典との対話/阿川 尚之
2020/05/11
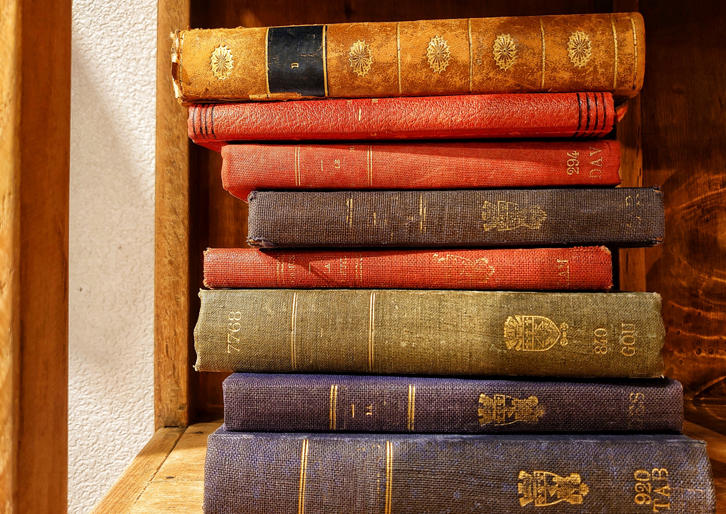
初めて古典に接したのは中学3年の春だった。大病にかかり数年間学校へ通えず、ようやく復学した麻布中学で『論語』と『平家物語』を読まされた。2年生までに漢文と古文の基礎を終えて、いきなりこの2つを課す。他の本は一切読ませない。
休学のため基礎を十分学んでおらず、いささか面食らったが、初めて触れた「子の燕居、申申如たり、夭夭如たり」という『論語』のことば、鬼界が島に1人置き去られた俊寛が「足摺りをして『これ乗せていけ、具して行け』とをめき叫」ぶ『平家物語』の一節などは、心にしみた。2つの本はその後も折にふれて手に取り、読み返している。
もっとも学生時代はあまり古典に縁がなかった。その後法律を学び仕事にしたため、さらに遠のいた。しかし大学で教えるようになって自分があまりにも基本的な書物を読んでいないのに気づく。そこで慶應の学生諸君と一緒に、まずは専門のアメリカ憲法に関連する古典を読み始めた。同志社でも続けている。
古典に共通するのは数百年、時には千年以上も前に書かれた内容が、今も読まれているという事実である。同時代の無数の書物の中でごく一部の作品が、繰り返し書き写され刷られて生き残った。これがいかに大変なことかは、物書きの端くれとしてよくわかる。
長い歳月を経てなお読まれるのは、古典と呼ばれる書物にそれぞれ深い思想や新鮮な考え方が詰まっていて、人々の脳を刺激するからだろう。もちろん難解でなかなか頭に入らないものもある。色々原因があろうが、訳文にも問題がありそうだ。
それでも古典を一緒に読んで、著者の言いたいことが存外ストレートにわかるという感想を、しばしば学生諸君からもらった。同感である。
思想史の教科書を読んでもよくわからない社会契約、抵抗権といった『統治二論』でロックが展開した概念も、原著の文章では具体的な例で丁寧に説明してあり、理解できる(気がする)。いかなる時に君主に抵抗してよいかを説く記述からは、革命に揺れた17世紀英国の王の臣下としてのためらいが伝わってくる。一方バークが『フランス革命の省察』で隣国の王政打倒を批判する時には、言葉が過ぎて暴走しがちである。福澤諭吉にも筆が走る傾向がある。古典の著者もそれぞれ癖がある。それがまた面白い。
優れた古典を読んでいると、著者が読み手に直接語りかけてくるような感覚さえ味わうことがある。「久しいかな、われまた夢に周公を見ず」という孔子のことばからは、挫折を繰り返すため息さえ聞こえてくるようだ。
19世紀前半の思想家トクヴィルの著作もそうである。国際政治の教科書で名前を知ったこの人の本を、その後アメリカを考える度に何度も読み返した。貴族の家に生まれたトクヴィルは、革命後の故国の混乱を深く憂いつつ1831年に10カ月間合衆国各地を訪れ、その経験をもとに帰国後『アメリカのデモクラシー』を著した。民主主義の利点と弱点、自由と平等、公と私のバランスなどについて深い洞察を残した。
若い時に胸を病み、肖像画からも華奢な体つきであったのがわかるこの人は、温かい性格の持ち主であったようだ。著書のそこここに、アメリカで遭遇した人々の様子や周囲の景観が生き生きと描かれている。例えばミシガンの深い森の奥で忽然と姿を現す開拓民の丸太小屋の描写。
「旅行者が夕刻そこに近づくと、板壁を通して、炉の火の輝きが遠くから見える。夜、風が立つと、森の木々のなかで小枝ぶきの屋根がざわめくのが聞こえる」
この部分を読むと、200年近い昔、トクヴィルと一緒に森の中を歩いているような気さえする。彼はこうした開拓民の丸太小屋を、「樹海に取り残されて漂う文明の方舟」と形容した。ここにアメリカの原点がある。
トクヴィルは、アメリカ滞在中に憲法の父と呼ばれるマディソンが著書『ザ・フェデラリスト』で説いた民主主義の欠点である多数の横暴という考え方に触れ、自著に取り入れた。トクヴィルから大きな影響を受けたミルは、『自由論』でこの考え方をもとにして個人の自由を論じた。
そのミルの思想を日本へ紹介したのが福澤である。『ザ・フェデラリスト』『アメリカのデモクラシー』『自由論』、そして独立自尊の思想を展開した福澤の『学問のすヽめ』『文明論之概略』は、こうして1つにつながっている。国も時代も異なる4人が書物を通じて対話をし、それぞれの思索を深めた。
古典は1度か2度読んで理解するものではない。その内容は時に矛盾してもいるから、1つの解釈が正しいわけでもない。そうだとすれば読者は心に響いた古典を何度も手に取って著者との対話を繰り返し、自らの思索の糧とするのがよいだろう。
はるか昔、筆を手にとった古典の著者が何を言いたかったのか。その思いを共有する。現実には会えなくても、残された著作を通じて著者を心の友(Kindred Spirit)とする。古典を読むというのは、そういうことであるように思う。
2020年5月号
【特集:新・読書論】
- 【特集:新・読書論】座談会:AI時代に古典を読む
- 【特集:新・読書論】「大正知識人」としての小泉信三/武藤 秀太郎
- 【特集:新・読書論】読書論の現在──教育の中の読書/山梨 あや
- 【特集:新・読書論】経験としての読書──環境から見る本の未来/柴野 京子
- 【特集:新・読書論】「完全な読書」が消える未来?/佐藤 卓己
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉電子書籍の現在と未来/松井 康子
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉❝読書会❞という読書のかたち/瀧井 朝世
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉周辺部を読む「古典」/橋本 陽介
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉人類の智慧の宝物庫/藤谷 道夫
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉検索時代にリアルな本との出会いの場を作る/幅 允孝
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉古典と現在の狭間で/堀 茂樹
- 【特集:新・読書論】〈私にとっての古典〉とっぴな楽しみ/湯川 豊
- 【特集:新・読書論】〈読書の風景〉子どもと❝本のたのしみ❞を分かち合う/松岡 享子
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

阿川 尚之(あがわ なおゆき)
同志社大学特別客員教授、慶應義塾大学名誉教授