【特集:慶應義塾の国際交流】
座談会:国際化をさらに進めるために何が必要か
2024/10/07
-

-
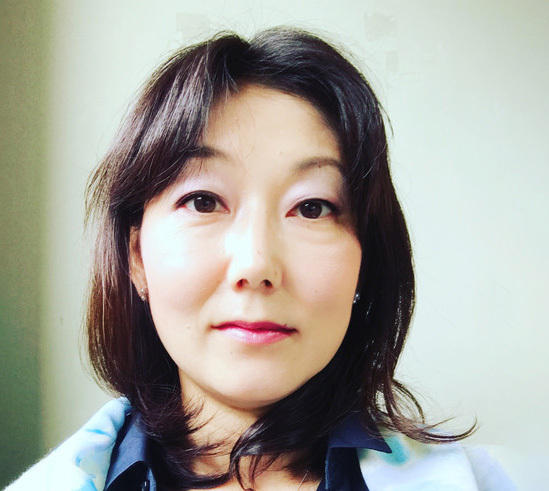
大串 尚代(おおぐし ひさよ)
慶應義塾大学文学部英米文学専攻教授、同大学国際センター所長
塾員(1994文・96文修・2001文博)。博士(文学)。ブラウン大学アメリカ研究学部訪問研究員等を経て2006年慶應義塾大学文学部准教授。14年同教授。専門はアメリカ女性文学、ジェンダー研究等。
-

三木 則尚(みき のりひさ)
慶應義塾大学理工学部機械工学科教授、同学部国際交流委員長
2001年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。マサチューセッツ工科大学航空宇宙工学科研究員を経て04年慶應義塾大学理工学部専任講師、17年より同教授。体育会スケート部部長。専門はマイクロナノ工学等。
-
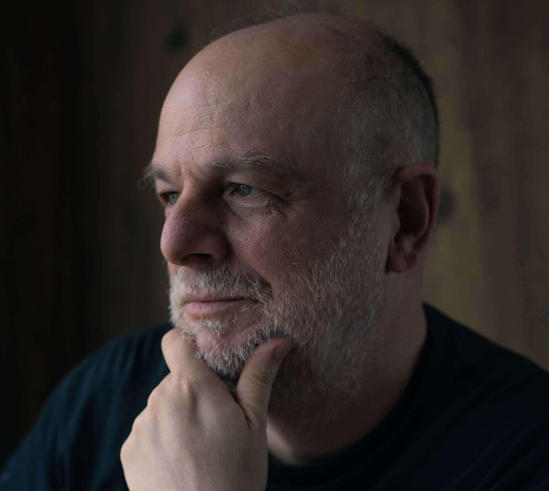
ロドニー・バンミーター(Rodney Van Meter)
慶應義塾大学環境情報学部教授
1991年南カリフォルニア大学でコンピュータ工学の修士号、2006年慶應義塾大学でコンピュータサイエンスの博士号取得。専門は量子コンピュータアーキテクチャ等。19年より現職。
-

土屋 大洋(司会)(つちや もとひろ)
慶應義塾常任理事(国際担当)、同大学大学院政策・メディア研究科教授
塾員(1994政・96法修・99政メ博)。博士(政策・メディア)2011年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授。19年総合政策学部長。21年常任理事。専門はサイバーセキュリティ、国際関係論。
留学経験から得たもの
土屋 今日は「慶應義塾の国際化」に関する座談会のために皆様にお集まりいただきました。その目的は、慶應義塾が国際化に向けて現在何をしていて、将来に向けて何をすべきかを理解することです。そして、慶應の塾生たちに国際的な経験を積んでもらうよう促すことです。未来志向の議論にしたいと思います。
慶應義塾はご存知のように福澤諭吉によって設立されました。福澤は19世紀にアメリカとヨーロッパ諸国を訪問した後、この学校を整えていきました。彼は西洋諸国から新しいものを得て、日本人を教育したいと考えました。それが慶應義塾の始まりです。
そういう意味で私たちは当初非常に国際化された学校でしたが、今日では必ずしもそうではないかもしれません。私たちはより多くの留学生を受け入れ、他方でより多くの学生を海外に送りたいと思い、より多くの海外の大学との協力を望んでいます。しかし、それにはいくつかの課題があります。
最初に皆さんに簡単な自己紹介をしていただくとともに、海外留学や在外研究において最もインパクトのあった出来事を伺いたいと思います。
まず私の経験から話したいと思います。私は現在、慶應義塾の国際担当常任理事を務めていますが、外国の大学で学位取得のために勉強したことは一度もありません。
しかし、慶應で博士号を取得後、ワシントンDCに客員研究員として1年間行き、半年はメリーランド大学で、次の半年はジョージ・ワシントン大学で過ごしました。
ところが、現地に到着してから2カ月後、9・11の同時多発テロに遭遇しました。その日、私は会議のためにサンフランシスコにいましたが、1週間ワシントンDCに戻ることができず、ただ飛行機を待っていました。
その時、インターネットの世界でも何か悪いことが起こるのだということに気づきました。私はそれまでインターネットの明るい面ばかり見ていて、インターネットはより良い方向に世界を変えると思っていました。しかし、このテロ攻撃の後、「悪者」もインターネットを悪用していることに気づき、それから、専門をサイバーセキュリティに転向したのです。
それは私の人生を変える出来事でした。このようなことが誰にでも起こるとは思いませんが、留学中に起こったことがその人の人生を変えるということはあるかもしれません。そういうことからも慶應の学生にもっと国際的な経験をしてほしいと思っています。
まず、皆さんにご自身の留学や海外での研究について伺いたいです。大串さんからいかがでしょうか。
大串 私は文学部英米文学専攻で教鞭を執っていますが、同時に国際センター所長を務めています。
国際センター所長としての私の主な仕事は、全塾を対象とした交換留学プログラムを統括することです。基本的には、海外に出る派遣学生を選考し、交換留学生として慶應義塾大学で学ぶ学生の受け入れをしています。受け入れは半年単位ですが、派遣は基本的に1年間で塾生に海外経験の機会を提供しています。
現在、146の海外の大学と交換協定を結んでおり、海外から500人以上の交換留学生を受け入れ、義塾からは約270人程度の学生を世界中に派遣しています。
私自身も交換留学生でした。その経験は現在の自分の学問への歩みに大きな影響を与えた貴重な経験であると思っています。
私は、慶應からの派遣生としてオレゴン大学に留学し、1年間英文科に所属しました。慶應と留学先でアメリカ文学についてしっかりと基礎知識を身に付けたことが、現在の私の研究の強固な基盤となりました。この経験はとても良い組み合わせだったと思います。慶應で学んだ知識を元にしてアメリカでさらに専門知識を身に付けることができたからです。
オレゴン大学では、アフリカ系アメリカ文学や文学批評、また女性学などの講義を受講しました。当時、こうした内容は慶應では特化された形ではほとんど開講されていませんでした。また、実技科目もあり、とても楽しいボーカルトレーニングの講義も履修しました(笑)。人生でも最も充実した1年を過ごすことができました。
他にも、外国で日常生活を送るという行為そのものが、私にとって大きな意味がありました。スーパーマーケットに行ったり、映画館に行ったり、寮で仲間と楽しんだりしたことが、すべて大切な思い出になっています。
ちょうどアメリカにいた時、ロドニー・キング事件によるロサンゼルス暴動があり、大学内でも集会が開かれました。それも非常に衝撃的な経験でした。それまでもアメリカのニュースには関心をもっていましたが、日本にいた時は遠く離れた場所でのことでしかありませんでした。しかし、アメリカで知るニュースはもっと身近に感じられ、アメリカについてもっと知りたいと思いましたし、同時に自分の国についてももっと知らなければと思いました。それが、私がアメリカにいた時に経験したことです。
MITでの経験
土屋 次に三木さん、お願いします。
三木 私は現在、慶應義塾大学理工学部の機械工学科主任と国際交流委員長を務めています。
理工学部は、国際活動の推進という点では最も積極的な学部の1つだと自負しています。1週間の短期留学コースから、最長で2年間留学する欧州の大学とのダブルディグリープログラム(修士課程を卒業すれば慶應と欧州の大学の両方から修士号を授与されます)まで提供しています。最近は博士課程学生を対象にした英国の大学とのプログラムも始めました。
私は慶應に来る前、MIT(マサチューセッツ工科大学)で3年間ポスドクとリサーチエンジニアをしていました。働いていたので厳密には留学生ではなかったです。博士号は東京大学で取得したのですが、その最終年度の2000年の夏、MITでの将来のボスになる人がたまたま研究室にやって来ました。彼が進めていたMITマイクロエンジンプロジェクトのことを知っており、興味もあったので、勇気を出してMITでポスドクポジションがあるか聞いてみました。すると、彼は笑顔で私にレターを送るようにと。
初めて英文のカバーレターを書き、指導教員の推薦状とともに送ると、面接に呼んでいただきました。その時の私ですが、「MITってどこにある?」「お、ボストンらしい。なんかいい感じ」「で、ボストンはどこにあるの?」「東海岸らしい」。その程度の国際性でした(笑)。
結果、無事採用され、修了後渡米し、MITマイクロエンジンプロジェクトで3年間働きました。2004年に日本に帰るまでのボストンでの日々は、最高で、そして視野をぐっと広げる(eye-opening)ものでした。
私の学生時代は、朝から夜中まで研究室にいて、午前3時に家に帰るような日々で、また、エンジニア仲間の友人しかいないような非常に狭い範囲で暮らしていました。しかし、ボストンでの生活は違いました。ボストンにはハーバード大学をはじめ複数の大学があり、日本からも、医師、政治家、ビジネススクールに通うビジネスマンなど、様々なタイプの人々が留学していました。様々な人と知り合い、その中で私はSushisという日本人のアイスホッケーチームをつくりました。
ボストンでの生活は、私をある意味白紙にしてくれたと思います。偏っていた自分が矯正されて、知見、視野が広がったと思います。現在私は、7年前に会社を立ち上げた経験から義塾における起業家育成の活動にも関わっています。その会社は結果的には上手くいきませんでしたが、MITやボストン時代の友人たちが立ち上げを手伝ってくれました。このように当時の友人とは20年たっても、仕事でもプライベートでも大変仲が良いです。
また、当時のラボでの親友の1人はベトナム難民でした。日本から遠く離れたところで起こったベトナム戦争をとても身近に感じました。最近も似たような経験をしました。
新型コロナウイルス感染症の世界的流行が終わった頃、私たちはようやく留学生たちを受け入れられると期待していました。しかしその時、ロシアがウクライナに侵攻したのです。その直後は、正直に言うと日本から遠い場所での出来事だと感じていました。しかし、留学生にロシア人学生がいたことで、一気に当事者意識が高まりました。さらに、ロシア人の考えも知ることができました。
日本のテレビ番組は、基本ウクライナ側の話のみですが、私は彼女からロシア人の本当の気持ちを聞きました。彼女はウクライナに多くの友人、親戚がいると話してくれました。もう1人いたロシア人留学生は、翌年、ウクライナから理工学部にやってきた留学生を案内してくれました。非常に不思議な状況でした。このように国際的な経験や活動があれば、物事を別の視点から見る機会を得ることができ、出来事の真実に近づくことができるのです。これが国際化についての私の経験です。
研究のために慶應に
土屋 では、バンミーターさん。慶應で博士号を取得されましたが、なぜ慶應に来られたのですか。
バンミーター 私は南カリフォルニア大学の研究機関で働き、その傍ら修士号を取得し、その後、日本と米国の企業で働きました。私はアカデミアと産業界の両方で働いた後、博士号を取得して、通常のコンピューティングシステムから量子コンピューティングへと、研究の方向(または雇用の方向)を変えたいと考えました。
そこで、私は1990年代に数年間日本に住んでいたので、日本で博士号を取得し、さらに数年間日本で過ごしたいと考えたのです。実は、東大の教授と伊藤公平さん(現慶應義塾長)にメールを送ったんです。伊藤さんは返信をくれたんですが、東大の教授は返信してくれませんでした。それで慶應に来たのです。最近は私もメールをほとんど読まないので、優秀な学生を見逃しているような気がします(笑)。
インターネット関連の研究で最も有名な研究所の1つの南カリフォルニア大学で働いていた私は、インターネットコミュニティで有名な村井純さん(慶應義塾大学教授)の名前を慶應義塾大学よりもよく知っていました。村井さんが慶應出身なので、きっとよいところだろうと思いました。
ノキアで働いていた時、当時慶應の博士課程の学生だった湧川隆次さん(現ソフトバンク先端技術研究所所長)が、学生インターンとして働いていました。彼は本当に優秀でした。慶應が皆、隆次のような人だったら、素晴らしい場所だと思いました。彼が村井研究室史上ナンバーワンの大学院生だったとは知りませんでした。そのようにして、私は矢上キャンパスに来ました。私の指導教員は物理情報工学科の伊藤さんと寺岡文男さんで、私は偶然にも矢上の国際プログラムの最初の博士課程の学生の1人でした。
私は博士課程を終える頃、米国でテニュア(終身在職権)の職を探し始めました。そうしたところ、湘南藤沢キャンパス(SFC)の村井さんから電話があり、「SFCのテニュアに応募してほしい」と言われました。そして今、17年が経ちました。予想もつかないような紆余曲折が起こることもあるのです。
日本に来ることが、予め私自身の長期計画の一部だったわけではありませんが、日本は今、私が住み、働いている場所であり、家族、住宅ローン、義母、学生、終身在職権、プロジェクト、大学での役職を抱えています。人生にはそういうことが起こるのです。
私は一部の人のように、もとから日本文化に魅了されていたり、日本を敵視したりしていたわけではありません。1992年に日本に初めて来た時、私は日本語をまったく話せませんでした。はっきり覚えているのは、初めて食料品店に行って買い物をしようとして、通路で黄色い液体が入ったペットボトルをひっくり返して、これが食器用洗剤なのか食用油なのかを見極めようとしたことです。まあ、両方とも必要だし、買ったほうがいいわけですが(笑)。
土屋 では、あなたの人生を変えた瞬間は、伊藤さんからのメールだったわけですね。
バンミーター はい、そうです。道の途中で何が起こるかは本当にわかりません。でも、人生には、決断を下しても、その道がどこにつながっているか、また、別の道がどこにつながっていたかもわからない時があります。
2024年10月号
【特集:慶應義塾の国際交流】
- 【特集:慶應義塾の国際交流】大串 尚代:慶應義塾の国際化の現状
- 【特集:慶應義塾の国際交流】マリー・ラール/リシア・プロセルピオ/カミーユ・カンディコ・ハウソン:日本の大学における国際化とランキング・ゲーム
- 【特集:慶應義塾の国際交流】中妻 照雄:次世代のグローバルリーダーを育てるCEMS MIMプログラム
- 【特集:慶應義塾の国際交流】萩原 隆次郎:一貫教育校の国際交流
歴史の上に展開している交流プログラム - 【特集:慶應義塾の国際交流】中嶋 雅巳:一貫教育校の国際交流
一貫教育校が非英語圏の学校と交流する意義 - 【特集:慶應義塾の国際交流】石井 涼子:一貫教育校の国際交流
一貫教育校派遣留学制度──世界にまたがる人間交際
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

アンネリーズ・ライルズ(Annelise Riles)
ノースウェスタン大学アソシエート・プロボスト、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授
ノースウェスタン大学法学・人類学教授。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで社会人類学の修士号、ハーバード大学ロースクールで法務博士号、ケンブリッジ大学で社会人類学の博士号をそれぞれ取得。