【特集:「トランプ後」のアメリカ】
座談会:「分断」の先に何が見えるか
2021/02/05

-

-

金成 隆一(かなり りゅういち)
朝日新聞国際報道部機動特派員
塾員(2000政)。朝日新聞社入社後、大阪社会部、ニューヨーク特派員、経済部記者を経て現職。ボーン・上田記念国際記者賞受賞。2016年選挙よりアメリカ各地を精力的に取材。著書に『ルポ トランプ王国』等。
-

岡山 裕(おかやま ひろし)
慶應義塾大学法学部教授
1995年東京大学法学部卒業。博士(法学)。東京大学大学院総合文化研究科准教授等を経て、2011年より現職。専門はアメリカ政治・政治史。著書に『アメリカ二大政党制の確立』、『アメリカの政党政治』等。
-

中山 俊宏(なかやま としひろ)
慶應義塾大学総合政策学部教授
2001年青山学院大学大学院国際政治経済学研究科博士課程修了。青山学院大学国際政治経済学部教授等を経て14年より現職。博士(国際政治学)。専門はアメリカ政治・外交。著書に『アメリカン・イデオロギー』等。
-
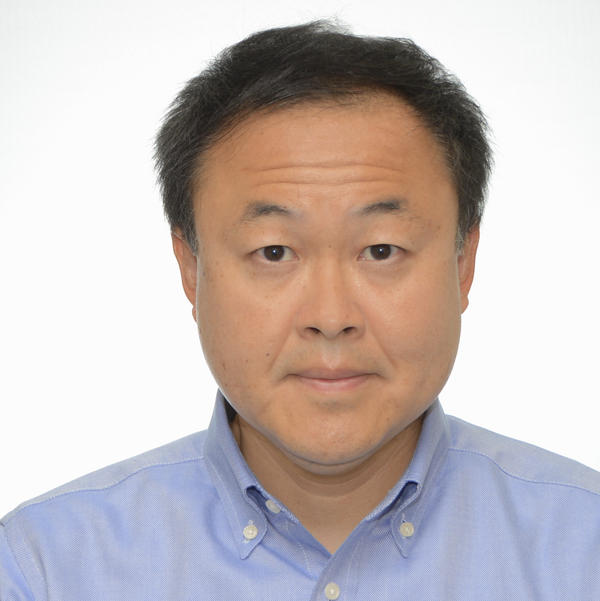
渡辺 靖(司会)(わたなべ やすし)
慶應義塾大学環境情報学部教授
1997年ハーバード大学Ph.D. パリ政治学院客員教授等を経て2005年より現職。専門は社会人類学、現代米国論。著書に『アフター・アメリカ』、『リバタリアニズム』、『白人ナショナリズム』等。
コロナ禍のアメリカで見た選挙戦
渡辺 2020年11月にアメリカ大統領選挙が行われ、その後投開票をめぐってやや混乱がありましたが、民主党のバイデン氏が勝利しました。今日は、「なぜバイデンが勝ったのか」「トランプ現象は続くのか」といった議論の、少し先を見越したものにできればと思っています。
まず、岡山さんは春からアメリカに滞在され、金成さんも選挙前後に取材に行かれていますので、日本の報道や世論調査と現地でお感じになられたことの温度差について、お話しいただければと思います。
岡山 私がこちらで所属しているコーネル大学は、ニューヨーク州のイサカ市にあります。ここはマンハッタンから北西に自動車で3時間程というかなりの田舎ですが、大学町なので非常にリベラルで人種的にも多様です。
ところが車で町の外を10分も走ると、「トランプ・ペンス」のサインボードだらけで、2つの世界を見ているようなところがあります。
コロナが蔓延して基本的に閉じこもっている状況ですが、ご質問に関連して、こちらの人と話していて改めて思うことがあります。日米の報道で注目される人たちは、民主党・共和党どちらかの陣営に肩入れしている人ばかりです。そういう人は実際多いわけですが、一般の人には、ある意味当然ながら、この状況下でも政治に大した関心がない人もそれなりにいるわけです。
そういう人は、保守とリベラルのイデオロギー的立場の違いもよく分かっていない。こうした人たちの存在を忘れてはいけないと思わされました。
他方で、政党に肩入れしている人の支持の仕方も特徴的で、今日のアメリカ人の党派性については、政治学でも2つ特徴が指摘されています。1つはネガティブな性格をもつこと、もう1つは感情的なものだということです。
ネガティブな政党支持とは、好きな政党でなく嫌いな政党が先にあって、嫌いでない方を支持すること。感情的とは、政党への態度が争点への立場などでなく文字通り好き嫌いに基づいていて、「あっちは気に食わない」とその対立政党を支持するということです。
ですので、多くの人はトランプなどその党の政治家と反りが合うかどうかで、感覚的に支持を決めている人が少なくないのです。また所詮「嫌いでない方」への支持なので、実は政党への支持意識が格別強いとは限りません。こうしたことを踏まえる必要がある、と改めて思いました。
渡辺 バイデンが勝利したことについてのキャンパス内外での反応はどんな感じですか。
岡山 当確が出た時には、リベラル色の強いキャンパス内は大騒ぎという感じでしたね。一方で、市の中心部ではたまにプラカードを掲げて車に箱乗りして快哉を叫ぶ支持者が通るという程度で、集まって盛り上がる様子は見られませんでした。保守派も多い場所柄、暴力沙汰も懸念される状況で大きく騒ぐのは憚られたのかもしれません。
渡辺 なるほど。岡山さんの肌感覚として、コーネル大学でもトランプ支持者はそれなりにいるような感じがしましたか。
岡山 正直、量的にはわかりにくいのですが、1つ印象に残っていることがあります。春頃にコーネル大学の学生新聞の中で、大学の共和党学生団体のリーダーの学生が、自分たちは今回基本的に「ロー・プロファイル(控えめな姿勢)を維持する」と書いていました。恐らく「トランプを強く支持するわけではないけれど、民主党支持に回るのではなく、自分たちの信念に従って慎重に行動する」というスタンスだったのだろうと思います。
渡辺 有り難うございます。金成さんは機動特派員というお肩書で、アメリカに行かれていましたね。
金成 残念ながらコロナ禍で機動があまりできませんでした(笑)。今年(2020年)は3月の1カ月間と、あとは選挙前と選挙後の計1カ月間アメリカに行き、いずれもパンデミックが悪化したことに伴って帰国しました。
今回の大統領選は仕方なく電話取材がメインとなりましたが、最初に気づいたのは世論調査とのギャップでした。バイデンが世論調査で、相当強く出ていることが分かっていました。しかし、「そうであれば、この人はもうそろそろトランプ支持から離れているだろう」と思って電話をしても、意外なことに支持が逆に強まっている人が複数人いた。それで「あれ、おかしいな。世論調査と一致しない」と感じていました。結果論ですが、トランプは得票数を前回より大きく伸ばしたわけで、あの違和感は間違っていなかったと思っています。
渡辺 トランプはコロナ対応を批判されたり、人種問題が噴出したりと逆風だったわけですが、それでも支持がはがれないという理由はどんなものだと感じましたか。
金成 私が取材してきた人は、アパラチアや、オハイオなどラストベルト地域の人が多く、エネルギー関連産業で働いていたり、その恩恵を受けている人が相当数いる。するとバイデンが掲げる、化石燃料からのトランジション(転換)という話は相当マイナスに効くんですね。当然バイデンは「ゆくゆくはそうなるだろう」と発言しているわけですけれども。
最後の討論会で、バイデンがそれを言った時に、「一定の支持が離れる」と感じたんですが、やはり、これまで2016年の大統領選以外はすべて民主党に入れているような人も、バイデン政権では賃金のよい雇用の場がなくなってしまう、と懸念し、「今年もトランプにした」と言っていました。
もう1つ、民主党が左傾化している、過激になっているという認識が、おそらくメディアを通して実態以上に増幅されている気がします。民主、共和のどちらかを選ぶ選挙ですから、民主党のそういうイメージが強まると、鼻をつまんででもトランプに入れ続ける人がいるとは感じました。
中山 2019年の11月に、ウィスコンシンで講演した時のことです。その時は、民主党がまだ候補を絞り込めておらず、全体の雰囲気で何となくトランプが押している感じでした。
日本の大学教授が話すところにわざわざ来るのはリベラルな民主党系の人が多かったのですが、講演が終わった後に小さなメモを持った人が、「聞きたいことだけを聞くな」というメモを置いて去っていきました(笑)。実は数年前、テキサスでも同じことがありました。
露骨に、「私はトランプ支持者だ」とは言わないけれど、微妙な感じで自分の存在を示した人がいたことが印象的でしたね。
トランプ現象と「分極化」
渡辺 不気味ですね(笑)。反トランプ感情が勝ってバイデンが勝った。ただ、トランプに対する得票率も得票数もそれなりにあるので、共和党内への影響力も保持してトランプ時代は続く、と言われています。
この4年間、トランプがここまで躍進をして、共和党の主流派たちをなぎ倒してアメリカの大統領であったことをどう位置付けるのか。
私から見ていて、もちろん批判点もいろいろあります。しかし、金成さんが接してきているような、これまで共和党の主流派からも完全に見放されたと思っているような、「忘れられた人々」が、トランプという過激な存在を通して選挙プロセス、政治プロセスの中に回帰したという面もある。そうすると、必ずしもトランプが、民主主義の破壊者であるというよりは、むしろアメリカ民主主義の健全さを示している、という解釈もできるかもしれない。
かつてアンドリュー・ジャクソン(第7代大統領)が、東部出身のエリートばかりだった大統領の中で、初めて西部の極貧の出身で教育も特に受けてないにもかかわらず当選し、今もある政治任命(猟官制)のシステムを導入した。エリートだけにワシントンを支配させないように、言ってみれば大衆からの反逆を体現したこともあります。
そう考えるとアメリカの中で、社会がピラミッド化した構造になってしまった時に、何かトランプ的な力で、それを平坦にしようとする動きというのは、政治以外の分野、例えば宗教などでも起きている。それはリチャード・ホフスタッターの言う「反知性主義」、つまり反権威主義と言い換えてもいいと思います。
ある意味トランプ現象は、ヨーロッパのような身分制社会は避けたいという、アメリカ的な動きとして前向きな評価もできるかもしれない。
待鳥さんはトランプの強さ、あるいはトランプ現象を、どう位置づけられますか。
待鳥 トランプやトランプ現象は、アメリカ政治の分極化を抜きに考えることはできないと思います。
20世紀以降のアメリカ政治を長期的なスパンで眺めた時に、重要な柱が2つあります。1つは民主党と共和党の2大政党が争っていること。もう1つは、議会と大統領に権力が分立していることです。そして、この2つの柱の関係が政治のあり方に影響してきました。権力分立と2大政党の軸の間で、綱引きのように競争する状態がずっと続き、それがアメリカ政治の変化をもたらしてきた、ということです。
ところが最近は権力分立側が一方的に負けていて、アメリカ政治の中で政党間対立が圧倒的な意味を持つようになっている。本来、どちらかが圧倒的にならないのが、アメリカ政治の特徴だったと思うんですが、それが失われ、変わってきていると感じます。
政党間対立の極端な強まりを「分極化」と呼びますが、分極化が権力分立を圧倒するようになったのは2010年代に入ってから、という印象です。9・11のテロ(2001年)では、一種の戦時として大統領に集権化しました。その後に通常の権力分立に戻らず、政党間対立がすべてに優先される状態になって、オバマ、トランプの時代が続いてきたと私は思います。
トランプは2016年の大統領選挙では、分極化とは一線を画する姿勢も見せたわけですが、就任後は非常に党派的になり、自分の支持者にだけ、あるいは共和党の支持者にだけ訴求することを厭わない大統領になりました。
普通は逆で、選挙中は党派的であっても、当選すると一応ポーズだけでも国の尊厳的地位を担って、ワシントン以来の伝統を引き続く超党派的な指導者になるんだ、と言うはずですが、トランプはそういうことをほとんど言わなかった。むしろ、当選後の方が党派的になったとさえ言えます。
その一因は、政党間対立が強すぎて、超党派的な大統領という位置づけの意味が失われたことにあるのでしょう。権力分立と政党間対立の間に綱引きがあって、初めて超然とした大統領の存在意義が出てくるわけですから。
岡山さんのお話にあったように、一般の有権者は、政治に関心がない人が多い。それでも、有権者の政党支持には復活の兆しがあり、しかもかつてに比べてはるかに民主党支持者と共和党支持者の間の懸隔は広がっている。分極化を推進したのは、トップエリートと一般有権者の間にいる活動家層だったのですが、今や上から下まで全部離れている状態です。こうなると、政党間関係がアメリカ政治を覆い尽くしてしまい、脱却が難しくなります。
渡辺 政党政治が前面に出てきて、より重い存在になったのは、どうしてだと思われますか。
待鳥 最近10年に注目すれば、特に民主党側の動きが顕著ですね。もともと民主党は、経済的弱者と文化的少数派の利害関心を表出する中道左派政党でした。ところが、世界の中道左派政党はリーマン・ショック以降、経済政策で支持を確保するのが難しくなり、民主党も例外ではなかった。
そこで活路を求めたのが文化的少数派の重視でした。具体的には、地球環境問題や性的少数派の権利擁護などで、オバマはそれを先導する象徴という役割を果たしました。結果的に、民主党内でのバランスが変わり、共和党も対抗する動きを見せますから、非経済的な文化的争点を重視するように、2大政党内部も政党間競争も変わってきたのだと思います。
ラストベルトの有権者には、経済的弱者であっても文化的少数派ではない人が多い。こうした人たちの動向が決定的な要因かどうかは、いろいろな考え方があると思いますが、非経済的争点が重視されれば、伝統的な民主党支持からは離反せざるを得なくなるのだろうと思います。
2021年2月号
【特集:「トランプ後」のアメリカ】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

待鳥 聡史(まちどり さとし)
京都大学法学部教授
1996年京都大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(法学)。大阪大学法学部助教授を経て、2007年より現職。専門は比較政治論、アメリカ政治。著書に『アメリカ大統領制の現在』等。