【特集:「トランプ後」のアメリカ】
大統領選挙と音楽
2021/02/05

本誌2017年12月号の特集「分断されるアメリカ社会」に寄稿した際、私はアメリカの音楽文化の領域に保守反動的な動きはとくにみられず、「ストリーミング・サービスに代表されるメディアの変化と、音楽シーンにおけるヒスパニックやアジア系などマイノリティーの可視化」が進んでいると述べた。この傾向はトランプ政権下で最後まで弱まることはなかったといえるだろう。もはやバッド・バニー(プエルトリコ)やJ・バルヴィン(コロンビア)など、ラテンアメリカのアーティストの曲がビルボード誌の総合チャートに上がることは珍しくなく、なんといっても昨年9月に韓国のアイドルグループ、BTSが総合チャート一位を獲得したこと──アジア勢としては坂本九「スキヤキ(上を向いて歩こう)」以来、57年ぶりの快挙である──は記憶に新しい。音楽以外の領域でも映画『クレイジー・リッチ!』(2018)の大ヒット、ポン・ジュノ監督『パラサイト』(2019)のアカデミー賞受賞など、アジア人/アジア系の文化がアメリカのエンタテインメント業界に大きな潮流を生み出しており、メインストリームのカルチャーがますます多様化していることは疑い得ない。
これは昨今のアメリカの娯楽産業が(建前としてでも)リベラルであることを掲げていることと無関係ではない。もちろん、アカデミー賞やグラミー賞などで例年マイノリティーの候補者が少ないことが問題となるが、そうした批判があがること自体、理想としての多文化主義が前提とされていることの証左でもある。こうした点を踏まえつつ、本稿ではアメリカ合衆国で進む「分断」が音楽の領域にどのような影響を及ぼしているかについて、昨年の大統領選を中心に分析してみたい。
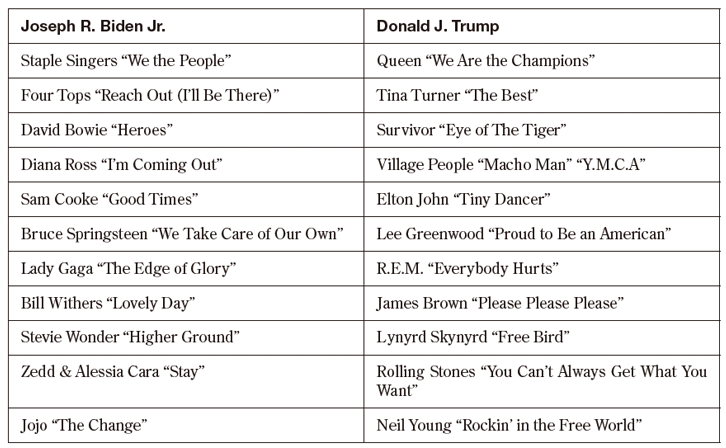
大統領選と音楽
上の表は両陣営が選挙戦で多く流した曲のリストである。皮肉なことに、クイーン、ヴィレッジ・ピープル、エルトン・ジョン、R.E.M.、ローリング・ストーンズなどのアーティスト/グループはトランプ陣営での楽曲使用を認めておらず、その妥当性をめぐって裁判で係争中であることがたびたび報じられた。だが、こうした無断使用は必ずしもトランプにネガティヴなイメージを付与するわけではなく、むしろ(腐敗した)ハリウッド・エスタブリッシュメントにひとり戦いを挑み続ける闘士という彼の(支持者にとっての)イメージを強化した。トランプ陣営の選曲は1960年代から80年代の「クラシック・ロック」が多いのが特徴だが、カウンターカルチャー世代の一部が年齢を重ねて保守化したことが窺えるだろう。
一方、バイデン陣営はよくいえば穏当、悪くいえば面白味のない選曲であり、オバマほどセンスエリートな嫌味さを感じさせず、かつ女性や黒人ミュージシャンなどマイノリティーのバランスにも配慮したリストだといえる。
では昨年8月に行われた民主党、共和党両党の全国大会で音楽がどのように用いられていたかを詳細に検討してみよう。とはいえ、実は共和党全国大会にミュージシャンはほとんど出演していない。これほど音楽が不在の大会も珍しく、後述するようにそれ自体が現在の共和党と文化産業との関係を表している。最終日にカントリー・シンガーのトレイス・アドキンスが国歌斉唱をし、オペラ歌手クリストファー・マッチオがレナード・コーエンの「ハレルヤ」のカバーを披露した(そしてそれはコーエンのファンから激しい非難を浴びた)が、党の戦略として音楽を有効活用しようという意志は感じられない大会であった。
それに対して、8月17日から20日にかけて開催された民主党全国大会は、コロナ禍の影響であらゆる音楽イベントがキャンセルされるなか、「今年最高の音楽フェスティバル」と称されるほど出演陣の華やかさが際立っていた。ジョン・レジェンドやジェニファー・ハドソン、それにヒスパニック票目当てのドミニカ系シンガー、プリンス・ロイスなどが次々にパフォーマンスを披露するなか、やはり話題を集めたのはビリー・アイリッシュだろう。昨年のグラミー賞で主要5部門を制覇した18歳のミュージシャンは「ドナルド・トランプはこの国と私たちが大切にしているすべてのことを壊している」と述べ、ジョー・バイデンに投票するよう訴えたのだ。
とりわけ興味深かったのは、最終日に国歌斉唱を行ったチックスである。カントリー・ミュージックを演奏する女性3人組のグループは、その数カ月前にディクシー・チックスからチックスへと改名したばかりである。共和党との相性の良さで知られるカントリー・ミュージックのグループが民主党大会に出演するのも異例だが、彼女たちこそ今回の民主党の戦略を象徴する人選だといえるだろう。
チックスの名前が全国紙を賑わせたのは、2003年3月、イラク戦争直前にツアー先のロンドンのステージで「私たちは大統領(ブッシュ)と同じテキサス出身であることを恥ずかしく思う」と発言したときである。この言葉はカントリー・ミュージック界に大きな波紋を広げ、保守的なファンを中心に大規模な不買運動にまで発展した。グループ名を変えたのも、昨年5月に再燃したブラック・ライヴズ・マター運動の影響が大きい。ここ数年、アメリカでは南部連合旗や南北戦争時の英雄の肖像が奴隷制を祝福するとして撤去すべきかどうか議論が繰り広げられている。「ディクシー(Dixie)」という言葉も「アメリカ南部」や「奴隷制」を含意することからその使用を控える機運が高まっており、彼女たちはイラク戦争時の発言同様、リベラルな思想に基づいてグループ名を変えたのだ。逆にいうと、昨今のカントリー・ミュージック界には若年層を中心にチックスを支持するファンが増えていることの証でもある。
カントリー・ミュージックの中でもリベラルな政治性で知られるチックスが民主党全国大会で国歌を斉唱するというパフォーマンスが、今回の民主党の戦略──共和党穏健派を取り込む中道左派路線──そのものを表している。さらにいえば、共和党大会の国歌斉唱が男性歌手の独唱であったのに対して、民主党が女性三声のハーモニーであるという点も、民主党が掲げるダイバーシティーの理念に合致するといえるだろう。
2人の民主党支持者
最後に、今回の大統領選をめぐる2人のアーティストの行動とその政治的帰結について見てみよう。1人目は、ブルース・スプリングスティーンである。ニュージャージー州フリーホールドの典型的なブルーカラーの家庭で育った彼は、全盛期に1700人近くを雇用していた地元の絨毯工場が1961年に閉鎖され、徐々に街が荒んでいく様子を目の当たりにする。「ライフロング・デモクラット(生涯民主党支持者)」として、今回の民主党全国大会でも彼が9・11をテーマに作曲した「ライジング」を用いたビデオが流された。だが皮肉なことに、ブルース・スプリングスティーンの地元ニュージャージー州モンマス・カウンティーは前回に続いて今回もトランプが勝利しているのだ。
もう1人はテイラー・スウィフトである。もともとカントリー・ミュージックの聖地ナッシュヴィルでデビューした彼女は、しばらくカントリーポップのシンガーとして活動するが、2010年代に入り、徐々にカントリー色を払拭し、メインストリームのポップスへと路線変更を図る。だがレディ・ガガやケイティー・ペリーなどが大統領選のたびに民主党候補を応援したのに対して、彼女は決して支持政党を明らかにすることはなかった。デビュー以来、支えてきたカントリー・ミュージック界のファンのことを考えると支持政党を明らかにできなかったのだ。ところが2年前の中間選挙で彼女は突然民主党支持を表明し、今回の大統領選では正式にバイデン・ハリス陣営をサポートした。穿った見方をすれば、トランプが大統領になったことで彼女は民主党支持を打ち出しやすくなったともいえる。また、チックスの例でも明らかなように、実はカントリー・ミュージックを聴く若い世代のファンが増えており、それを裏付けるかのようにナッシュヴィルを擁するテネシー州デヴィッドソン・カウンティーはかなり前から民主党支持者が多くなっている。テネシー州自体は強固な「赤い州」(共和党支持州)であり続けているので、ナッシュヴィルは典型的な「赤い州の青い町」となっている。
この2人のミュージシャンの動向を追うことで判明するのは、民主党が労働者の権利を守るブルーカラーの党から、女性や黒人などマイノリティーの権利を重んじるアイデンティティ・ポリティクスの党へと変化したことである。ブルース・スプリングスティーンの党からテイラー・スウィフトの党へ──その結果、前者のファンを構成する白人労働者が置き去りにされ、トランプを支持するようになったのだ。
アメリカの「分断」は解消されていない。それは華やかなカルチャーに彩られる世界と、音楽すら持つことを許されなくなった世界の対立であり、次期大統領はこの2つの世界の融和を求められるのだ。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
2021年2月号
【特集:「トランプ後」のアメリカ】
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

大和田 俊之(おおわだ としゆき)
慶應義塾大学法学部教授