【特集:戦争を語り継ぐ】
座談会:戦後80年を経て何を、どう伝えていくか
2025/08/06
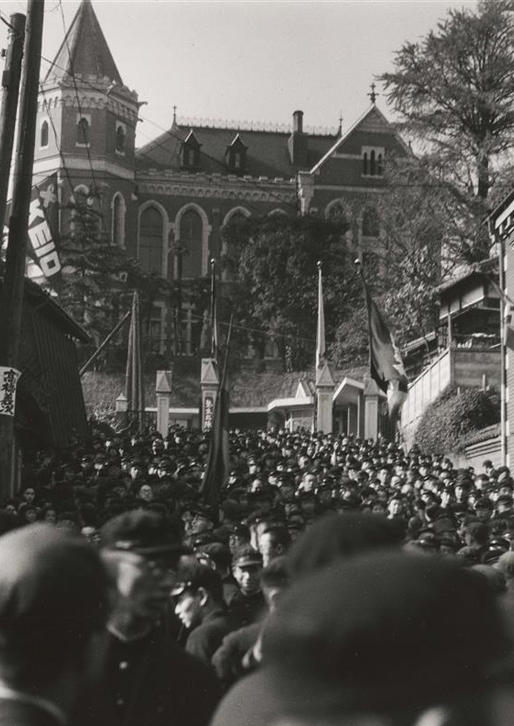
-

-

大川 史織(おおかわ しおり)
映画監督
塾員(2011政)。大学卒業後マーシャル諸島に移住。同地で戦死(餓死)した父を持つ息子の慰霊の旅に同行したドキュメンタリー映画『タリナイ』(2018年)を監督。編著書に『マーシャル、父の戦場』等。
-

奥村 湧太(おくむら ゆうた)
共同通信仙台支社編集部記者
塾員(2021法)。大学卒業後、共同通信社入社。大分支局を経て現在仙台支社編集部記者。2024年、太平洋戦争関連の旧軍施設を主とした戦争遺跡の現存状況を調査。
-

清水 亮(しみず りょう)
慶應義塾大学環境情報学部専任講師
2014年東京大学文学部卒業。20年同大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(社会学)。2024年より現職。著書に『「予科練」戦友会の社会学』『「軍都」を生きる』『戦争のかけらを集めて』等。
-

安藤 広道(司会)(あんどう ひろみち)
慶應義塾大学文学部民族考古学専攻教授
塾員(1987文、89文修)。2014年より現職。専門は日本考古学、博物館学。慶應義塾大学日吉キャンパス一帯の戦争遺跡の研究、『鹿屋・戦争アーカイブマップ』等の構築を行う。
「戦争の語り」の世界
安藤 今年、戦後80年という節目を迎えました。慶應義塾は大きな戦争被害を受けた大学であり、また、日吉に連合艦隊司令部地下壕などの戦争遺跡も抱えているわけですが、直接の戦争体験者がほとんどいなくなったという現状を踏まえ、残された体験談やモノなどから、今後、戦争をどう語り継いでいくかを考えていく機会にしたく、皆様にお集まりいただきました。今回は特に若い世代に多くご参加いただきました。
特集タイトルの「戦争を語り継ぐ」という言葉について、この座談会では、かなり広い意味で用いたいと思います。つまり、戦争を体験した方々の記憶や手記などの記録をそのまま継承していくという意味に限定しない、ということです。
例えばこれまでの学術的な研究成果や戦後世代の市民の活動などを通して生成されてきた、様々なアジア・太平洋戦争に関わる言説を、まず「語り」として受け止めようということです。
皆様はそうした語りを受け止めて、その時点でそれぞれの立場から、自らの語りを発信していると思います。そういう語りを受け止めて語りを発信し続けるという実践も、「戦争を語り継ぐ」という言葉に含めたいと思っています。戦争を語りつないでいくと言えばいいでしょうか。
まずは皆様から自己紹介を含めて、「戦争を語り継ぐ」取り組みを始めたきっかけ、あるいはどんなことを語ってきたのかについて、お話しいただきたいのですが、私はこの中では年配者になりますので、最初に私から自分自身の取り組みを紹介したいと思います。
私の専門は考古学と博物館学で、21世紀の初めまではずっと、弥生時代の研究をしていました。それがどうしてアジア・太平洋戦争に関わることになったのかというと、2008年、義塾の創立150年事業で建設された、日吉キャンパスの蝮谷体育館の工事において、帝国海軍の地下壕の出入り口が発見されたのです。それを私が調査したのがきっかけです。
そこで初めてアジア・太平洋戦争の語りの世界に触れることになったのですが、弥生時代の研究は、「学術の語り」が圧倒的に強いのです。つまり、研究者が語る歴史が一般の人たちにとってもそのまま歴史になっていく。これに対して「戦争の語り」の世界は、学術以外の人たちの存在感が非常に大きい。私はそのことに気付き、ショックを受け、自分の語りのあり方を大いに反省することになりました。
そこからは日吉の地下壕を中心に、戦争遺跡において考古学的に語り得ることは何だろうと考えながら、一方でそこに様々な立場の方々の多様な語りをつなぎ、対話の場をつくっていく、そうした取り組みを進めています。
最初は日吉だけだったのですが、日吉の連合艦隊司令部が指揮していた作戦は当然広い範囲に及びますので、そこから航空特攻作戦の中心だった鹿児島県鹿屋市とか、特攻部隊が出撃していった先である沖縄とか、最近は大戦末期に作られた大規模な海軍基地、島根県出雲市の大社基地なども結びつけて、語りをつなぐ実践をしています。
また、こうした実践をしていくと、戦争遺跡の保存の問題にどうしても向き合わなくてはいけなくなるので、併せて戦争遺跡の保存や活用の問題点などについて研究しています。
高校生の時の署名活動
安藤 では、次に今日はオンラインでご参加の大川さん、お願いします。
大川 私は卒業後、マーシャル諸島に移住し、現地で3年間働きました。帰国後、その島で餓死した日本兵をめぐるドキュメンタリー映画『タリナイ』をつくり、映画の核となる日本兵の日記をめぐる歴史実践の本を編みました(『マーシャル、父の戦場』)。
私自身が戦争を意識したきっかけは、祖父の存在かもしれません。祖父は17歳の時に敗戦を迎えました。昨日まで学校で教えていたことは間違いだったと先生が謝り、価値観がひっくり返るという経験を通して「学校や国が言っていることが正しいとは限らないのだ」と、身に沁みて感じたそうです。私が幼稚園生ぐらいの頃、会えばよくその頃の話をしてくれました。
私が17歳の時、戦後60年でした。その当時から、「戦争の体験者がいなくなるぞ、どうする」とメディアなどでも議論されていました。戦争体験がない世代として、どうしたら戦争に加担せず、巻き込まれもせずに生きていけるのかを考えていた時、長崎では日頃、高校生が核兵器廃絶を求めて署名活動をしていることを知りました。
一方、「原爆を落としてよかった」という教育を受けて育つアメリカの高校生もいます。将来、彼らと出会った時、どんな対話ができるのだろうかと想像しながら、私は長崎の高校生から署名用紙をもらい、東京でも仲間を募り街頭で署名を集めました。道ゆく人と署名を介した一瞬の出会い――通勤や通学路など、日常の景色にふと現れる「核兵器のない世界を」という声が戦後60年の日本でどのように響くのか、関心を持っていました。反応はさまざまでしたが、被爆地である長崎と東京の温度差も大きく感じました。
私にとって「戦争を考える」ということは、街頭ですれ違った人が署名をする間にささやく言葉や、無言でも思いを託されたと確かに感じる眼差し、署名はできないと立ち去る人の後ろ姿を見つめた記憶を思い出すこととつながっています。その後、映画という表現と対話のツールにたどり着きますが、「戦争を語り継ぐ」実践の原点は、街頭での署名活動にあると思います。
様々な原体験から
奥村 私は5年目の記者で経験も浅いですが、江東区の生まれで、東京大空襲の被害があった隅田川近くの小学校に通っていました。学校では地元の商店のおじいさんが戦争の時の話をしてくれる機会があったのですね。焼夷弾の投下で夜なのにあたり一面が真っ白になったとか、川に飛び込んだ人の死体が浮かんでいて、それを土手を掘って流し込んで埋めたという話を聞きました。通学路には空襲慰霊碑があったのですが、何気なく通っていた場所が戦争の爪痕を残し、想像もつかないようなつらい現場だったと知ったことは衝撃的な原体験でした。
3つ下に弟がいるのですが、弟の時は、その話を聞く機会がなくなってしまったようで、ちょっと年齢が下っただけなのに戦争が語られなくなっていることに、子どもながらに危機感を覚えました。この経験があったので、何かしらの形で戦争の語りに関わりたいと思っていました。
記者として、最初に大分県に赴任しました。特攻基地があった宇佐市の海軍航空隊や、津久見市保戸島の小学校で児童127人が亡くなった空襲の話を取材しました。
今の赴任地、宮城県では女川町の空襲や、蔵王の山中にB29が墜落して34名の搭乗員が亡くなり、地元でその慰霊を続けているという話を取材しています。
また、昨年夏には、安藤先生にご協力いただきながら、全国の戦争遺跡の残存状況を調査しました。
清水 戦争というものは人の「生と死」が凝縮して現れてくる現象です。だからおそらくフィクションも含めて様々な物語になるのですが、体験や歴史がどのように語り継がれるのかに関心を持ってきました。鋭い価値観の対立を背景に、戦争展示には論争がつきものですが、12年前、私は社会学の卒論を書くために、茨城県の霞ヶ浦の畔にできたばかりの少年航空兵のミュージアム「予科練平和記念館」に調査に行ってみました。
そこで少年兵だったおじいさんと出会い、1年ほど通ってお話を伺い、語り部の卒論を書いたのが、原体験かなと思います。
そのおじいさんは終戦時17歳で、飛行機に乗って実戦に出てはいません。自分が直に体験した訓練等を語る点では半分体験者ですが、特攻隊員について遺書をもとに語る時には非体験者の立場でもあります。体験者と非体験者の境界は、実は曖昧なのかもしれないと考えさせられました。
大学院では、その地域に生きた多様な立場の人々の戦争や基地の経験を調査研究し、その後は、よそ者の私が地域の方々へ向けて歴史をいかに伝えるかということに関心を持って、本を書き続けています。
湘南藤沢キャンパス着任後には、風光明媚なイメージの湘南海岸や藤沢市にも戦争や基地の歴史が埋もれていると知って驚き、調査を進めています。
平山 私も幼い頃に祖父母の戦争体験の話を聴きましたが、本格的に戦争の歴史研究に関与するようになったのは、3月に他界された経済学部の白井厚先生のゼミナールで、「太平洋戦争と慶應義塾」という共同研究に入れていただいたことがきっかけです。そこで戦争体験世代の塾員にアンケートを出し、それを集計したり、インタビューをしたり、いろいろな資料の提供を受けたりして鍛えていただきました。
その後は大学院に進んで、慶應の経済学部と中国・吉林省社会科学院による満鉄史の共同研究プロジェクトに入れていただき、満鉄史研究で学位を取っています。満州にもいろいろな語りがあります。
もう1つ、福澤研究センターで都倉先生が「慶應義塾と戦争プロジェクト」を立ち上げられた時にお声がけをいただき、シンポジウムやデータベースの作成などでささやかなお手伝いをさせていただいています。
2025年8月号
【特集:戦争を語り継ぐ】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

平山 勉(ひらやま つとむ)
湘南工科大学総合文化教育センター教授
塾員(1995経、98経修、2003経博)。博士(経済学)。大学学部時代、白井厚ゼミナールにて「共同研究 太平洋戦争と慶應義塾」に参加。2018年より現職。著書に『満鉄経営史』等。