【特集:日本の“食”の未来】
座談会:豊かでサステイナブルな食を届けるために
2022/02/04

-

-

金丸 美樹(かねまる みき)
株式会社SEE THE SUN代表取締役CEO
塾員(1998環)。大学卒業後、森永製菓入社。2017年森永製菓のコーポレートベンチャーとして株式会社SEE THE SUNを設立。食にまつわる社会課題を解決する場をデザインする。
-

小川 美香子(おがわ みかこ)
東京海洋大学学術研究院食品生産科学部門准教授
塾員(2003経管研修、07政・メ博)。博士(政策・メディア)。1993年早稲田大学卒業。東洋情報システム等を経て、07年東京海洋大学着任、17年より現職。専門は食品トレーサビリティー、食品流通安全管理等。
-

川越 一磨(かわごえ かずま)
株式会社コークッキング代表取締役CEO
塾員(2014総)。2015年、富士吉田市で株式会社コークッキングを創業。2017年、日本初のフードロスに特化したシェアリングサービス「TABETE」を事業化。一般社団法人日本スローフード協会理事。
-
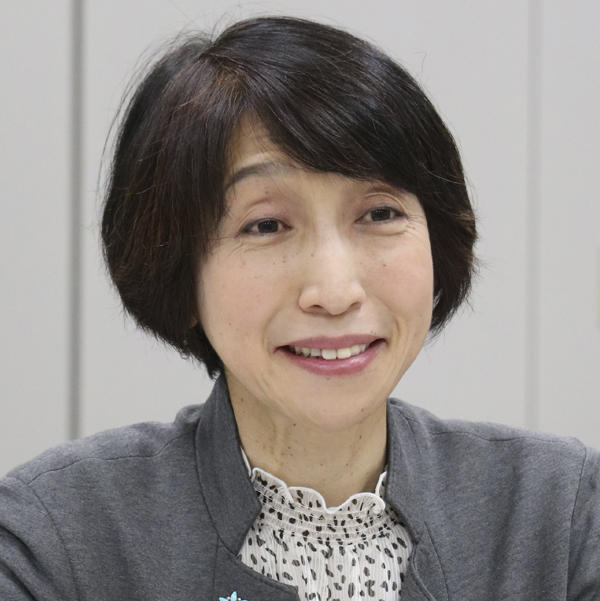
秋山 美紀(司会)(あきやま みき)
慶應義塾大学環境情報学部教授
塾員(1991政、2005政・メ博)。仙台放送報道局勤務等を経て、2012年環境情報学部准教授。17年より現職。博士(医学)、博士(政策・メディア)。専門はヘルスコミュニケーション。
「食」の未来を阻むもの
秋山 本日のテーマは「日本の食の未来」です。今日お集まりの皆さんは、それぞれが豊かな食、おいしい食、安全な食を届けること、さらに食を通して社会課題を解決しようと取り組まれています。「食」というのは、生命をつなぐという栄養面だけではなく、その国や地域、あるいは各家庭で育まれてきたもので、その人らしい幸せや生き方を支えるものと捉えています。
SDGsの多くの項目にも、食は直接的、間接的に深く関わっています。環境や資源の問題、それから社会格差や排除の問題、多様性と包摂の実現に向けた課題なども、食から見えてくるかと思います。
まず、ひかり味噌󠄀の林さんから、関心領域や問題意識をお話しいただけますか。
林 昨今、食を通してサステイナブルとかエシカルとよく言われますが、日本の場合、一番の逆風になっているの は私は経済力だと思っているのです。先進国の中でほぼ唯一、過去30年間可処分所得が増えていない。今、ポストコロナ、ウィズコロナと言われるようになり、日本だけが立ち遅れているという報道が増えています。
サステイナブルだ、エシカルだという消費は、やはりお金がかかると思うのです。さらにヘルスやウェルネスといった健康面のことも加え、民間企業の経営者という立場から見ると、経済成長の鈍化が一番のハンディキャップに見えるのです。
例えば、当社は現在、輸出に力を入れていますが、コロナ前、海外出張で現地のレストラン、スーパー等の現場に行くと、お金がかかってもいいから、即席味噌汁のプラスチックの袋はやめてすべて紙にしてくれ、われわれが単価を上げてその分を儲けるからという声を聞きます。日本のスーパーではこれはあり得ません。われわれが環境対策として紙にしたいと言っても、1円の値上げであっても受け入れていただくことは容易でない。この原因は何だろうと考えると、結局、経済力なのです。
ヨーロッパやアメリカの流通であれば、大抵の場合、値上げ分を価格転嫁し、それを末端の消費者が受けている。それが日本ではできていない。これが日本のマーケットの一番苦しいところです。それは企業努力だけでも解決できないもので、行政も含めてどうするのかという対応が必要ですが、何も実施されていない。
辛口の表現をすると、日本は税金を使って米の輸出と牛肉の輸出は一生懸命やる。だけど、エシカルや環境対応に対しては、「いい方向ですね」とは言っても、それを全国レベルで実際に施策として行うことはないですね。もっと足下にある国内の地元の消費に対して考えていかなければいけないのではないか。行政に全部任せるべきとは言いませんし、企業努力ももちろん大事ですが、ちょっとバランスを欠いているなと思います。
もう1つ例をあげると、今は日本のスーパーでも買い物袋が有料になりましたが、どこも2円、3円です。ヨーロッパのスーパーでは大体日本円で10円、20円します。そのかわり何回も使える品質のものです。日本は1回しか使えないような買い物袋を渡してどうするのかと思うのです。
そういうところが中途半端というか、私の解釈ではすべて業界ごとの横並び意識なのです。だから買い物袋1つでも行政から言われたから有料にした。だけど、5円、10円チャージする自信がないからどこに行っても2円、3円でとなる。それは本当の問題解決になっていないわけですよね。
秋山 確かにサステイナブルとかエシカルという言葉は、流行っていますが、現実にそのためにどのぐらい皆がお金を払う価値があると思っているか、疑問なところはありますね。
林 サステイナブルやエシカルという方向性は見えてきても、まだまだ地に足が着いていない気がします。ただ、日本はもともと食に関していい環境だったことは事実です。日本の食生活は、欧米の動物性の油脂や肉偏重に比べたら、極めて健康的ですから。
秋山 核心をつく問題提起をいただきました。金丸さんはいかがですか。
金丸 今の話はとてもよくわかります。たぶん戦後の高度成長期、まだ日本に豊富に物がなかった頃、皆がおいしいものを食べられるように各企業・流通が努力をした。その時はマスプロダクト、マスプロモーションが上手く回っていたので、それが価値観として色濃く残っているのだと思います。
現在、価値観も多様化し、皆、自分らしく生きたいと思い、同時に地球環境のことも考えなければいけなくなっている時代に昔のモデルが成功体験として残ってしまっている。お客さんのほうも安くていいものが当たり前のように手に入り続けるという意識になってしまっているのだと思います。
流通さんはお客さんのことを思い、安くすると売れると考える。でもそれは短期的なことだと思うのです。安くするために、原料メーカーも農家さんも利益を削らなければいけない。どこかにしわ寄せが来るはずです。
飲食業の方も、原料メーカーも農家さんも、おいしい笑顔のために皆さん一生懸命ですが、その努力がコストに反映されずに、末端になるとコスパ重視だけになってしまうのが、すごくもったいないと思っています。
エシカルと言っても、洋服と食べ物で違うのは、食べ物は本能的なもので、しかも毎日のことなので、やはりおいしく安いものが食べたいとなるのはしょうがないとは思うのです。ですので、お客さんにもメリットがある形で、その食物にストーリーがあって、10円、20円高くても豊かな気持ちになれると納得できるような相互理解が進めばいいなと感じています。
今はお互いを理解せずに価格のみで会話しているようなところもあるのではないでしょうか。もっとお互いを知ることにメリットがあるという形になれば、お客さんも自分ごと化してくださるのではと思います。
秋山 金丸さんは大手食品メーカーから企業内のベンチャーとして今の会社を立ち上げられたわけですが、そのような問題意識が、起業されたきっかけにあったのですか。
金丸 サステイナブルとダイバーシティをかけ合わせて食で解決しようと思い、プラントベース(植物由来)のフードなどに注目し、それを加工して売ってわかったことは、食で社会課題の解決をすることの難しさです。お説教では絶対に駄目で、お客様にわくわく感がないと手に取ってくださらないことは痛感しました。いくらきれいごとを言っても、それを日常的な行動につなげるには設計が必要です。
フードロスへの関心
秋山 川越さんはどのような問題意識から起業されたのでしょうか。
川越 もともと飲食畑にいた期間が長くて、SFC在学中も和食の料理店でアルバイトとして裏方に入り、大量に食べ残しをごみ箱に突っ込み続ける毎日を送り、飲食店の裏側の事情に気づきました。卒業後は銀座ライオンに就職し、店舗運営やホール業務をやる中でもフードロスの観点は持ち続けていました。
また、スローフードの運動にもかかわっていました。近年、日本のスローフード運動は美食家の集まりのような感じになってしまっていたのを若返りをして、草の根的な運動に回帰していこうと、協会の理事もやりながら、フードロスなどの啓蒙啓発活動などをやってきました。
青山のファーマーズマーケットで、毎月1回フードロスの削減ということで農家さんから売れない野菜を全部買い取り、600人分の災害用煮炊き鍋のようなものでスープにしていました。そうすれば捨てられてしまうものも普通に食べられます、それを寄付ベースで啓蒙啓発活動としてやってきました。
そのとき「コークッキング」という会社はもう立ち上げていたのですが、やはり啓蒙啓発活動だけでは難しいなと思いました。それだけでは世の中を変えていくスピードはとても遅いと思ったのです。
もっとシステムとしてインフラを整え、2次流通とまではいかなくとも、1.5次流通のような道をつくっていかなければいけない、と思って調べると、ヨーロッパでは2015年頃から、今の「TABETE」のような、フードロスで出た食材を、別の形の流通で販売するサービスがあったのですね。当時、アジアでこれをやっている人は誰もいなかったので見切り発車的に始めたのです。
僕は、今はフードロス専門の人みたいになっているのですが、どちらかというと、スローフードのほうから、現在はフードロスにフォーカスしているという感覚です。食の持続可能性やダイバーシティが本来目指すべきところと思っていて、最適化されすぎたサプライチェーン全体を今の時代に合った、よりサステイナブルな形にしていく必要があると思い、チャレンジしています。
小川 皆さんのお話はとても印象的です。私自身はトレーサビリティーなど食の情報が価値を生むと思い、研究のフィールドを食にしてきました。そのうちHACCP(ハサップ=食の衛生管理手法)など食品安全をテーマにすることが多くなってきたのですが、私もエシカルな消費や地産地消を進めるには想像力が必要だと感じています。
例えばドイツのある地方では、地元のワインを皆が飲むのですが、そのワインは専門家からするとそれほどおいしいわけではないのだそうです。しかし、これはうちの村のワインだからと箱買いをして、年間を通して皆飲むそうです。また、スイスのスーパーでは、他の地域からの安い卵があっても、私たちが買わないとスイスの乳業、畜産業がなくなってしまうからと地元の卵を買っている。
このように作り手や未来を想像できるようになれば、その地域の中での食にお金を払うことに満足できるようになるのだと思います。東京ではそれがなかなか難しいところもありますが、今、食による教育の分野にも携わっているので、想像力を持てる人をたくさん育てられたらと思っています。
すごくいい日本語だと思うのが「足るを知る」という言葉です。人間の欲望は限りないのですが、「これでいいんだ」と思えればずいぶん変わってくる。他者との比較でなく、自分らしさを基準に、想像力も持ちながら食と向き合える人たちを育てたいと思っています。
金丸 私も今、「OUR TeRaSu」というオンライン上の場所をつくっているのですけれど、そこのテーマが、やはり想像力と好奇心なのです。与えられた情報だけで満足してしまいがちなので、食に対する好奇心を持ってもらって自分を広げる体験をするうちに、想像力が豊かになるということを伝えたいと思っています。
今、SFCの学生さんと共同研究をしているのですが、そのテーマが生活者と作り手の新しい関係を模索するというものです。作る側が一方的に提供するのではなくて、食べる側もパートナーだと思って、相互理解をして未来をつくろうとしています。
しかし、人口のボリュームゾーンとしては、まだまだ40代、50代が多い。そうするとやはり安いほうがいいとなりがちで、若い人に芽生えている価値観もミックスして市場をつくるのはまだ難しいとも思います。
情報開示の重要性
秋山 購買層の世代差というのはあるのでしょうね。例えば今の大学生は当たり前のようにSDGsを学んでいたり、エシカルという言葉を皆知っている。そういう層がいずれ主要な消費者になっていくと、消費の動向は変わるかなとも思いますが、今はちょうど過渡期ですよね。
林 世代間の違いというのは非常に悩ましいですね。味噌はいったい誰が買ってくれるかという話になると、明けても暮れても結論は出ないのです。例えば若年層は和食を食べないけれど、年を取ってくると和食に回帰する、と業界では言われますが、私はそれはないと思います。都内のマックでは、おじいさん、おばあさんが一生懸命、ハンバーガーを食べていますから(笑)。
皆さんのお話を聞いて感じたのは、例えばトレーサビリティーの発端は受け身的にやらざるを得なかったのです。BSEの問題が出た、遺伝子組み換えの問題が出た、というのは、つまりサプライサイドの不祥事で消費者が不信感を持ったから、慌ててやりましたということで、否応なしに対応を迫られた。
GMO(遺伝子組み換え作物)の話はまさにそうだと思います。そもそも「ラウンドアップレディ」(除草剤耐性作物)とか動向を作ったのは、世界的に悪名高い巨大ケミカルカンパニーです。彼らが十分な説明責任を果たさなかったから、何をやっても駄目という印象を消費者団体は持ち、だからGMOの作物は全部駄目になってしまった。
私も大豆の買い付けでよく海外を回っていたのですが、NON-GMOの種子と農薬はセットで売られています。しかも一世代だけで毎年買わなければいけない。農薬を散布した後の大豆畑は地平線が真っ白です。いくら科学的に健康に問題はないと言われても、その現場を見てしまうと、感情も含めて食べたくないですよね。
ですから、当初受け身的なところからいろいろ出てきて、今は過渡期ですが、この先は能動的になって消費者がまず今後の方向性、エシカルとか、サステイナブル、もったいないという気持ちを受容するようになり、次に今度は能動的にアクションを起こすようになるのだと思うのです。
今は受容しはじめたところだと思います。今度はサプライサイドも能動的にアクションを起こさなければいけないし、消費者も、私は選ぶ権利がありますと自分でアクションをする。そのように、だんだん目覚めていくと思うのです。
秋山 GMOの話も、その裏にある本質的なところは、知らない方が多いと思います。それを知らせていくのは非常に大事なことですね。
林 情報開示(ディスクロージャー)は本当に大事です。ここ30年ぐらいでどの国でも本当に変わってきたと思います。消費者の知る権利に疎い企業はこれから難しいでしょうね。
私がこの業界に入った30年ぐらい前は、ある食品業界は国産原料を70%使っていたら国産表示ができたとか、当時の日本はそのぐらいでした。今だったらそんなことはあり得ない。企業経営者も、消費者も、中間流通も着実に意識改革はできていますから、これはいい方向だと思うのです。
2022年2月号
【特集:日本の“食”の未来】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

林 善博(はやし よしひろ)
ひかり味噌󠄀株式会社代表取締役社長
塾員(1982政)。大学卒業後、信州精機(現セイコーエプソン)入社。1994年家業である「ひかり味噌󠄀」に転職し、2000年より現職。ひかり味噌󠄀は、無添加、有機の商品を中心に販売を伸ばす。