【特集:日本の“食”の未来】
光田達矢:食肉の歴史から見た21世紀の肉食
2022/02/04

日本は肉食社会か?
学研教育総合研究所が1989年以降定期的に発行している『小学生白書』の中に、子どもの食生活に関するデータが収められている。2019年のアンケートを取り出し、好きな食べ物に対する平成生まれの子どもの回答を紐解いてみると、人気料理の多くに「肉類」が登場していることがわかる(図1)。1位に君臨する「おすし」(40.8%) を除くと、2位の「フライドチキン・からあげ」(25.2%)、5位の「カレーライス」(21.9%)、6位の「焼き肉」(21.8%)、7位の「ハンバーグ」(17.8%)、10位の「ステーキ」(11.1%)は、牛肉・豚肉・鶏肉を食材として使用している洋食ばかりである。また、新型コロナウイルスによって繰り返し発出される緊急事態宣言に振り回され、外食産業の売り上げは大きく落ち込んでいるが、居酒屋を筆頭に廃業に追い込まれる飲食店が多い中、焼き肉店は健闘している。無煙ロースターによる換気が安心感を生んでいるため、客足は意外と遠のいていないという。その結果、店舗数を増やす攻めの姿勢を見せる全国チェーンが少なくない。このようなことから、日本の肉食人気は高いという印象に陥りやすい。
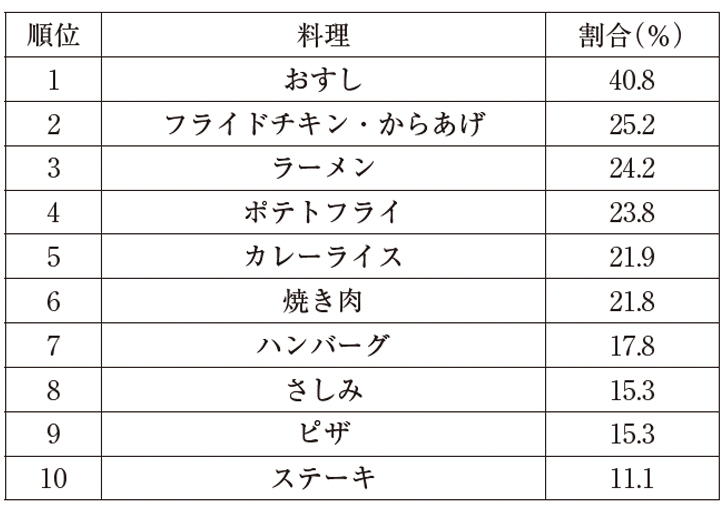
しかし、世界と比較してみると、日本の「肉食度」は決して高いとはいえない。環境への悪影響が大きいことでやり玉に挙がりやすい牛肉の消費量に絞って見てみよう。『OECD/FAO食肉消費量統計』(図2)によれば、世界1位のアルゼンチンは1人当たり年間36kgの牛肉を口にしている。次にアメリカが26kg、ブラジルとイスラエルが24kg、チリとカザフスタンが21kg、オーストラリアが18kgと続き、地域を越えて牛肉需要が旺盛であることがうかがえる。
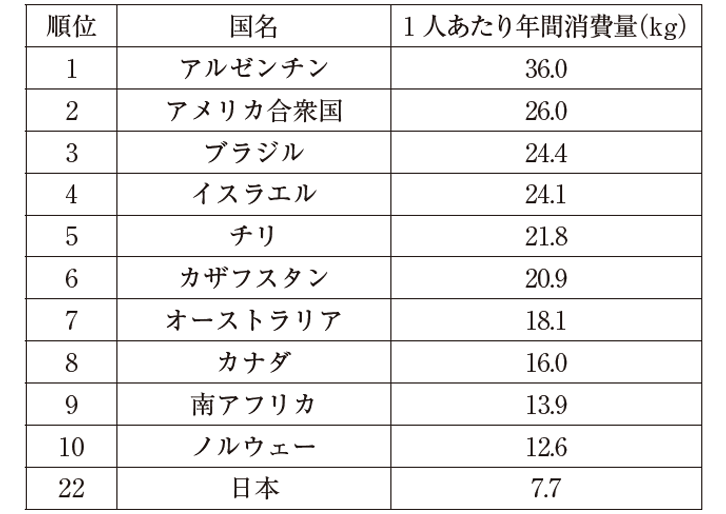
一方、ランキングから日本の順位を探すのは困難だ。OECD加盟国平均である14kgの半分程度の約8kgが日本人の胃袋に毎年収まっている。この数字は、韓国の12kg、ロシアとベトナムの10kgより少なく、エジプトと肩を並べるほどである。小学生アンケートから洋食人気が堅調であることを示したが、全世界平均の6kgに近い牛肉消費量しかないのである。
このように食べる量が少ないのは、諸外国と比べ日本の牛肉価格が高いことに起因する。アメリカ、イギリス、イタリアの消費者より数倍のお金を払わなくてはならず、なかなか手を出せない。カレーを作る際、値の張る牛肉を避け、求めやすい豚肉や鶏肉を選択する家庭は少なくないのではないか。今後、世界的に「脱肉食化」が進むにしても、日本は少なくとも牛肉に関しては高い消費ベースからのスタートにはならないだろう。
近代化と肉食化
日本が肉食化の道を歩みだしたのは幕末である。それまでは牛肉をはじめ獣肉は忌避されがちであった。仏教思想に基づく食肉禁止令がタブーの形成に寄与したのだが、役畜として重要な労働力を保護し、農業経済の破綻を回避する必要性から食用に回すわけにはいけなかったことも関係している。ただ、食肉が全く流通していなかったというのではない。馬、鹿、猪、鳥など野生動物の狩りを通してもたらされる肉をこっそり食べる習慣は近世からあった。口にする後ろめたさから、それぞれ桜肉、紅葉、山鯨、柏といった隠語を用いて食肉は売り出され、浮世絵『名所江戸百景 びくにはし雪中』 (1858)(図3)には「山くじら」の看板が読み取れるように、都市部を中心にそれなりの需要はあったことがわかっている。

ところが、明治維新以降、肉食に対する忌避感は次第に薄まっていった。江戸幕府の使節団の一員として欧米を1860年代に訪れた福澤諭吉(1835-1901)は、片山淳之助の名で『西洋衣食住』を1867年に著し、文明国における生活情報を広めようとした。その後、東京・築地に設立された牛肉販売会社の依頼を受け、『肉食之説』を1870年に発行する。「今我國民肉食を缺(かい)て不養生を爲し、其生力を落す者少なからず。即ち一國の損亡なり」と警鐘を鳴らし、日本人の食生活を改革する手段として肉を食べるよう強く奨励した。具体的に、植物由来の食材を基本とする日本料理は滋養が足りないことから、動物由来の食材を基本とする洋食を普及すべく、肉食化に懐疑的な社会を説得しようと試みた。たとえば、クジラ肉を口にする肉食保守派の矛盾を突き、汚染された海洋で得体の知れないものをのみ込んできたクジラとは対照的に、人間の完全な管理下において飼育できる家畜動物がもたらす食肉は、健康被害を最小限に抑えることのできる極めて衛生的な食べ物であることを訴えた。福澤のような知識人が日本の肉食化に大きく貢献したのである。
国家も肉食化を進めようとした。大久保利通(1830-1878)が率いる内務省は、貧弱な在来牛の改良に乗り出すと、欧米農業先進国から種牛を買い付け、和種との交配を繰り返すことで本邦牛の増加と大型化を実現しようとした。1860年代を皮切りに英国からショートホーンとデボン種を取り寄せ、全国の農家に貸付けようとした。これら英国種が日本の地理的条件に合致しないと判明するや否や、同じく山岳地帯であるスコットランドやスイスからエアシャー、シンメンタール、ブラウンスイス種の輸入に切り替え、食肉生産の国内環境を整備しようとした。
また、富国強兵を掲げた明治政府は、西洋先進国軍の兵糧に食肉が不可欠であったことから、牛肉を採用する動きを見せた。海軍はいち早くビーフステーキ、ローストビーフに加え、携行食として牛肉の缶詰を兵食として加えた。最初は懐疑的であった陸軍も1877年に牛肉を兵糧として受け入れることになり、それ以降、兵士の間で牛肉を食べる習慣が定着していった。
これらの働きもあって、1880年代になると、都市部を中心に牛肉を食べることに対する忌避感は消え、現在のすき焼きの元祖となる牛鍋ブームが巻き起こる。木村荘平(1841-1906)は1880年に牛鍋チェーンを起業し、三田四国町(現在の港区芝2~5丁目)を皮切りに東京に少なくとも22店舗を開き、中流階級の間でとくに人気を博すと、牛肉はいつしか文明開化を象徴する食べ物になっていった。かくして、日本の肉食化の口火が切られたのである。
2022年2月号
【特集:日本の“食”の未来】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

光田 達矢(みつだ たつや)
慶應義塾大学経済学部准教授