【特集:歴史にみる感染症】
座談会:文学に現れる感染症
2020/11/05

-
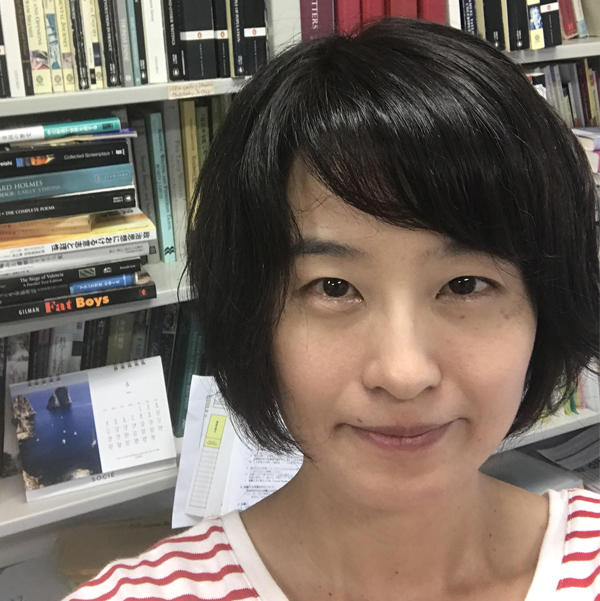
-

小倉 孝誠(おぐら こうせい)
慶應義塾大学文学部仏文学専攻教授
1978年京都大学文学部卒業。87年パリ・ソルボンヌ大学にて博士号取得。88年東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。東京都立大学助教授を経て2003年より現職。専門は19世紀フランス小説、フランス文化史。著書に『身体の文化史』『ゾラと近代フランス』等。
-

ピーター・バナード(Peter Bernard)
慶應義塾大学文学部英米文学専攻助教
アメリカ・マサチューセッツ州生まれ。ハーバード大学大学院博士課程修了(Ph.D.)。専門は日本近代文学、比較幻想文学論。2020年より現職。訳書にA Bird of a Different Feather: A Picture Book(泉鏡花著・中川学画)。
-

巽 孝之(司会)(たつみ たかゆき)
慶應義塾大学文学部英米文学専攻教授
1978年上智大学文学部英文学科卒業。87年コーネル大学大学院博士課程修了(Ph.D.)。98年より現職。専門はアメリカ文学、批評理論。日本アメリカ文学会長等を歴任。著書に『ニュー・アメリカニズム 増補決定版』『パラノイドの帝国』、Full Metal Apache 等。
『聖書』からアンドロメダ病原体まで
巽 本日は「文学に現れる感染症」をめぐる座談会を行うにあたり、まずは私が作成しました「感染症文学年表」を叩き台に、その大枠をスケッチしてみたいと思います。
時期的に最も古いのは言うまでもなく『聖書』。我が国では『源氏物語』ですが、最も新しいのはマイクル・クライトンの有名な『アンドロメダ病原体』の続編で、クライトン没後にダニエル・ウィルソンが書いた『変異(The Andromeda Evolution)』ということになります。
『源氏物語』には当時の「おこり」(マラリア)がよく出てくるんですね。『平家物語』の平清盛もマラリアで亡くなったと言われている。
一方、クライトン&ウィルソンになると、1969年の正編の方は宇宙から来た病原体が蔓延した結果、全面核戦争の可能性を醸し出すという怖い話ですが、続編は、逆に人類がアンドロメダ病原体を利用するという、たくましい発想になっています。
時代順に見ていくと、英文学ではまずは言うまでもなくチョーサーの『カンタベリー物語』。29人の巡礼者が一人一人、順にしゃべっていく語りの形式自体は、ボッカチオの『デカメロン』を踏襲したと言われていますが、それだけではなくて、ペスト(黒死病)が扱われていることでも通底している。
そして、ペストそのものがテーマになるのが、17世紀後半のロンドンのペスト大流行を描いた、ダニエル・デフォーの『ペストの記憶』。『ペストの記憶』という邦題は、最近の武田将明さんの新訳で、以前の平井正穂訳は、ずばりカミュと同じ『ペスト』でした。
アメリカ文学だと、チャールズ・ブロックデン・ブラウンのゴシック・ロマンス、『アーサー・マーヴィン』が1793年のフィラデルフィアのイエローフィーバー(黄熱病)を扱った作品。これがたぶん小説の形ではアメリカ文学史上、初の感染症文学ではないでしょうか。
ポーは、新潮文庫の拙訳ではあえて「赤き死の仮面」(『黒猫・アッシャー家の崩壊』所収)としていますが、他では「赤死病の仮面」の訳題が多い。赤死病(Red Death)というのは、黒死病(Black Death)、つまりペストのパロディとしてポーがつくり出した架空の伝染病ですね。その病気が蔓延しているのを避けてプロスペローという王様が自分の城を完全に密閉して仮面舞踏会を開くんですが、なぜか疫病の権化が忍び込んでしまうという話です。
結核文学は数多あって、スーザン・ソンタグも『隠喩としての病』で強調していますが、ロマン派と結核というのは非常に相性がよかった。『ラ・ボエーム』もその中に入るでしょう。トーマス・マンの『魔の山』もサナトリウムが舞台の結核文学。日本の『女工哀史』『風立ちぬ』もそうですね。
そしてメルヴィルの『白鯨』。この小説は捕鯨の話なので、感染症と関係ないと思われるかもしれませんが、何と捕鯨船が疫病に襲われるエピソードがさし挟まれています。
ジャック・ロンドン作品は、邦訳は『赤死病』なのでポーへのオマージュみたいですが、原題はThe Scarlet Plague。ただし訳すと同じ『赤死病』になってしまうのが面白い。ジャック・ロンドンはいわゆる生物兵器としての病を蔓延させる物語を他にも書いていて、一種のSFのはしりとも言える。そして1947年にカミュの『ペスト』が来る。
もう1つ、『聖書』以来、古今東西の文学が描いてきたのがハンセン病ですね。日本では松本清張の『砂の器』や遠藤周作の『わたしが・棄てた・女』『死海のほとり』がすぐに思い浮かぶでしょう。
そして米ソ冷戦の渦中、1962年のキューバ危機で核戦争勃発の恐怖が感じられるようになった不穏な空気の中で、小松左京が『復活の日』を書く。
文学の中で感染症の扱いは、どちらかというと一種の脇役という感じだったのが、20世紀になってくると、病を主役にした文学が増えてくる。ソンタグの言っている「隠喩としての病」のリアリティが増してくるんです。
そして1980年代には、エイズが登場する。エルヴェ・ギベール『僕の命を救ってくれなかった友へ』は当時不治の病であったエイズに罹患した著者の自伝的物語ですが、ミシェル・フーコーとも交友があった。フーコーもエイズで亡くなっていますが、ギベールもこれを書いた直後に亡くなっています。エイズについては演劇作品『エンジェルス・イン・アメリカ』や、映画『ボヘミアン・ラプソディ』も忘れられません。
1990年に2つ、これは傑作短編と言っていいSFが出てきます。1つがパット・マーフィの『ロマンティック・ラヴ撲滅記(The Eradication of Romantic Love)』。これはロマンティック・ラヴ自体が感染症であるのだからそれを撲滅しなくてはいけないというSFです。
もう1つがJ・G・バラードの『戦争熱(War Fever)』。戦争をしたがるのも、政治の問題ではなくて、実は感染症ではないか、ではそれを予防するにはどうするかという策略の顚末が語られます。たぶん伊藤計劃の長編小説『虐殺器官』の発想源でしょう。米ソ冷戦が終結を迎える時期にこういう2つの小説が書かれているというのは非常に象徴的ですね。
ラテンアメリカでは世紀転換期を舞台にしたガルシア=マルケスの『コレラの時代の愛』(1985)も見逃せません。
私からはとりあえずこんなところなので、小倉さんにバトンタッチいたしましょう。
19世紀フランスのコレラ流行
小倉 フランス文学について言うと、文学に描かれた特権的な病ということになると、やはり19世紀以降になるだろうと思います。
病の歴史を考えてみると、ペストはヨーロッパでは18世紀でほぼ終焉する。ですから、日本でもコロナ流行後、非常に読まれているカミュの『ペスト』は20世紀半ばのアルジェリアのオランが舞台なので、実はペストという病に対する恐怖という意味では現実性はほとんどない話なのです。
カミュの意図では、あの「ペスト」とは文字通り隠喩であり寓意であり、端的にナチズムのことだった。彼自身、ある手紙の中でそう明言しています。戦後すぐに発表された作品ですから、同時代に読んだフランスの読者は、これはペストの話ではなく、ペストに象徴されるいろいろな意味での悪、それを凝縮した形でのナチズムの寓意として読んだはずなのです。
ただ現代の日本の読者は、それを文字通り一種の感染症の文学として読んでいるのでしょうし、それはそれで正しい読み方です。カミュの描写が疫学的にどこまで正しいかはともかくとして、今回のコロナのように、すぐに撲滅できない感染症が1つの都市に蔓延してしまうという話です。オランという町が文字通り封鎖され、外部との接触を完全に断たれてしまう。そうした極限的な状況を物語の中につくり出すために、ペストという病は実に有効に機能している。
同時代には人間が対処できない謎の病、まさに中世のペストや現在のコロナもそうですが、それは非常に不安や恐怖をあおる原因になっているわけです。そのような状況と重ね合わされて、カミュの『ペスト』がよく読まれていることは、とてもよく分かります。
さて、フランス文学の中で特権的な感染症を古いほうから言うと、まずコレラです。フランス、特にパリを中心にして、19世紀に何度かコレラが流行しています。一番大きかったのが1832年のコレラ流行。この時、パリだけで2万人近くが死んだと言われる。当時のパリの人口が6、70万人ですからすごい割合です。
そうしたコレラを背景にして書かれた文学は2種類あります。1つは実際にその時にパリにいた作家による回想録です。1人はシャトーブリアン(『墓の彼方の回想』)、それから女性作家のジョルジュ・サンド。ジョルジュ・サンドには『わが生涯の歴史』という非常に長い自叙伝があります。2人とも1832年にパリにいました。
ではそのコレラが起こった時に何が生じたか。コレラ菌が見つかるのは19世紀末ですから、当時のコレラは謎の病で、もちろん対処のしようもありません。そうした謎の病を前にして住民たちはなすすべもなくバタバタ死んでいく。しかも死んだ後にろくに埋葬もされません。中世のペストと同じで、身内だろうが、友人だろうが、死んだ人の葬儀にほとんど誰も付き添うこともない。
これは、まさに今のコロナと似ているのですが、コレラは人々の接触を断ってしまうわけです。人々が出会うこと、触れることすら許されなくなってしまう。そうして街全体が隔離状態になり、接触が断たれて非常に孤独になる。シャトーブリアンもジョルジュ・サンドも、「コレラで死んだ人間は孤独だ。墓に付き添っていく人すらいない」と書いています。
そして、もう1人、大衆文学を代表するウージェーヌ・シューという作家が『さまよえるユダヤ人』という小説を書きました。これはユダヤ人一家をイエズス会が迫害するという、波瀾万丈の物語ですが、イエズス会がユダヤ人一家を迫害するときに、1832年のコレラを意図的に使う。言ってみれば、今で言う細菌兵器みたいな形です。
この小説の中ではイエズス会が非常に腹黒い連中の集団として書かれている。この時代、フランスでもイエズス会に対する偏見がかなり強かったのですが、イエズス会が陰でコソコソ、ユダヤ人を迫害するという物語の1つの装置として、この謎の病であるコレラを利用するという作品です。
2020年11月号
【特集:歴史にみる感染症】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

小川 公代(おがわ きみよ)
上智大学外国語学部英語学科教授
ケンブリッジ大学政治社会学部卒業、同大学院修了。大阪大学大学院文学研究科修了。グラスゴー大学文学部にてPh.D.(英文学)取得。専門はイギリスを中心とする近代小説、医学史。 編著書に『文学とアダプテーション――ヨーロッパの文化的変容』(共編著)等。