【特集:歴史にみる感染症】
日本史から「病」を考える授業
2020/11/05
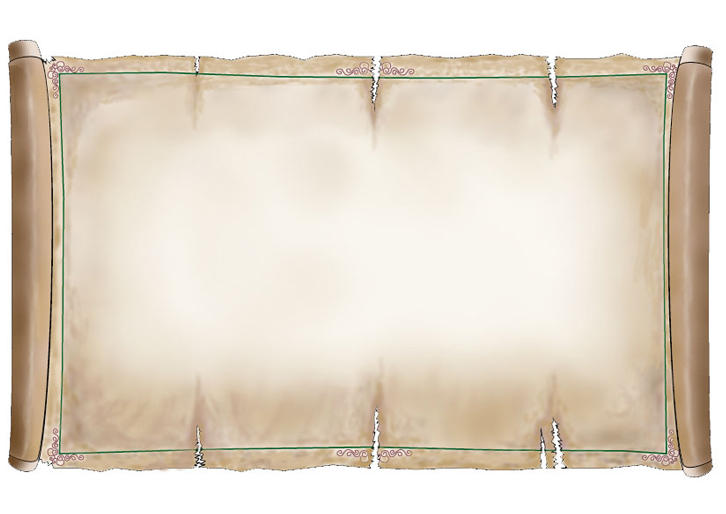
「病」と向き合う
4月、日吉キャンパスの閉鎖と共にいよいよ本校も臨時休校が決定した。メディアは日に日に増える新型コロナウイルス感染症の陽性反応者の数を続々と報じている。家から一歩も出なくとも、社会全体に「不安」という病が広まっていく様子は容易に感じ取ることができた。そんな中、歴史を教える教員の端くれとして考えたのは「かつて疫病が流行した時、過去の人々はどのように向き合ったのか」というものだった。奇しくも、「有効な薬がない」という点においては過去と現在が一致している状況である。狩猟・採集・漁労・栽培で自ら食料を得るしかない縄文人も、電話1本で何でもどこでも配達してもらえる現代人も、特効薬のない病を前にすれば、結局は等しく無力なのだ。だからこそ、我々は今まさに「病と向き合う術」を過去から学ぶ必要があるのかもしれない……と、いうのが今年度前期の私の授業テーマだ。本来であればここで紹介するような大層な代物ではないが、この度せっかくの機会を頂戴したため、以下に履修者が「授業中に睡眠学習へ移行しにくかった話」を中心に例を挙げさせていただく。
「病」の虫
平城宮跡などの古代遺跡で発掘調査をすると、籌木(ちゅうぎ)と呼ばれる木のヘラのようなものが発掘されることがある。要は古代のトイレットペーパーなのだが、これを顕微鏡で観察すると、古代人が寄生虫やその虫卵に起因する感染症に難儀していた様子がありありと伝わってくる。もちろん彼らがその病原を突き止めることは叶わなかっただろうが、実は「体内の虫が何かをする」こと自体はどうやら知っていたようである。
というのは、天台宗の開祖最澄の弟子・円仁の留学記『入唐求法巡礼行記(にっとうぐほうじゅんれいこうき)』に、庚申信仰に関する記述があるからである。庚申信仰とは、「庚申の日は体内に住む三尸(さんし)の虫が、寝ている間に体を抜け出して閻魔大王へ当人の罪を告げ口しに行く日である。そして閻魔大王はその罪に応じて寿命を減らす」というものだ。そのため、当日は夜通し起き続けることで三尸の虫が動けないようにする必要があるらしい。そしてこれが日本国内では平安貴族の酒宴の時間となり、時代が下るごとに武士の間にも広まっていった。半ば公認のような形で朝まで呑むことができるなどまるで夢のような話であるが、いずれにせよ「体内の虫が何かをする」ことを、過去の人々も知っていたのだろう。
「病」を有効活用する
一方で病の原因を「虫」ではなく「祟り」にみることもあった。日本の歴史上に現れる流行り病の中で、最も古く詳細な記録が残されている事例は奈良時代の天然痘の大流行であろう。当時の人口の2割とも3割ともされる犠牲者の中には、時の為政者であった藤原四子全員が含まれている。この時、平城京ではある噂がまことしやかに囁かれていた。曰く「これは長屋王の祟りである」と。彼は729年の長屋王の変に際し自刃しているが、そこには四子の陰謀が存在しているとされる。非業の死を遂げた長屋王が文字通りの「疫病神」と化し天然痘を流行らせ、怨敵である四子全員の命を奪った、というのはいかにもな話である。他にも桓武天皇の弟・早良(さわら)親王は、長岡京の造営をめぐる「藤原種継暗殺事件」の首謀者として、天皇家への刑罰として最も重い配流に処された。自らの無実を訴えるための10日間に及ぶ獄中での絶食とそれに起因する憤死は、彼が怨霊と化すにはこれまた十分すぎる理由であろう。その結果、平安京では疫病が流行し、自らの生母である高野新笠(たかののにいがさ)や桓武天皇の妃たちが病に倒れることとなった。このように「祟りと病」を結びつける事例は枚挙にいとまがない。
しかし、人々は「疫病神」にただ翻弄されるばかりではなかった。桓武天皇はすぐさま早良親王を含め、非業の死を遂げ怨霊と化した人々の霊を祀った。彼らを「怨霊(おんりょう)」から「御霊(おんりょう)」、すなわち神聖なる神として崇めなおすことで、その「負の力」を疫病から身を守る「正の力」へと転換しようとしたのである。これが京都神泉苑でおこなわれる儀礼「御霊会(ごりょうえ)」の始まりであった。また京都祇園祭で著名な八坂神社の祭神・牛頭天王(ごずてんのう)は祇園精舎の守り神である一方、病を司る神でもある。そして同じく八坂神社の祭神で、その牛頭天王と同一視される日本神話の英雄・須佐之男命(すさのおのみこと)もまた、蘇民将来伝説に代表されるように疫病神としての側面を持っている。この祇園祭の別称もまた「御霊会」なのである。
つまり、やはり人々にとって病や疫病神は、ただ恐れ忌避するだけの存在ではなかったのだ。むしろあえて病を肯定的に捉えることで、その大いなる力を生きる糧として有効活用したのである。この極めてしたたかな生き方は、今まさに我々が先例とすべきものなのかもしれない。
2020年11月号
【特集:歴史にみる感染症】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

島﨑 哲也(しまざき てつや)
慶應義塾高等学校教諭