【特集:歴史にみる感染症】
フロイトとスペイン風邪
2020/11/05
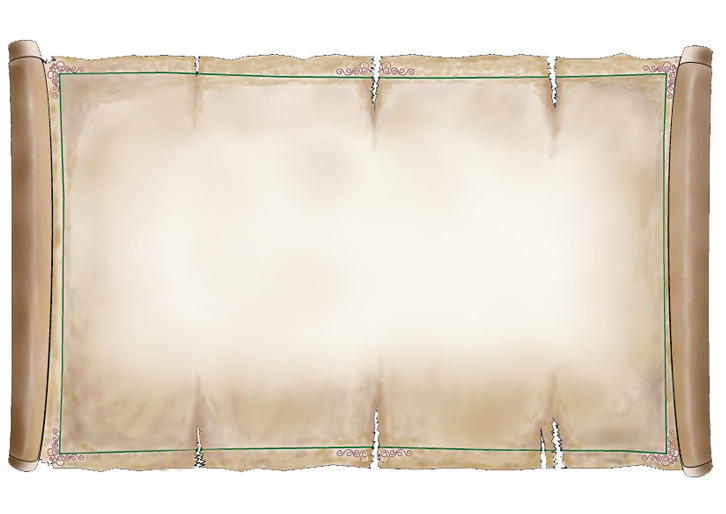
愛娘の死
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行について、約100年前のスペイン風邪の世界的な流行になぞらえて語られることが多い。スペイン風邪とは、1918年3月頃から米国やヨーロッパに端を発し、世界的に流行した新型インフルエンザの俗称である。当時、そのウイルスは同定されず、未知のウイルス感染症とされていたため、感染対策としては、患者の隔離、接触者の行動制限、個人衛生、消毒と集会の延期、マスクの着用などだったという。現在、新型コロナウイルス感染症に対して私たちがとっている対策とほとんど変わらない。異なるのは、スペイン風邪では死亡例の99%が65歳以下であり、15~35歳の若年者層に最も多くの死者を出したという点である。その原因は定かではないが、スペイン風邪の流行が第1次世界大戦のただ中に始まり、戦場でも多くの感染者を出したことにも由来するだろうことは、想像に難くない。
しかし、戦場とは無縁の場所で、精神分析理論(治療)の創始者であるフロイトの愛娘ゾフィーは、スペイン風邪によって、26歳の若さで亡くなった。それは、1920年1月25日のことであった。フロイトの側近中の側近であったアーネスト・ジョーンズが著したフロイトの評伝、『フロイトの生涯』によると、フロイトにとって、彼女の死は青天の霹靂であり、大きな心理的な打撃であった。彼は側近のアンティンゴンへの手紙に「何を言うべきかわからないほどに、(ゾフィーの死は)私を麻痺させている」と綴っていたという。
同じ年の夏、フロイトは「快感原則の彼岸」と題する論文を完成させた。この論文は、それまでの臨床経験に基づいた論文とは一線を画し、思弁的、哲学的であった。その中で彼は「死の欲動」について初めて言及し、論じた。
ジョーンズによると、フロイトはアンティンゴンに、「(この論文が)ゾフィーがこの上ない健康に恵まれていた頃、すでに半ば出来上がっていたという証人になってほしい」という奇妙な依頼をしたという。一方、アンティンゴンに対して「死の欲動」に言及したのは、1920年2月20日が初めてだったらしいともいわれている(ジェームズ・ストレイチー『フロイト全著作解説』)。また、フロイトがジョーンズに対して初めて「死の欲動」に言及したのは、ゾフィーの死の2週間後だったようである。ジョーンズは、「(ゾフィーが亡くなった2週間後の手紙の中で)彼が自分が『死の欲動』について以前から書き続けていることについて偶然言及しているという事実がなければ、彼の新しい思想が娘を失った落胆によって影響されたものであることを、内心で拒否しているしるしではないかという疑いがおこりうるところであった」と述べている。
彼らの証言通り、「死の欲動」理論がゾフィーの死以前に着想されていたとしても、彼女の死がその理論の構築にまったく影響を与えなかったとは、筆者には思えないところがある。なぜなら、筆者は、フロイトの「死の欲動」理論に、「理不尽な死」への抗議のようなものを感じるからである。
死の欲動(タナトス)
フロイトは、前述の論文で、自らの欲動論を根本から定式化し直した。すなわち、欲動を「死の欲動(自我欲動)」と、それに対立する「生の欲動(性的欲動)」の2つに大別した。
彼は、「死の欲動」の前提として「生物は無生物から派生した」と考え、「生物は内的な理由から死んで無機物に還るという仮定が許されるなら、われわれはただ、あらゆる生命の目標は死であるとしかいえない」と述べ、「高等動物では一定の、平均した寿命があるという事実は、もちろん内的な原因による死を証明するものである」とした。
このような「死の欲動」を、「自らに向かう攻撃性」の存在を肯定するものと考える研究者もいるが、一概にそうとはいえない。なぜなら、フロイトは「死の欲動」、別名「自我欲動」には、「自己保存本能」も含まれると考えていたからである。彼は、「有機体は、それぞれの流儀にしたがって死ぬことを望み、これら生命を守る番兵も、もとをただせば死に仕える番兵であったのだ。このようにして、生命ある有機体は、生の目標にもっとも短い道筋を経て(いわゆる短絡によって)到達することを助けるかもしれぬ作用(危険)に、きわめてはげしく抵抗するというパラドックスが起こる」と述べている。すなわち、「死の欲動」は、外的な脅威(危険)から自己を護るために文字通り必死の抵抗を試みるというのである。その時、フロイトの脳裡には、愛娘の生命を奪ったスペイン風邪が思い浮かんでいたのかもしれない。
個を超えた「生の欲動(エロス)」
一方、フロイトは、「生の欲動(エロス)」については、有機体と有機体が接合(生殖)することによって次の有機体へとその素質を受け継がせるための欲動であると考えた。それは、いわば「無限の生命」を維持しようとする欲動であるため、「死の欲動」と対立する。
精神分析家シミントンは「(米国の社会学者の)タルコット・パーソンズはフロイトの思想におけるこの結合させる物質(エロス)が、接合効果をもつ価値システムを通じて個人が有機体全体へと統合された有機的単位としての社会、というデュルケームの概念と類似していると指摘しました。……会社なり機関なりで働く人びとが何らかのかたちで集団同一性をもつのは、エロスを通じてのことなのでしょう」と述べている。
その意味では、フロイトの「死の欲動」理論は、戦争を引き起こし、継続させたような社会の集団同一性に対して、「否(いな)」という無意識的な抗議の声をあげていたともいえるように思う。そう考えると、フロイトの「ゾフィーの死以前から着想していた」という言葉も真実であったかもしれない。
2020年11月号
【特集:歴史にみる感染症】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

平島 奈津子(ひらしま なつこ)
国際医療福祉大学病院教授(三田病院精神科)