【特集:英語教育を考える】
座談会:AI時代こそ大切になる"ことば"の学びとは
2025/05/11
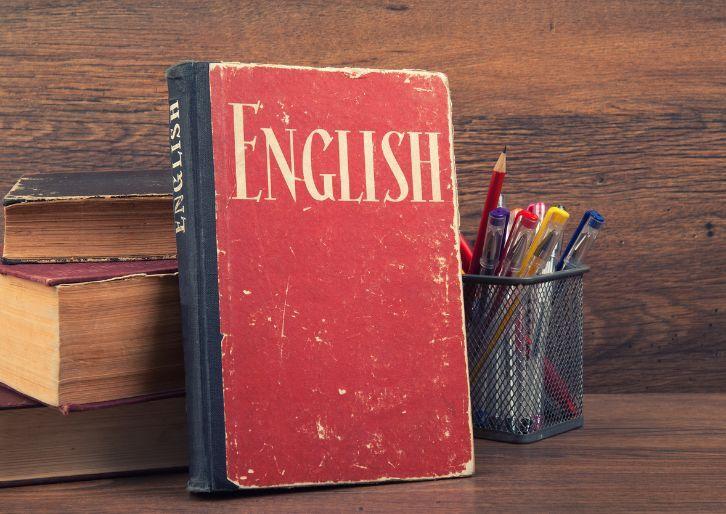
-

-

瀧野 みゆき(たきの みゆき)
慶應義塾大学大学院経営管理研究科講師(非常勤)、社会言語学者
塾員(1983文)。2016年英国サウサンプトン大学応用言語学博士課程修了(Ph.D.)。16年間英国に在住し、英語教授法等を学び、現在社会や仕事で「使うための英語」を教える。著書に『使うための英語』。
-

アダム・コミサロフ(Adam Komisarof)
慶應義塾大学文学部教授
1990年ブラウン大学教育学部卒業。2008年国際基督教大学大学院行政学研究科博士課程修了(Ph.D.)。16年より現職。専門は異文化間コミュニケーション。著書にThe SAGE Handbook of Intercultural Communication 等。International Academy for Intercultural Research 元会長。
-

山本 富夫(やまもと とみお)
慶應義塾ニューヨーク学院高等部教諭、同校主事
塾員(2007文)。幼少期より英語圏で育つ。大学卒業後、私立高校英語科勤務を経て、2011年慶應義塾湘南藤沢中・高等部教諭。12年~21年慶應義塾高等学校教諭を経て、21年より現職。
-

原田 範行(司会)(はらだ のりゆき)
慶應義塾大学文学部教授、同大学院文学研究科委員長
塾員(1988文、94文博)。博士(文学)。杏林大学教授、東京女子大学現代教養学部教授、同学部長を経て2019年より現職。専門は近現代英文学、比較文学、出版文化史。日本学術会議会員(言語・文学分野委員長)。
150年以上続く英語教育の議論
原田 今日は「英語教育を考える」をテーマとして皆さんとお話ししたいと思います。
日本では150年以上にわたって、英語教育に関して実に様々な議論がありました。英語教育は、一義的には言語教育ですが、世界における日本の役割や立場、あるいは政治経済、文化や科学技術のあり方にも深くかかわってきます。さらに、海外の情報を得たり、文化について考えるような場面で英語を使うこともあれば、実際に英語を使って交渉し、議論するという場合もあって、英語教育の目的も、英語を使う環境も、実に多岐にわたっています。
日本語という環境の中で生きている以上、すべての国民が、毎日英語を使って仕事をしたり、生活を営んだりするわけではありません。しかし、日本語だけでグローバル化、国際化する現代社会に対応できるかというと、決してそんなことはない。これは、福澤諭吉が、オランダ語では通じないからということで、慶應義塾を英学塾にした当時から変わらない状況だと思います。
英語はまた、日本のみならず、大学の入学試験で極めて重要な科目になっていますが、受験科目としての英語の学習が、実際の「英語力」とあまり結びついていないという指摘もあります。
英語学習は現在、小学校から始まっていますが、どのような展開が望まれるのか。特に高校から大学というところでは、様々な高大接続の可能性が探求されている中、具体的にどのようなプリンシプルや実践が考えられるのか。そしてまた、急速に利用が広まっているAIが人間の言語環境に大きな影響をもたらしている中で、英語教育をどのように考えていけばいいのか。
皆さんはこれまで英語教育、英語教育政策、あるいは日本人にとっての英語、異文化理解などについて、様々なご経験をお持ちだと思います。自己紹介を兼ねてまずお話しいただければと思います。
瀧野 私は大昔に慶應の東洋史で中国語と中国史を勉強し、その後、回り回って、今は慶應のビジネススクールでビジネスコミュニケーションとしての英語を教えています。
今までビジネスの中で英語を使ってきましたが、アメリカに留学して、自分の考えを英語で上手く伝えられず、苦労しました。どうして今まで学んだ英語教育が役に立たないんだろうとも考えました。一方で、イギリスに16年ほどいて、子どもがイギリスの学校で学ぶ中で、英語というものが、すごく豊かで面白く、また、日本の英語教育とは全く違う学び方があることも知りました。
日本人が、英語を使って世界に語りかけることをもっとできるようになってほしい。それを手伝うような教え方ができないだろうかと考え、その1つの選択として、English as a lingua franca、つまり、ネイティブ英語を規範にするより、世界中の人にわかりやすいということを重視する、「共通語としての英語」の考えを取り入れて教えています。
山本 私は4歳から7歳までイギリス、7歳から17歳までニューヨークで過ごしました。現在、教えている慶應義塾ニューヨーク学院の卒業生です。
このようなバックグラウンドですので、英語学習は逆算しているイメージです。つまり、冠詞や比較級や、関係代名詞等の文法事項は、使える状態から、逆に理屈を学んで生徒たちに教えていたので特殊な形だと思います。
授業において常に意識しているのは authenticity で、生徒には本物に触れてもらいたいと思っています。できるだけ原典を読んでもらうことを、特に慶應義塾高校(塾高)で教えている時は意識していました。
コミサロフ 私は、慶應の文学部で英語と異文化間コミュニケーションを教えています。それ以外にも慶應ビジネススクールや通信教育課程、経済学部CEMSプログラムなどで、英語の聞き取り練習やアカデミックライティング、異文化間コミュニケーションなどを教えています。出身は米国ですが、日本に住んで27年になります。
私は英語を教える際に、異文化間コミュニケーションとリベラルアーツとの相乗効果が出るようなアプローチをしています。
阿部 私は英語体験としては、たぶん幼少期が一番英語ができました(笑)。1歳頃から3年ほど北米にいて、保育園と幼稚園までは英語圏だったんです。ただ、日本に帰ってからはあっという間に英語を失いまして、失ったものをいかに回復するかで苦労してきました。
その後、海外に住んだのはずっと後で、博士論文を書くためにイギリスに行って、3年半ほど勉強しました。その後はずっと日本です。ですから、英語との出会いは非常に中途半端という感じです。
その後も境界上の模索は続いて、留学先は英国ですが、博論は米詩人 Wallace Stevens だったり、20世紀詩が専門と言いいながら、実際には小説や日本文学のこともやっています。ただ、言葉についてはずっと関心があり、言語学にも興味があるので、今でも言語と文学のつなぎ目みたいなところでいろいろ仕事を試みています。
「しゃべりたいけど、しゃべれない」
原田 よく出てくる身近なテーマに、「しゃべりたいけど、しゃべれない」ということがありますね。このあたり、瀧野さん、いかがでしょうか。
瀧野 「しゃべりたいけど、しゃべれない」ということは多くの人が感じることだと思いますが、それは当たり前のことではないかとも思います。
つまり、英語で話したり聞く練習をしないで急に話そうとしても、すぐにはできないわけです。今まで自分が学校教育などで学んできたものを、今度は使うために訓練する場がどうしても必要だと思います。学校で学んだから「さあ、ペラペラになるだろう」という期待値そのものが大きすぎるというのが1つあります。
では、その訓練をする場が英語教育のどこにあるのがいいのだろうということです。私は英語を使いたい学生たちが自分の興味にあわせて英語を「使う練習」をする場は、大学が担うべきなのではないかと考え、そういう授業をしています。
今まで学んできた学校英語にダメ出しするのではなく、それをいかに上手く使って、自分が表現したいことに結びつけていくか、学校で学ぶ英語と実社会で使う英語の橋渡しをするということです。多くの日本人は海外で英語がどのような場でどう使われているか、どんなスキルが必要か、知らないことが多い。だから、「こういう場面があるんだよ」などと教えて訓練していけば、日本で英語を勉強してきた学生たちも英語を使えるようになると思います。
ただ、英語で何もかもできるようになるのも難しく、言葉というのはなかなか手ごわいものです。ですから、まずはそれぞれの学部によって英語の使い方が違うのだとしたら、その学部に合った使い道を意識しながら訓練していくことが、大学でやるべきことではないかと私は考えています。
原田 なるほど。山本さんは、塾高などでのご経験をお持ちですが、この問題をどうお感じになりますか。
山本 塾高も含めて義塾の一貫教育校は様々な工夫をしています。ただし、どうしても物理的、時間的な制限があります。例えば塾高ですと標準クラスと上級クラスの2つに分けます。上級のクラスは20人ぐらいで収まりますが、標準クラスですとどうしても35人くらいになってしまいます。その人数で50分の授業を週数回行う中で、リスニング、スピーキングなどの練習時間が確保できるかというと、なかなか難しいところがあります。
逆に皆様にお伺いしたいのですが、大学や大学院で教えていらっしゃる中で、高校のうちにこれはやっておいてほしいというのはどういう部分でしょうか。
瀧野 1つは、「聞く力」を鍛えておいていただきたいと思います。聞く力はすべての基礎になる部分ではないかと私は思っています。「読む」ことについては辞書で調べながらでもできますが、「聞く」のは調べながらできないので、その時の自分の持っている力がそのまま反映されます。
英語の音に耳を慣らすには時間がかかるので、リスニング力がないと大学の授業で追いつくのが大変です。私はディスカッションをよく教えますが、そこでたとえ意見を表明することができるようになっても、グループの中での話のやり取りにはどうしても聞き取る力が必要なので、ぜひ高校レベルまでにある程度聞く力を育てていただきたいなと思います。
山本 確かにそうですね。
日本語話者の環境と英語学習
原田 阿部さんは東京大学で教えておられていかがですか。
阿部 瀧野さんがおっしゃったことはその通りだと思います。つまり、やっていないのにできるわけがない。しかし、TOEFLを受験科目にすれば朝起きたらいきなりしゃべれるようになるのではないかと、何か魔法の薬みたいに話す人もいてびっくりします。
ここで大事なのは、しゃべれないから日本の英語教育はダメなんだ、みたいに全否定になりがちですが、まず日本語の問題と日本語話者の環境の問題を思い出さなければいけません。日本にいたら普段英語に触れる機会がとても少ないわけですから、日常的に他の言語にモードを切り替えるスイッチがそもそもないとも言えます。
例えばヨーロッパに住み、日常的に3つ4つの言葉に触れている人は、自然と言語間のスイッチを変換する準備ができていて、他言語のモードにあまり抵抗がない。日本語話者の場合、その抵抗感がすごく強いわけです。
それから日本語と英語を比べると、日本語のほうが音の種類が少なく、英語で使われる音のほうが細分化されて感じられるので、発音は当然難しいわけです。だから、日本語話者が他の言語の話者に比べて英語の発音で苦労し、なかなか上達しないのは仕方がない。変にコンプレックスを抱く必要もないし、英語教育が悪いわけでもない。
一番はリズムの問題で、英語のストレスアクセントが日本語のリズムと全く違うので、そこがネックとなっています。しかもそのことに気がついていない人が多い。単に「聞き取れない!」「発音が上手くいかない!」と思っている。なので、意識的にストレスアクセントに慣れるようにすると大きく前進すると思います。
ただ、山本さんがおっしゃったことにつながるんですが、高校の授業でひたすらリスニングをやればいいかというと、それはなかなか難しいと思うのです。リスニングは大量に時間を使わないとできるようになりません。英語を第2言語として学ぶ人はどうしても文法の知識が必要になるので、学校では文法や基礎的な語彙といった、オーソドックスなところを押さえてもらう必要がある。リスニングは上手く家庭学習や端末の活用などを考えてもらうのもよいかと思うのです。
ですので、スピーキングやリスニングに特化することより、基礎体力、英語の体幹を身に付けてもらいたいというのが、大学教員の立場からの私の意見です。特にこの10年、20年はこれができていない子が多い。知性のレベルは高いのに、もったいないなと思う例がしばしばあります。
2025年5月号
【特集:英語教育を考える】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

阿部 公彦(あべ まさひこ)
東京大学大学院人文社会研究科教授
1989年東京大学文学部卒業、97年英国ケンブリッジ大学博士号取得(Ph.D.)。専門は英米・英語圏文学、英米詩研究。英語教育政策についての発言多数。著書に『理想のリスニング』『ことばは「形」から読む』等。