【特集:日本の“食”の未来】
鈴木隆一:AI味覚センサーが引き出す日本食の力
2022/02/04
日本人の味覚は世界一
味覚について調べていくうちに「日本人の味覚は奇跡的だ」と思うようになり、『日本人の味覚は世界一』(廣済堂新書)という本まで出版した。
日本人の味覚のすごさはひと言でいえばうま味の感受性。図2のとおり、レオで調査した結果、日本食を平均比較で見ると、海外の食に比べてうま味が非常に強いのだ。外国に行って「物足りない、日本の食が懐かしい」と思われる正体は"うま味"なのだ。
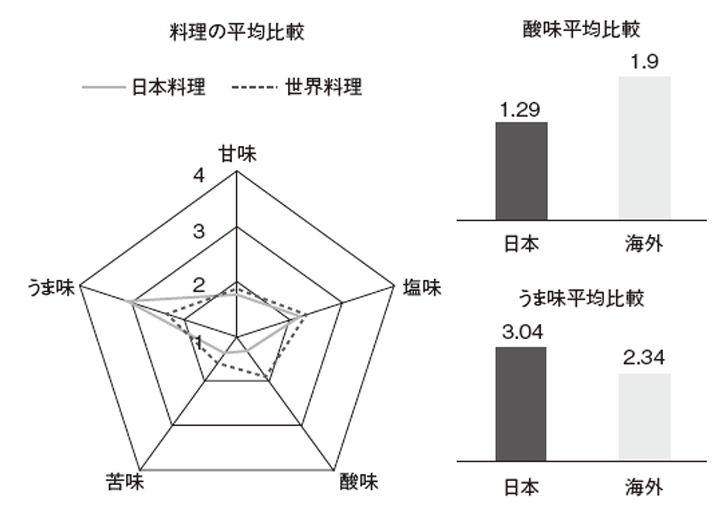
では、なぜうま味をそこまで感じる食文化になったかというと、海に囲まれている島国という日本の地理的要因が関係している。イギリスも同じではないかと思うかもしれないが、イギリスで獲れる魚にはそれほどバリエーションが多くないのに対して、日本は国土を海に囲まれているだけでなく海との接点が長く、また南北の潮の交点でもあるため、海の幸に恵まれて海洋資源が豊富だ。
そもそも1000万人以上の人口の国・地域に成長するためには、動物性タンパク質を取ることが必須で、肉と魚を食べて人口が増えるのだが、魚というのは、肉に比べて収穫量のバラツキが激しいため、日本以外の他の地域では肉の代替品というポジションに甘んじていた。ところが、日本は江戸時代に2000万~3000万ぐらいの人口の動物性タンパク質をほとんど魚で賄うことができた。動物性タンパク質を魚介類で取っているうちに鰹だしとか昆布だしといった出汁の文化が非常に発達していった。これが日本食にうま味が多い理由である。
他にも、日本人は甘味の感覚を白米で培ってきた。砂糖の甘さに比べ、白米は噛めば噛むほど甘味が出てくるので、よく味わうようになり、味覚のレセプター(受容体)が自然と鋭くなっていった。
日本の環境に近かったのが中国の東南部で、実際、寿司の原型はここで生まれた。動物性タンパク質は長期保存が難しいのだが、そのソリューションとして炊いたお米に魚を入れて保存していた。お米は自然発酵し、そのときに発生する乳酸が魚の腐敗を妨げる働きをしたのだ。これが日本に伝わって、寿司になった。ただ、大陸ではその後内陸からきた民族の肉重視の考え方により、淘汰されてしまったとされている。
食文化を発展させる
食というのは文化なので、発展していくし、衰退もする。発展していくためには新しい組み合わせが必要になる。例えば、今では当たり前の肉じゃがも洋風の食材に和風の味付けなので、明治になるまではあり得ない組み合わせだった。それがいつの間にか市民権を得て広まっていった。
味覚も時代とともに変わる。最近の日本人は、コーヒーの苦みに対して、慣れてきている。本来あの種の鋭い苦みは日本には存在していなかった。確かに、お茶にも苦味はあるが、お茶は苦味+うま味であるのに対して、コーヒーは苦味+酸味で鋭い苦みとなっている。イタリア料理などをイメージしてもらうとわかりやすいのだが、西洋料理では、酸味とうま味の組み合わせがポピュラーなのに対して、日本食は塩味とうま味の組み合わせがオーソドックスだ。
現在は味覚がグローバル化してきており、昔ほど各国の味覚が変わらなくなってきている。近年では、世界でもうま味に対する嗜好が高まってきていて、世界中が"うま味好き"になっているので、うま味が豊富な日本食にとっては大きなチャンスである。大陸と絶妙な距離にあることで生まれた、日本人の希有な味覚/食文化を世界中に輸出して、日本の食がもっと広がると日本の未来も明るくなる。
その際には前述の肉じゃが同様に現地に受け入れやすい形でアレンジしていくことが重要になる。人間は「新しすぎる味」は警戒してしまうし、「いつもの味」は飽きてしまうので、「ちょっと新しい味」が良いのだ。「ちょっと新しい味を」どのように実現すればいいかを定量的に味覚データを用いて議論できるようにしたい。現地の料理の味覚を数値化して、AIで学習させるとどのような味が受け入れられるかを計算することは理論的には可能なので、あとは成功事例を作っていくだけだ。
ラーメン屋の再建に挑戦した塾生時代に感じた「何となくではなく、科学的なデータに基づいた商品開発」を実現する未来はもうすぐそこに来ている。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
2022年2月号
【特集:日本の“食”の未来】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |
