【特集:ジェンダー・ギャップに立ち向かう】
ジェンダー・ギャップ指数に見る男女の雇用格差
2020/04/06
日本における女性活躍推進
日本では、今から35年前の1985年に、国連の女子差別撤廃条約の批准に向けて、男女雇用機会均等法が成立した(翌年施行)。その後の改正を経て、同法は、雇用管理の各ステージにおいて性別を理由とする差別を全面的に禁止するに至っている。また、仕事と育児の両立支援についても、育児休業制度や保育サービスなどが次第に充実し、女性の労働市場への参加も進んできた。しかしながら、ジェンダー・ギャップ指数など、国際比較をすると、日本には、大きな男女の雇用格差が残っている。
こうした状況を踏まえ、2015年には女性活躍推進法が成立した。同法により、国、地方公共団体、および従業員数301人以上の企業は、女性の活躍に関する状況の把握と課題分析を踏まえた、女性活躍推進の行動計画の策定や情報公表が義務づけられた。そして、施行3年後の見直しを経て、2019年には、情報公表の強化や、101人以上の企業へ行動計画策定義務を拡大することなどを内容とする改正法が成立し、今年6月に施行されることになる(対象企業の拡大に関する部分は2022年4月施行)。
同法成立の背景には、日本における女性管理職比率の低さへの問題意識があった。そして同時に、日本の男女間賃金格差の大きな原因が女性管理職の少なさにあるため、管理職に就く女性が増えることは賃金格差の縮小に貢献することも期待される。そこで次に、日本の女性管理職比率が低い理由を考えながら、取り組むべき課題を検討しよう。
女性管理職比率と女性社員比率の関係
図表2は、産業別の女性管理職(課長級+部長級)比率と女性社員比率(社員全体に占める女性の比率)の関係を示している。この図から、女性管理職比率には業種ごとに大きな差があること、そして女性社員比率が高い産業ほど女性管理職比率も高いという正の相関関係が観察できる。
つまり、女性の管理職を増やしたいのであれば、女性の管理職登用に取り組むだけでなく、採用や定着(継続就業)などにも努めていく必要が示唆される。採用、仕事と育児・介護の両立支援、長時間労働の是正、職場風土、そして配置・育成・教育訓練および評価・登用といった幅広い職場環境の改善に努めることが必要となろう。
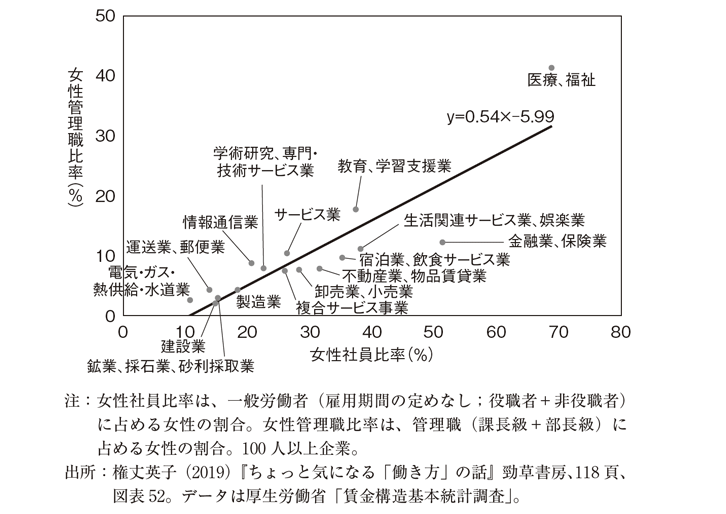
コース別雇用管理制度
男女雇用機会均等法が施行された頃から、大企業を中心に、総合職、一般職といったコースを設定して、採用時からコースごとに異なる雇用管理を行うシステムが導入され普及してきた。そして、管理職候補を養成する総合職には男性が、定型的業務を行う一般職には女性が多くなっている。このため、将来管理職になるための訓練や昇進の機会を得る女性が少ないことになる。
厚生労働省「雇用均等基本調査」(2017年)によれば、コース別雇用管理制度のある企業の割合は企業規模30人以上のうち11.2%とさほど高くはないが、5000人以上の企業では52.8%に及んでいる。また、産業別では、「金融業、保険業」で導入企業の割合が高くなっている。図表2を見ると、「金融業、保険業」は傾向線の下に位置し、女性社員比率の高さに比べて女性管理職比率が相当に低い。背景には、こうしたコース制度による処遇の違いもある。
2020年4月号
【特集:ジェンダー・ギャップに立ち向かう】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |
