【特集:ジェンダー・ギャップに立ち向かう】
ジェンダー平等を阻む「家族主義」の諸相
2020/04/06
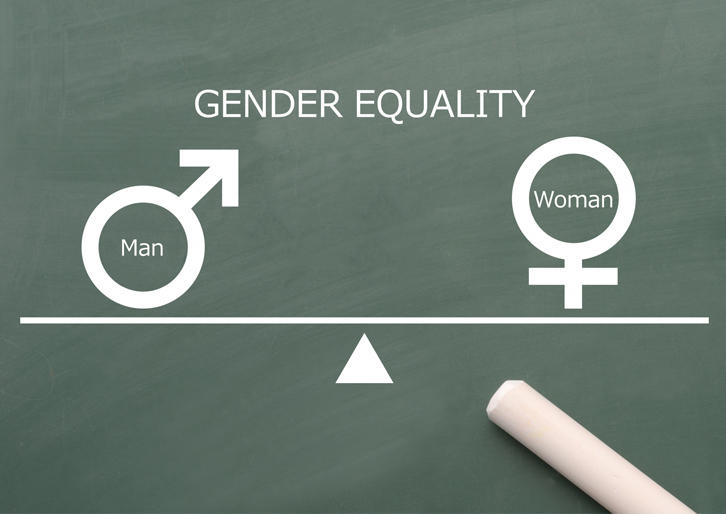
1.ケアの家族主義──出生率と家族規範
2015年度に内閣府が実施した「少子化社会に関する国際意識調査」において、自分の国が「子供を生み育てやすい国だと思うか」という問いに対し「とてもそう思う」と答えた人の割合は、日本が対象4カ国で最も低い8%にとどまった。こうした子育てに対する「窮屈さ」の背景には何があるのだろうか。本稿では、日本社会に根強く残る「家族主義」に注目して考えていきたい。
長らく日本では、女性の就労率の上昇が少子化を引き起こしたと考えられてきた。しかし現在では、女性の就労率と合計特殊出生率に関するこのような通説が誤りであることはすでに多くの国際調査で明らかになっている。デンマークの福祉社会学者エスピン=アンデルセンは、EUのデータに基づいて、女性の就労が普及した国ほど出生率が高くなる傾向を明らかにし、就労率と出生率にはむしろ相関関係さえ存在すると指摘している(『アンデルセン、福祉を語る─女性・子ども・高齢者』林昌宏訳、NTT出版、2008年)。
現代社会において、少子化を考えるうえでキーワードになるのが福祉の「家族主義」である。ここで言う「家族主義」とは、世帯がそのメンバーの福祉に主要な責任を負うべきとするシステムを指し、育児や介護などのケア責任が、規範的にも制度的にも家族に押し付けられている社会を批判的にとらえる概念である。
皮肉なことに、「家族主義」が強い国で家族形成が停滞している。国際比較調査からは、超低出生率国は日本と韓国、イタリアやスペインなどの南欧などであり、これらの国々に共通するのは「家族主義」的な規範や制度が根強いことである。家族主義が女性の就労率と出生率の双方を抑制しているのである。
現代の福祉政策において、ケアの「脱家族化」は基本前提であり、ケアの家族への依存をいかに軽減するかが問われている。アンデルセンはこうも指摘する。「家族の仕事を外部化することは、家族の絆を根底から崩し、家庭生活の質を損なうであろうといった信条が流布している。しかし、すべてのデータは、まったく逆のことを示している」。つまり、現代社会では「伝統的な家族主義」が家族形成の足かせになっている。彼は福祉を家族に依存する「家族主義」を脱することこそが「家族の絆」を強化するのだという逆説を示す(『平等と効率の福祉革命──新しい女性の役割』大沢真理監訳、岩波書店、2011年)。
日本は、国家と市場の役割が限定的で、親族の支援も少ないという意味で、家族主義が特に強固な社会である。それは欧州諸国に比べて家族政策全体の財政的な規模が著しく小さいことにも表れている。ジェンダー平等実現のための第1の条件は、福祉の家族主義を脱することにある。
2.ジェンダー家族主義──男性とケア
さらに、アンデルセンは「男性の育児」が出生率上昇の鍵を握ると言う。国際比較データからは、男性の家事・育児に費やす時間の多い国、そして育児休業取得率の高い国が高い出生率を示している。アンデルセンは、国の福祉政策のみならず、夫婦間の関係改善を重視し、「女性の男性化」に対応して「男性の女性化」こそが重要だと指摘する。アン・マリー・スローターも、男女の平等が達成されるためには、女性の就労支援だけでなく、「男性がケアの担い手になること」が不可欠だと述べる。そのためには、競争を重視する「男らしさ」の価値観やケア労働そのものの社会的意義が見直される必要がある(『仕事と家庭は両立できない?──「女性が輝く社会」のウソとホント』関美和訳、NTT出版、2017年)。
重要なのは、仕事と育児を両立できる諸制度の導入と、父親の育児を推進するための育児休業制度の仕組みづくりである。父親の育児関与の度合いが子どもの出生に大きな影響を及ぼすことはすでに多くの研究が実証している。例えば、日本の専業主婦世帯では、男性の労働時間が長いと第2子が生まれにくく、共働き世帯では、父親の家事・育児時間が長いと第2子が生まれやすいという(Nagase andBrinton 2017)。第2子出生の鍵は男性の労働時間と家事・育児時間が握っているのである。
日本の男性の育児休業取得率は、2018年度に6.16%と過去最高を記録したものの、国際的にみるとその水準はきわめて低く、男性の育児時間も先進諸国のなかでは最も短い。職場では長時間労働する者を優遇する傾向はなお強く、育児休業を取る男性を評価しないことが大きな要因である。
男性をケアの担い手にするには何が必要か。ジェンダー平等という「理念」に訴えることが大切なのは言うまでもない。しかし、制度的工夫によって男性の意識や行動を「矯正」する道も探らねばならない。「育休を取りたい」という男性の希望は近年大きく増加している。にもかかわらず、実際の取得率が低率にとどまるのは、制度があっても風土がないからである。
北西欧諸国でほとんどの男性が育児休業を取得するようになった契機が「パパ・クオータ制度」の導入であった。この制度は1993年にノルウェーで開始されたもので、子ども1人につき育休を最長で59週間取得でき、うち10週間は配偶者が交代して取得することを義務づけるという内容である。実際、導入前には5%に過ぎなかった取得率が90%以上まで向上し、出生率も上昇した。クオータ制の詳細は国によって異なるが、格差是正のために意図的に「ロールモデル」を生み出し、制度・環境をデザインすることで男性の意識・行動を変革することは効果的である。
3. 標準家族主義から多様なパートナーシップとケア関係の承認へ
日本のジェンダー平等を阻む要因の1つとして、画一的・固定的な家族観もある。ある特定の家族形態のみを「標準」とみなし、その他を「逸脱」や「病理」とみなすような家族観のことをここでは「標準家族主義」と呼んでおこう。
海外に目を向ければパートナー関係は多様化している。象徴的な事象として、婚外出生率の上昇があげられる。2012年時点で、先進諸国の婚外出生割合は、日本が2.2%であるのに対し、スウェーデンやフランスなどでは過半数を占めており、そのほかの国でも3割から5割を占める。つまり、「結婚している夫婦が子どもを産む」ことは自明のことではなくなりつつあり、結婚した夫婦から生まれる子どもがもはや少数派になっている国さえある。先進国を比較すると、法律婚にとらわれない多様なパートナー関係とその出生、子育てを承認・サポートする社会において家族形成が促進されていることがわかる。
パートナーシップの多様化という点で、より大きな世界的な変化が同性婚の法制化であろう。2000年のオランダを皮切りに、現在、世界30以上の国と地域において同性カップルの結婚が異性カップルと全く同等の結婚として認められている。2014年には、国連も明確に「同性婚に異性婚と同等の権利を与えるべき」との声明を発表した。養子縁組や生殖補助医療を通じてレズビアンやゲイのパートナー関係による子育ても一般化している。男女の異性愛カップルのみを家族生活の基盤とするような「異性愛主義的家族」の常識は消滅に向かっている。
日本においても「標準家族主義」を脱し、「かたち」にとらわれないケア関係の実態に焦点化した法・政策への転換が求められている。上記のパートナー関係に限らず、ひとり親や里親等の非血縁親子を含め、多様な家族形成・子育てのあり方を承認し、制度的に保障している国ほど出生率が高い傾向にある。
2020年4月号
【特集:ジェンダー・ギャップに立ち向かう】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

阪井 裕一郎(さかい ゆういちろう)
福岡県立大学人間社会学部専任講師・塾員