【その他】
【講演録】福澤諭吉と在来産業──酒造業に対する考え方を中心に
2024/07/26
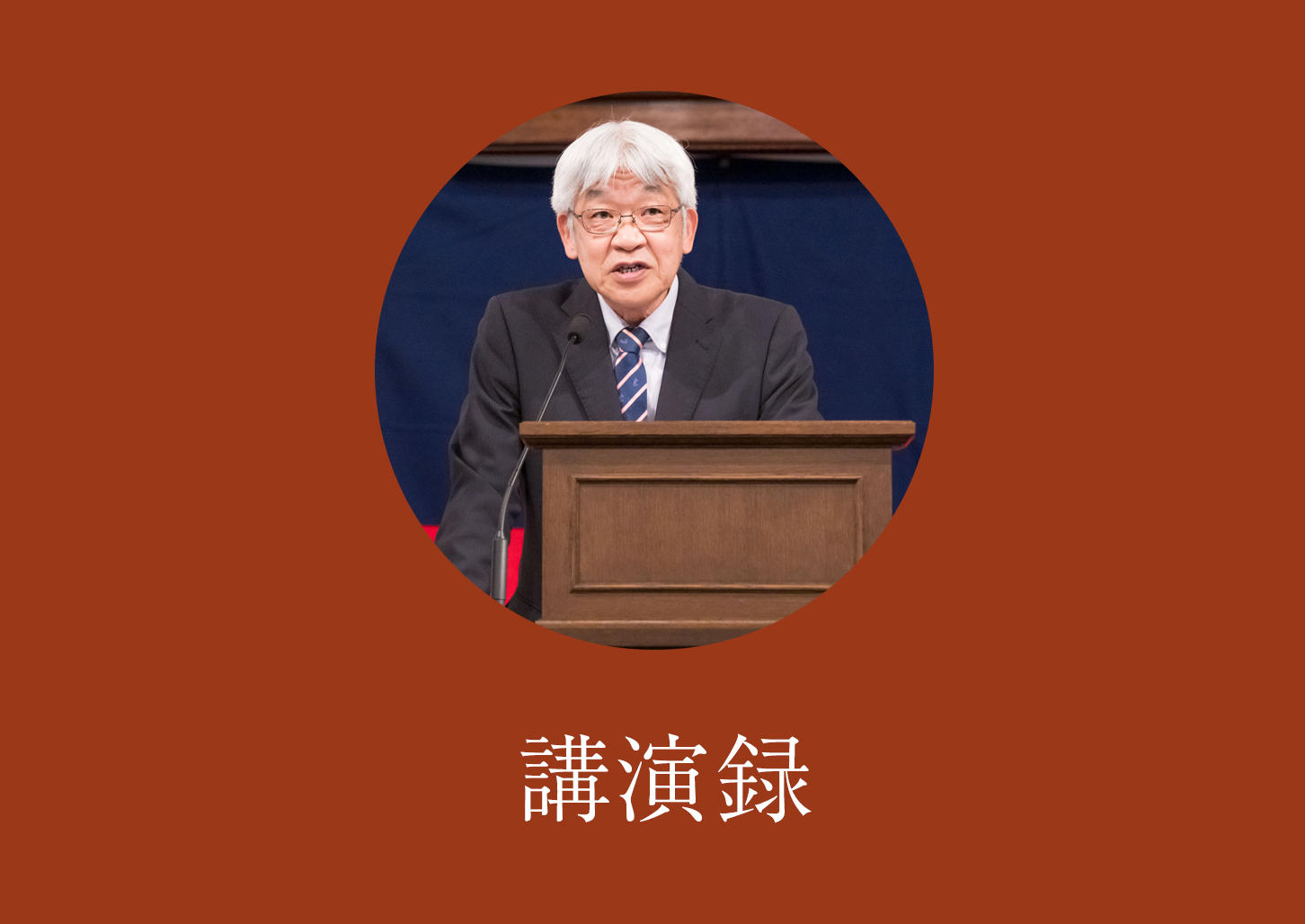
ただいまご紹介に与りました井奥でございます。私はもともと福澤研究の専門家ではないのですが、福澤研究センターの所長を務めたこともあって、福澤先生関係の講演もいろいろなところで頼まれます。その都度、浅学非才の私がそういうお話をすることに本当におこがましく思う次第ですが、自分にとっての勉強にもなると思い、これまでお引き受けしてきております。
今、こうして後ろから福澤先生に見下ろされておりますと、本当にお話ししにくいと言いますか、「お前しっかり勉強しているか」というような声が聞こえてきそうですが、辛抱してお付き合いいただければと思います。今日は気持ちとしては「福澤先生」と言いたいのはやまやまですが、学術の講演ということで、「福澤諭吉」と呼ばせていただきます。
在来産業とは何か
今日のお話は福澤諭吉と在来産業についてです。在来産業の中でも特に酒造業に対する考え方を中心にお話させていただきます。在来産業とは、ごく簡単に言えば、維新前の近代以前から日本に存在する伝統的な産業ということになります。具体的には酒造業や醬油醸造業、織物業あるいは陶磁器業。それから生糸製糸業は阿部武司先生の分類によれば、座繰製糸は在来産業に分類され、器械製糸になると近代産業に分類されています。この在来産業の中で、酒造業というのは当時最も生産額が大きかった産業です。
酒造業あるいは醬油醸造業といった醸造業は当時も今も、日本が世界をリードしていると言っても過言ではないと思います。例えば、イギリスでビール工場を見学した岩倉使節団は、非常に詳細な見学の記録を『米欧回覧実記』(久米邦武編)の中で記していますが、「醸造術ハ、日本ノ長技ニ属ス」つまり、醸造術は日本の得意技と言っています。続けて「農産ヲ製作シ、醸造品トナシテ輸出スルハ、尤国産倍殖ノ眼目ヲ得タルモノト謂フヘシ」。醸造品、農産物から醸造品を作って輸出するというのは国産倍殖を得るものとして、非常に期待できるといった趣旨かと思います。
また「日本ノ酒ハ……醸法頗ル高尚ニ属ス」とあります。その造り方は非常に高度な技術によるということです。続けて「只未タ欧洲人ニ嗜好ヲ生セサルノミ、飲料ハ開化ニ従ヒ進ミ、異味ヲ好ムハ人ノ通慾ナレハ、今ヨリ其醸法ヲ慎精ニシ、貿易ノ道ヲ得ハ、必ス一箇ノ輸出物品トナラン」と言います。今はまだ欧州の人は日本の酒を好んでいないけれど、飲料は時代とともに違う味を好むのが人の常であるから、そのうち必ず有力な輸出物品になるだろうということです。
これは確かにそうかと思います。近年、外国で日本酒ブームが起こっていると言ってもいい状況です。少し前までは、外国人はなかなか日本酒を飲まなかったのですが、近年、当たり前のように日本酒を飲んでいる姿が見られます。確かに時代とともに好みは変わるので、輸出物品として有効であるという考えも、もっともなことかと思います。ただ、それには少し時代が早すぎた感がありますが。
さらに、同書は醬油に関しても言及しています。「醤油ハ、蘭人之ヲ輸送シ、独逸(ドイツ)地方ニ賞味セラレ、英人モ亦之ヲ好ム」。すでに江戸時代、鎖国下の長崎からオランダとの貿易で醬油がヨーロッパに輸出されて、それを口にしたフランスのルイ14世が絶賛したという話も残っています。明治の初めにも、醤油はオランダ人が日本から輸送してドイツで賞味され、イギリス人もまたこれを好んだようです。岩倉使節団は非常に優秀な人たちで構成されていた使節団ですが、当時、外国の醸造業を見た人たちは、日本が得意とする醸造業に対してこういった認識を持っていたわけです。
また明治10(1877)年に前田正名(まさな)に伴われてフランスにワイン醸造の習得に行った山梨の酒造家の子弟の高野正誠と土屋龍憲の残した記録には「葡萄酒醸造ノ義ハモットモ易シ」と書かれています。高野や土屋という酒造家の子弟から見て、葡萄酒を造ることは最も簡単に思えたということです。「タダ葡萄ヲ潰シ桶ニ入レ置キ、沸騰後ニ至リ暖気サメタルトキ絞レバ則チ酒トナルナリ」。葡萄を潰して桶に入れておくと、発酵するとぶつぶつと泡が出てくる。それを「沸騰」と言っています。また発酵すると熱が出て温かくなるわけですが、それが冷めた時に絞ればもうそれで酒になるのだと記しています。日本酒の造り方と比較して簡単だという印象を持ったのだろうと思います。
海外で飲まれる日本酒
ちなみにその頃、明治政府は、官主導でワイン製造にはかなり積極的になっていました。その中心人物である大久保利通は岩倉使節団でヨーロッパに行き、現地でワインやビール工場の見学もしています。清酒は米を原料とするお酒です。日本の主穀、食べるものの中心が米であった時代にあって、米を酒造業の方に回していると飢饉などがあった時に食料不足になるのではないかと考え、米に代わる材料でお酒を造ったらどうかと、明治政府は積極的にワイン造りを進めようとしていたわけです。
ところが、ヨーロッパから輸入したブドウの品種が日本の気候風土に合わなかったということもあり、また当時ヨーロッパで日本酒の需要が少ないのと同じようにワインの需要も日本ではまだ少なかったので、この計画はどうもうまくいかなかったようです。
現在の醸造業の状況はどうかと言いますと、醬油は今や世界の調味料になっていると言ってもよいかと思います。日本の大手醬油会社は海外に工場を持っています。最大手のキッコーマンは海外に8カ所も工場を持っており、海外での醬油生産は国内での同社の醬油生産の倍近くになっています。
日本酒のほうも、海外でブームが起き、大手の日本酒の会社は海外に工場を持っていますし、輸出もさかんに行われております。私はハレという旧東ドイツの人口20万くらいの地方都市に大学の集中講義で呼ばれていくことがよくあるのですが、そこにお寿司屋さんが何軒かあり、その中の「サクラ」というベトナム人が経営しているお寿司屋さんには8種類くらいの日本酒が置かれています。ハレという街は日本人が観光で行くようなところではありませんので、お客さんもほとんどドイツ人なのですが、店にはたくさんのお客さんが入っていて、お寿司を食べ、皆、日本酒を飲んでいます。
また、「獺祭」という最近評判になっているお酒がありますが、アメリカに工場があり、外国での日本酒ブームに一役買っていますね。今も昔も醸造業は日本の得意とするところであることがわかるかと思います。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

井奥 成彦(いおく しげひこ)
慶應義塾大学名誉教授