【特集:青少年とスポーツ】
高野連が投球数制限に至るまで
2020/03/03

昨年11月29日、日本高等学校野球連盟(日本高野連)は理事会を開き、同連盟主催の全国大会ならびに地方大会において、1人の投手の投球数を1週間で500球以内に制限することを正式に決定した。これは、日本高野連からの要請により発足した「投手の障害予防に関する有識者会議」が同月20日に発表した答申を受けてのことだった。
この有識者会議の座長を務めた経験を踏まえ、本稿ではこうした決定がなされた背景、決定に至るまでの経緯、そして今後の課題などについて述べることとしたい。
〝高校野球〟とは何か
高校野球は数ある学生スポーツのなかでも花形的な存在だろう。8月の選手権大会(夏の甲子園)は、夏休みのど真ん中、阪神甲子園球場を2週間以上も借り切って開催される一大イベントだ。その間の観客動員数は80万人を超え、NHKは全試合をライブ放送する。昨年の決勝戦の視聴率は平日の昼間にもかかわらず15%に達し、まさに国民的行事といっても過言ではない。
そんな高校野球にも実は陰りが見え始めている。高野連の加盟校数(硬式)は、05年の4,253校をピークに減少に転じ、19年は3,957校となっている。 より深刻なのは部員数で、ピーク時から15%の減少で、1年生部員に至っては25%も減っているのだ。
その原因は明らかだ。まず日本全体で青少年の数が減っている。特に、16歳~18歳男子はここ20年で560万人も減少した。2つ目にスポーツの選択肢が増えている。20年の東京五輪における実施競技数は33にも及ぶ。近年ではバスケットボールや卓球など、スポーツのプロ化も進み、もはや野球だけが子どものあこがれるプロスポーツというわけではない。そして、3つ目に選手個人の人権尊重の動きがある。禁欲の修行道場に入るかのように部員全員が頭を丸坊主にし、集団のためにはいかなる自己犠牲をも厭わない野球部のイメージは、現代の若者たちにとって前時代的に映るだろう。
ところが、困ったことにこうした前時代的要素が高校野球のウリになっているのである。〝古き良き時代〟へのノスタルジーといってもいい。高校野球部の部活動を見学すると、どこの部員も例外なく帽子を取って「こんにちは」と大声で挨拶する。休み中もほぼ毎日、朝から晩まで汗と土まみれになって練習する。そして試合では常に全力プレーで、負ければ大粒の涙を流して甲子園の土を集める。今どきこんな〝純真な〟若者が身近にいるだろうか。もはや絶滅危惧種とでもいうべき〝高校生らしさ〟に多くの日本人は心を動かされ感動するのである。
こうしたイメージが定着した背景として、高校野球が〝教育の一環〟とされている点に注目すべきである。そもそも日本に野球が持ち込まれたのは、明治初期の東京の学校(大学南校)である。そこから全国各地の中等学校に伝播し、現在の甲子園大会の前身である全国中等学校優勝野球大会が開かれるに至った。だが、野球の試合を見れば明らかなように、グラウンドにいる選手の多くは突っ立っているだけで、あまり運動しているようには見えない。攻撃中はほぼ全員がベンチに腰掛けている有様だ。勉学に励み身体を鍛錬すべき学校で行う活動としては不適切に見えてもおかしくない。実際、明治後期に『朝日新聞』が22回にわたって「野球と其害毒」という記事を連載し、学生野球の抱える教育上の問題点を厳しく指摘したほどだ。
そこで必要となったのが、学校で若者が野球をやることの大義名分である。それは一見遊んでいるように見える野球に教育的要素を導入することで批判をかわすという発想だ。すなわち、ハードで長時間の練習は〝忍耐力〟や〝精神力〟を養うための手段として正当化され、規律の厳守や違反した際の連座制は徳育のひとつとして容認された。さらに、先の大戦中に野球が〝敵性スポーツ〟と見なされ批判の対象となったことによりこの傾向はさらに強まった。
こうした歴史的経緯が戦後の高校野球に影響を与えたことは間違いないだろう。図1が示すように、高校野球部では、ほぼ毎日長時間にわたる練習が常態化している。また、高校野球指導者の約1割が体罰を容認しているとの調査報告もある(*1)。教育には投資的側面があることから、理不尽と思える状況であっても〝将来のため〟として正当化されてきたと思われる。
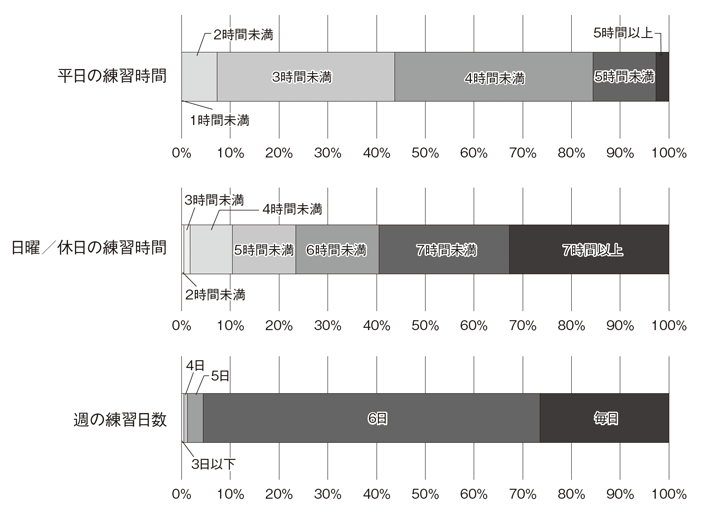
有識者会議発足の背景
高校野球関係者のなかには、華やかな面に隠れた悪弊を改善することに意欲を示す者も少なからずいた。その1人が新潟県高野連会長の富樫信浩である。
有識者会議発足の直接のきっかけは、富樫が「1投手1試合100球まで」という単純明快なルールを新潟県の大会に導入すると宣言したことである。これが大きく報道されたことで富樫は一躍〝時の人〟となったのだが、彼は新潟県高野連の理事長を務めていたときからさまざまな改革に乗り出していた。その要点は、野球界の縦割り体制を廃し、選手ファーストを徹底させるというものである。
すなわち、09年に新潟県野球協議会を立ち上げ、中学、高校、社会人野球の団体が顔を揃える場を作り、12年には新潟リハビリテーション病院の医師の協力を得て〝野球障害ケアネットワーク〟を設立した。なかでも特筆すべきは、すべての小中学野球選手に〝野球手帳〟を配布したことだ。そこには、身長や体重などの成長の記録に加え、各種検診の記録や医療機関での受診記録などが書き込めるようになっており、野球関連のケガに関する情報をすべて網羅するよう設計されている。
つまり新潟県高野連の〝1試合100球宣言〟は唐突に出てきたものではない。私は16年に出版した『高校野球の経済学』執筆のさい、日本高野連理事の田名部和裕から富樫に会って話を聞くよう強く勧められた。一部報道では、日本高野連が新潟の先走りを不快に思っていたかのように伝えられていたが、それは誤解である。むしろ、日本高野連は新潟県のおかげで、懸案事項であった投手の障害予防問題に正面から取り組むきっかけをつかんだのである。そして、同書を出版したという理由から、野球経験のない私に有識者会議座長の就任依頼があったと推察される。
2020年3月号
【特集:青少年とスポーツ】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

中島 隆信(なかじま たかのぶ)
慶應義塾大学商学部教授、日本高等学校野球連盟
「投手の障害予防に関する有識者会議」座長