【特集:青少年とスポーツ】
女子アスリートの思春期からの教育・支援
2020/03/05

はじめに
女性アスリートには、思春期以降、月経と関連した女子特有の問題が生じてくる。選手も指導者もよく理解して対処することが、競技パフォーマンス、学生生活、その後の人生において重要である。ここ数年、国内でも女性アスリートのサポート体制が強化されつつある。慶應義塾体育会の女子部員も年々増加しており、スポーツ医学研究センターでも、多くの部のご協力のもと、医学部整形外科と協働の疲労骨折の調査、女子部員向けの基礎講座、「体育会女子部員 健康と生活のアンケート調査」等を実施した。潜在的に女子特有の悩みを抱えている部員も少なくなく、まずは気軽に相談に来れる窓口が大学の中に必要であり、女子アスリートサポート窓口を2018年夏より開設した。規模は小さいが、内科医師、保健師をはじめ、スポーツ医学研究センターの女性スタッフが相談に乗り、必要に応じて、婦人科・整形外科・精神神経科といった専門性の高いドクターや管理栄養士・アスレチックトレーナー等とも連携して、問題の解決を支援している。
女性アスリート特有の健康障害と思春期の問題
女性アスリートの三主徴というものがある。1993年アメリカスポーツ医学会での発表当初は摂食障害、無月経、骨粗鬆症の三主徴であったが、必ずしも摂食障害でなくとも無月経や骨粗鬆症のリスクが高まることがわかり、2007年、利用可能なエネルギー不足、視床下部性無月経、骨粗鬆症の3つと再定義された。発端にあるのは、利用可能なエネルギー不足、すなわち、消費エネルギーに見合う摂取エネルギーがとれていない状況である。図1のように、健康な状態では、摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスがとれており、月経も正常、最適な骨量を保っている。利用可能なエネルギー不足の状況が続くと、月経不順、低骨量を招き、さらに、視床下部性無月経や骨粗鬆症が深刻化していく。
月経不順の時点でいかに利用可能エネルギー不足を改善できるかが無月経を予防するうえで重要なポイントとなる。無月経が長引けば将来の妊孕性(妊娠のしやすさ)にも影響を及ぼす。また、骨密度はエストロゲンの影響を強く受ける。通常エストロゲンの分泌が急激に増える12〜14歳に骨密度が急激に高くなる。骨量は、その後、20歳で最大値となり、閉経を迎える50歳前後から急激に低下する。人生100年時代、10代でしっかり骨量を確保することは後々の骨粗鬆症予防のためにも非常に重要である。
コンディションに影響を与える女性特有の問題としては、月経困難症(月経痛で日常生活に支障をきたすこと)、月経前症候群(月経前3〜10日の黄体期の間続く精神的、身体的症状で、月経発来とともに減退ないし消失するもの、Premenopausal Syndrome, PMS)等、過多月経もあり、月経に伴う周期的な体調の変化を上手にコントロールする必要がある。時に低用量ピルの適切な使用など、婦人科医の助けも必要だ。
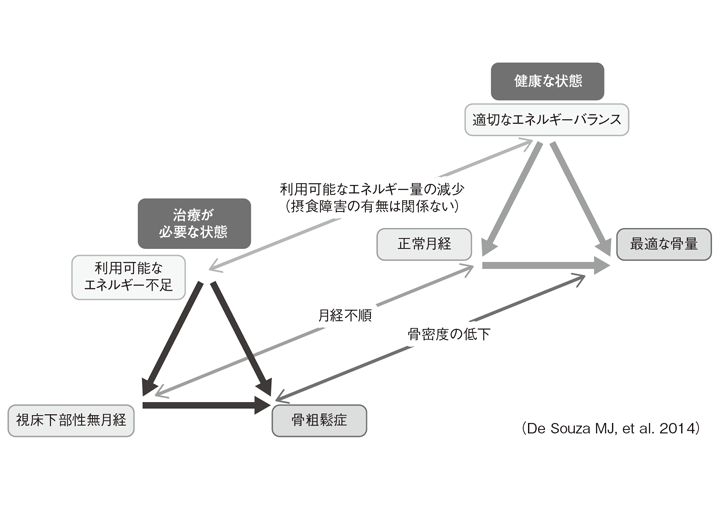
2020年3月号
【特集:青少年とスポーツ】
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

小熊 祐子(おぐま ゆうこ)
慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・大学院健康マネジメント研究科准教授