【福澤諭吉をめぐる人々】
増田宋太郎
2025/04/10
増田宋太郎にうかがわる
明治3(1870)年秋、母・順と姪の一(いち)を東京へ迎えるため、福澤は中津に滞在した。滞在中、福澤は増田を幼子と思って昔と変わらず可愛がり、増田は笑顔で接して家に出入りしたが、その内実は福澤のことを「西洋かぶれ」と思い嫌っていて、福澤家への出入りは偵察のためであったという。増田は福澤家に忍び込み、暗殺の機会をうかがっていたが、福澤は親類でもある上士の服部五郎兵衛(ごろべえ)と一晩中飲み明かしていたため、増田は機を逃し、福澤は九死に一生を得た。
その後、福澤は諸々の始末を終えて、船便で東京に戻ることとなった。福澤一行は、船が出発する近隣の宇島港(現在の福岡県豊前市)に前泊したが、宿に尊皇攘夷の思想をもつ人物がおり、増田ら道生館一派に福澤の動向を伝えたため、彼らは再び福澤の暗殺を計画したのである。道生館一派は金谷(岩田茂穂等下士が多く居住した地区)に集まり、暗殺計画を相談したが、誰が先陣を切るかどうかで大喧嘩となった。その声を聞いた中西与太夫という老人に窘められ、中西も含めて揉めている間に夜が明け、福澤は無事に神戸へ出発することができたという。この中西は中西一刀流という剣術指南の家系の出身であり、血気盛んな攘夷志士を止めることができたことも福澤にとっては幸運であった。
明治2〜3年頃に増田が重石丸にあてた書簡では、島津祐太郎ら藩政の中枢にいる上士が福澤に同調して洋学教育を推進する一方で、国学に対しては何ら支援がない状況に関する憤りが記されていた。また、藩主・奥平昌邁を誑(たぶら)かして米国に留学させるのでは、といった風説もあり、増田らの福澤に対する嫌悪感が強まっていた。明治3年の滞在中、福澤は「中津留別之書」を記して故郷の人々に近代社会の思想を啓蒙しようとしたが、福澤の思惑とは逆行して、まだまだ中津は福澤の思想を受容する状況にはなかったと言える。福澤はこうした暗殺計画を知らずにいたが、数年後に耳にし、自分が命拾いをしたことを知り、恐怖したことも語っている。
福澤への反発
明治初期の増田は、京都への遊学、中津にて道生館の後継とも言える皇学校を設立し、慶應義塾へ入学、結婚、討薩計画と様々な活動を行った。明治5年には、妻・鹿の兄である水島均(別名・六兵衛。中津藩下士で、奥平壱岐が失脚した文久亥年の建白書事件で中心的役割を果たした)と共に上京した。均の息子・鉄也(神戸高等商業学校初代校長を務めた)は、増田から「この日本という国は極く小さな国であるから我々国民は心身共に確(し)つかりしなければならぬ」と何度も聞かされ、道中でも均と増田は議論を交わしていたという。
『水島鉄也先生伝』(愛庵会編)では、上京途中で立ち寄った下関で増田が断髪し、均が「お前が断髪したと聞いたらあの男は何と言ふぢゃろうな」と福澤の反応について増田に問うと、増田は断じて福澤に屈服したわけではないと反論したエピソードを紹介している。その後、増田と均は福澤が中津に持ち込んだ新しい時代の思想について話し、増田は福澤の思想は承服し難いが、海防や外交、国のためを考えるのであれば、新しい思潮を学ぶことは必要だと考えを述べたという。
自由民権運動から西南戦争へ
討薩計画が露見し蟄居を命じられたのち、明治7年に増田は共憂社を結成し、自由民権運動を開始した。共憂社の主要な社員は道生館で共に学んだ学友であり、中津の尊皇攘夷志士の多くは増田と共に自由民権運動家へと転身した。土佐・立志社から林有造が中津へ派遣され、共憂社の結社を祝ったという。共憂社員は、福澤家菩提寺であった明蓮寺や中津市学校で演説会を開き、熱心に活動した。増田は明治9年には再び慶應義塾に入学、福澤のもとで学んだ。のちに、立志社の教育機関・立志学舎には、中津出身の塾員であり中津市学校の教員も務めた永田一二が教員として派遣されるが、こうした中津・慶應義塾・立志社の交流の発端は、共憂社であった。
同じく明治9年11月には、後に玖珠郡長を務めた村上田長が社長を、増田が編集長を務める田舎新聞社より、田舎新聞第1号が発刊した。この新聞社は中津市学校の基金を用いたもので、山口半七など自由民権論を唱える諸氏が中心となって運営にあたった。しかし、その数カ月後、増田は中津隊を結成して西南戦争に参加。明治10年9月には戦死した。
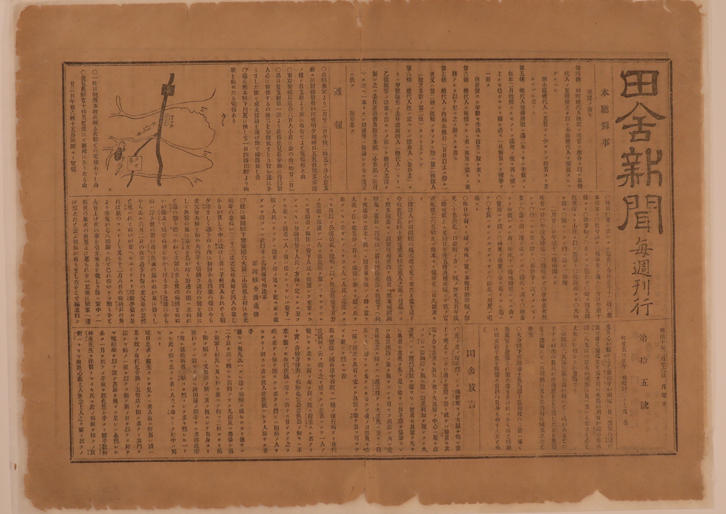
増田宋太郎とは
明治期の増田の活動は多方面に及び、その思想を捉えることは難しい。しかし、増田は尊皇攘夷運動から西南戦争に至るまで、一貫して国の独立と海防の重要性を唱えていたことは注目に値する。明治6年に計画した討薩計画での増田の主張は、「外交の不振を憂い、外海を防ぎ、大いに国権を振起するためには、まず内憂をのぞくべきとし、薩州のなお甚しく封建の余態を存し、傲然他県と隔絶して毫も協力の状がないことは甚だ歎しいこと」であり、薩摩の独歩が国内の足並みを乱すことを懸念したことが理由であった。
のちに西南戦争に与する際は、外患への憂慮と外交・財政面での明治政府の失政を糾弾し、専制政治を非難する檄文を作成した。増田の周囲には福澤、重石丸という異なる思想家・教育者がおり、互いに影響を与えていたことを考えると、増田は終生一貫した愛国思想を持っていたが、その実現手段については福澤等の思想を吸収しながら試行錯誤していたとは考えられないだろうか。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |
