【福澤諭吉をめぐる人々】
奥平壱岐
2024/12/18
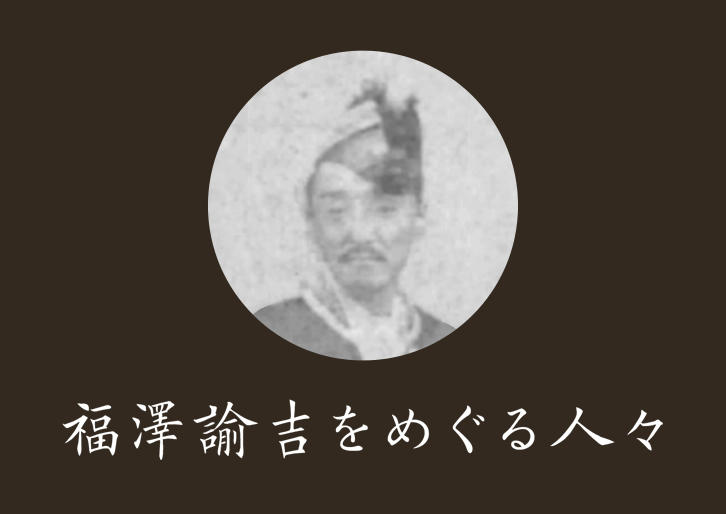
「奥平と云う人は決して深い巧みのある悪人ではない。唯大家(たいけ)の我儘なお坊さんで智恵がない度量がない」(『福翁自伝』、以下『自伝』)
奥平壱岐(おくだいらいき)と言えば、『自伝』の中でも印象深い描かれ方をした人物の1人である。なぜならば、長崎で蘭学修業に励む福澤の成長を「ヤッカミ出し」、「母の病気」という「鄙劣(ひれつ)千万な、計略を運(めぐ)らして」、福澤を長崎から追い出そうとした人物であるからだ。なぜ福澤はこのような壱岐像を後世に残したのだろうか。『自伝』では壱岐を「漢学者の才子」と評価しながら、「局量が狭い」、「猿松」、「大家の我儘なお坊さん」、「智恵がない度量がない」とこき下ろしつつ、最後には「実を申せば壱岐よりも私の方が却て罪が深いようだ」と複雑な感情を見せている。『自伝』を丁寧に読み進めた読者の中には、福澤が描く壱岐像に違和感を覚えた方もいるのではないか。
『三田評論』では、939号(1992年)で、「福澤諭吉と奥平壱岐」と題し、故河北展生名誉教授、長谷山彰前塾長、中金正衡(なかがねまさひら)(奥平壱岐)の曾孫である故中金武彦氏のてい談が掲載されている。記事の中で語られる壱岐は、豊かな教養の持ち主で、福澤の思想に影響を受けた進歩的な考えを持つ人物である。また維新後には慶應関係者との関係はそれほど悪くなかったと締めくくられている。福澤が伝えたかった本当の壱岐像とはどんな姿か。改めて見直したい。
中津藩家老 奥平壱岐
壱岐は、祖父正名、父正韶(まさあき)も家老を務めた中津藩大身衆、家禄700石の中金奥平家に生まれた。母千世は、後述の『系図書』に「長崎光永寺日蔵女」とある。福澤はその縁に乗っかる形で長崎遊学をスタートさせるのである。
壱岐の生涯をたどる史料は数少ない。実際、出生年については明確な記録はない。前述の中金氏によると、中金家に伝わる壱岐の日記『適薩俗記』、奥平の『系図書』および『覚書』、それに加えて中津藩の大身衆(最も家格の高い11家)の山崎家が残した記録『御用所日記』、壱岐と縁のあった勝の『海舟日記』から、壱岐の足取りをある程度つかむことができる。河北氏はこれらをもとに壱岐の動静を『「福翁自傳」の研究 注釈編』にまとめた。
壱岐は長崎での遊学を終えた後、孝明天皇の即位祝いの使者などの公務を果たすなどして、家督を継いで28年目の1857(安政4)年にようやく家老職に就き、1861(文久元)年には江戸詰めの家老となった。この頃から「壱岐」の名を使い始めている。
亥年(文久三年)の建白事件
そして1863(文久3)年、中津藩と壱岐の人生を揺るがす大事件、亥年の建白事件(文久騒動)が起こる。事は同年に、伊予・宇和島の藩主伊達宗城(むねなり)の三男、義(儀)三郎(当時9歳)を江戸家老だった壱岐が中心となって、中津藩主昌服(まさもと)の養子として迎える動きを見せたことに端を発する。これに対し、攘夷論が高まっていた下士間で、洋学派・開国派である壱岐への不満が爆発、壱岐が藩主の交代を謀り、さらに次代藩主に自身の娘を嫁がせようとしているなど、藩を私物化せんと計略を図っていると国家老の奥平図書に建白書を叩きつけたのであった。建白書では、壱岐は「偏頗(へんぱ)私論」「佞奸(ねいかん)」「種々奸曲(かんきょく)」「姦計(かんけい)」などと強い表現で糾弾されている。この建白書を受けて、将軍警護のため藩主昌服とともに京都にいた壱岐は急遽江戸に戻ることになった。
結論を言えば、壱岐はこの建白書を受けて家老職を外れることとなり、禄200石を削られるという処分を受けている。一方、壱岐糾弾の首謀者であった中津藩士水島六兵衛ら15名は「禄各二石ヲ削リ勤メ役ノモノハ更ニ之ヲ免ス」という処分を下された。『適薩俗記』の初めの一節に「慶應元年乙丑歳有故辞禄」と残されているが、この事件が「故」に壱岐が脱藩を決意したことは間違いないだろう。建白書の内容や藩の処分は、壱岐やその家族の中津での居場所を奪っただけでなく、壱岐の妻が「之を恥じ独自ラ屠(と)腹」するという悲劇を生んだことが中金家に伝わっている。
「門閥制度は親の敵」である福澤にとって、この「古来未曾有の大事件」は大いに議論すべきものに見える。しかし、これを取り上げた『旧藩情』では淡々述べられているようにみえる。文中では「上士の気風は少しく退却の痕を顕わし、下士の力は漸く進歩の道に在り」とした上で、「一定不変」の階級社会を揺るがしたと事件を位置付けている。一方で「当時執権の家老」と壱岐の名を出さず、藩の処分についても「姑息の策に出で、その執政を黜(しりぞ)けて一時の人心を慰めたり」と、上士である壱岐に同情的だ。さらにこの事件については『自伝』で一切触れていない。福澤がその事情を詳しく知っていたことを考えると、『自伝』の中で言及していてもよいようにも思う。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

川内 聡(かわうち さとし)
慶應義塾中等部教諭