【福澤諭吉をめぐる人々】
アーサー・メイ・ナップ
2025/01/14
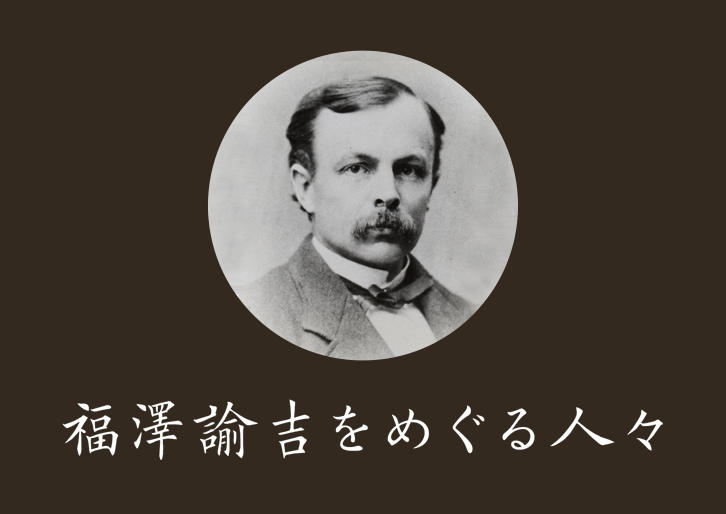
慶應義塾(とりわけ大学部)の基盤をつくるにあたって、米国ユニテリアン派宣教師であるアーサー・メイ・ナップ(Arthur May Knapp 1841-1921)が果たした役割は、塾史のなかでもっと強調されてもよいであろう。福澤諭吉(1835-1901)と同時代を生き、福澤本人のみならず、その息子たちとも深い交流があった人として、注目されるべき人物の1人である。ナップは1841年マサチューセッツ州チャールズタウンに生まれた。1860年にハーバード大学を卒業後、南北戦争では北軍の兵卒として従軍した。戦後、ハーバード大学神学部を1867年に卒業している。
ナップ来日前史
福澤はもとはと言えば、キリスト教排撃論者であった。しかし、1884年6月の『時事新報』社説に「宗教も亦(また)西洋風に従はざるを得ず」というコメントを出し、キリスト教容認の態度を示した。しかし同時に、正統派キリスト教の不寛容さには反発を覚えていた。福澤がナップをはじめユニテリアンたちに好意的な態度を示した背景には、彼らが日本の宗教・文化に対する寛容な精神と姿勢を持ち合わせていたということがあった。
さて、ナップの来日に大きな役割を果たしたのが、福澤の門下生である矢野文雄(龍渓)である。矢野はユニテリアニズムを日本の国教にするよう提案し、まず英国ユニテリアン協会に対して、日本へ宣教師を派遣してほしいとの要請を行った。だが同協会は経済的理由により断念し、米国ユニテリアン協会に協力を求めた。その結果、1887年、米国ユニテリアン協会より日本の宗教事情視察にナップが派遣されることになった。矢野の動きがなければ、ナップと日本、福澤との出会いはなかっただろう。
ナップの日本派遣前のタイミングは、ちょうど福澤の2人の息子たちのアメリカ留学と時期が重なっており、この2人は出国前のナップに対する援助に重要な役割を果たした。福澤の長男・一太郎(満23歳)はボストンを散歩していたときに、たまたまナップと出会い、ナップの家に2カ月程度滞在して日本事情や言語について教え、さらに父諭吉に対しナップの日本語教師の斡旋も依頼している。次男・捨次郎(満21歳)は、1887年11月にボストンにて行われたナップの壮行会で応援演説を行った。その中で、捨次郎はこれまでの正統派キリスト教宣教師たちの不寛容な姿勢を批判し、ナップの日本渡航を応援した。同年12月16日の『時事新報』に掲載された捨次郎の英語演説の翻訳を見てみよう。
我本国の日本人は玆(ここ)に始めて真誠自由の耶蘇(やそ)教家なるものは果して如何なる人物なるかを見るの機会に遭遇し、而して君が従来半固まりの宣教師とは大いに異なる所のものあるを見ることならん。(清岡暎一(編集・翻訳)・中山一義(監修)『慶應義塾大学部の誕生─ハーバード大学よりの新資料』より。注:「君」とはナップのことを指す)
このようにユニテリアンは異教文化に理解があり、ナップはこれまでの宣教師とは一線を画すとして、ナップの日本渡航を歓迎した。
ナップ初来日
1887年11月30日にサンフランシスコをベルジック号に乗って出発したナップは、12月21日に妻子とともに横浜港に到着した。ナップからジョージ・フォックス(米国ユニテリアン協会副幹事)に宛てた書簡(1888年1月7日付)には、到着直後のことが詳細に記されている。到着数日後には福澤自身が馬車で迎えにきて、ナップを家まで案内し歓迎した。また、同書簡には、福澤と会った時の印象について次のように書かれている。
Mr. F. is a large man with strong homely features, the pleasantest voice you ever heard, and expression of simplicity and genuineness which reminds me very much of Emerson. Everyone here speaks of him as the leader of the Japanese people in thought and in life.
[福澤氏は大柄で、強いながら質朴な顔の人で、およそ聞いたことのない気持ちよい声をし、エマソンを思わせる簡潔純粋な表情を持っている。当地の誰もが、彼のことを思想においても生活においても日本国民の指導者であると話してくれた。](清岡編、同前。注:エマソンとは超絶主義思想家のラルフ・ウォルドー・エマソンのこと)
これを読めば、ナップの福澤に対する第一印象はかなり良かったことがわかるだろう。既に日本の先導者であるということも認識している。一方ナップに対して福澤は、滞在中、慶應義塾にて講演したり、『時事新報』へ寄稿したりする機会を提供するなど、援助は手厚かった。ナップが赴任して1年ほど経った1888年11月には、一太郎と捨次郎は米国留学から帰国しており、日本国内においてもナップをサポートしていた。
1889年2月までには、福澤はナップに対して、慶應義塾大学部を設立するにあたり、法律学、経済学・社会学、英文学を教える3人の教師の選任を委ね、可能ならばハーバード卒業生から選んでほしいと伝えている。このことを受け、ナップは1889年2月に米国ユニテリアン協会ならびにハーバード大学総長チャールズ・エリオット(1834-1926)に対して、相次いで書簡を送っている。
ナップからエリオットに送った書簡では、ナップ自身がアメリカに一時帰国するまでに、エリオットに候補を選定しておいてほしいと頼んでいることがわかる。また、ナップから米国ユニテリアン協会副幹事フォックスに2月6日付で送った書簡を見ると慶應義塾のことを次のように表現している。
… the Keiogijiku or Fukuzawa College with its 1300 students is second only to the Imperial University, and possesses many elements of strength not enjoyed by the latter. Its friends have recently contributed a large sum to endow three new professorships of the highest rank.
[1300人の学生を持つ慶應義塾または福澤塾は帝国大学に次ぐものであり、後者にない多くの強い要素を持つ。その後援者達は近頃、大学部を新設して教授の最高地位を3つ設けるために多額の基金の寄付をした。](清岡編、同前)
ナップは福澤との会談を通じて、慶應義塾の強みを十分に理解している様子がわかる。
福澤はナップ帰国前の1889年4月にエリオットに宛てた書簡の中で、アメリカの最高学府であるハーバードと慶應義塾の間に密接な関係を構築したいと考え、これに関してナップとエリオットで話し合ってほしいと述べている。同書簡を読むと、慶應義塾の教授陣をハーバードの卒業生で埋められないかどうか、そして科目・教授法・試験法もハーバードに近づけ、義塾をa Japanese branch of Harvard University [ハーバードの日本分校](清岡編、同前)のようなものにできないかどうかとまで福澤は考えていたようである。さらには、塾生のなかでハーバード留学を希望する者のために、奨学基金をつくることに協力してほしいとも述べている。
こうして約1年半の視察を終えたナップは、第64回米国ユニテリアン協会年次総会に出席し日本視察の報告をするために、同年5月3日、日本を発ち一時帰国することになる。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

佐々木 貴久(ささき たかひさ)
慶應義塾高等学校教諭