【その他】
【講演録】子どもを育む遺伝の力、環境の力
2020/04/14
環境の力
教育環境は父性的
冒頭でお話しした胎児環境の他にも、家庭環境、育児環境、学校環境、社会環境などさまざまな環境があります。中でも教育環境は、「父性」的だなと感じます。これは私なりの考えですが、父性の特徴は、世の中の平均的な考え方や標準、ルールなどのデータに基づいて計画的に行動する力です。「よく考えてみろよ」「だいたい社会においては……」などなど。そして、教育には「こういう人を育てたい」という目標、アウトカムが必要です。目標を設定し、多くのデータに基づいて、標準的なアプローチを踏まえながら、効率的にさまざまなことを経験させてみる。これは、母性ではなく父性的な考え方に近いと私は思います。
ちなみに母性はもっと直感的です。正しいか否かよりも、それでいいと感じたかどうかに判断をゆだねる傾向があります。「だって見てごらん」「この子だってそう言ってるし」であっさりと決断します。もちろん、教育の場でも、母性と父性のバランスが重要であることは当然です。
ここで、必ずしも母性=女性、父性=男性というわけではない、ということを強調させていただきます。ある女性はふだん9割が母性で、1割が父性だとして、出産、育児を経て母性が倍に、でも父性はそのままとして全体で190%まで上昇。その後、仕事に復帰すると父性が増加して、部長に昇格すると父性50%、全体でなんと240%へ。男性も同じで、仕事一筋だったご主人が、お子さんを授かったことをきっかけに母性が大きくなるのではないかと思います。女性も男性も、人生の色々な場面で母性と父性を使い分け、自分自身を育んでいけるのではないでしょうか。
教育の力は平等である
さて、皆さんは「ディスレクシア」という病名をご存じでしょうか。学習の困難さの一種で、努力家だし勉強はできるはずなのに読み書きだけが苦手。この困難さは、ほぼ遺伝子の力によって決まっています。そのため、一生懸命勉強しているし、他の科目はできるけれども、国語の音読がからきしダメ。また、学校生活ではさほど問題にならない程度でも、読むのが得意ではない人はさらに多くいます。実は私も、論文を読むのが大嫌いです。でも、論文を読んだ人から話を聞くと、耳からは頭にスッと入るのです。
ここで、図表3を見てください。このグラフは横軸が子どもの年齢で6歳から16歳、小・中学校の時期にあたります。縦軸は文章を読む能力です。上側の曲線、読み書きが得意な子をA君、下側の破線、読み書きが苦手な子をB君としましょう。まず読み書きの得意なA君を見ると、小学校時代にぐんぐん伸びていきます。ただし、中学校に入ると横ばいですね。小学校でたくさん音読をするのは確かに重要だということが分かります。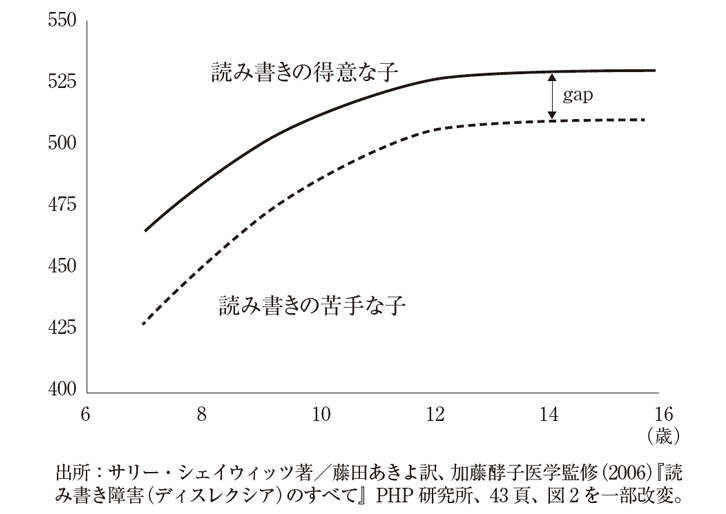
図表3 遺伝の壁と教育の効果
一方、B君はと言えば、小学校で頑張ったものの、どうしてもA君に追いつけず、その後も差を詰めることはできません。読む能力については遺伝的に決まる要素が強いので、努力しても追いつけない壁があるという結論に達します。
しかし、小学校6年間を見ると、A君もB君も点数の上がり方はほぼ同じ、つまり教育効果は同じだということに気付きます。驚きですね。生まれつきの得意不得意であり、越えることのできない壁はあるにせよ、教育は両者に同様の効果をもたらします。ある時期に何かを懸命に頑張るということは、決して無駄ではないのです。子どもの頃の「お家で3回音読して、お母さんにサインをもらいなさい」という宿題は、なんと意味があったことか。私はこの年になってやっと合点がいきました。これが教育の力なのだと。
さらに近年、アメリカではこのギャップを乗り越えるトレーニングが開発されつつあります。将来、科学がもっと進歩すれば、少なくとも読み書き程度のことなら、遺伝的な壁を訓練、つまり教育という環境の力によって乗り越えられる可能性が出てきたということです。
環境の力で遺伝子の壁を乗り越える
ここで、慶應病院に通院している赤ちゃんのお話をさせてください。脊髄性筋萎縮症という遺伝子の異常によって起こる病気の赤ちゃんに、いわゆる遺伝子治療を施しています。背中に針を刺して、髄液の中に薬を注入するのですが、それを数カ月ごとに繰り返すことで、早晩亡くなっていたはずのお子さんの命が助かるばかりか、歩くことも夢ではなくなったのです。これは驚異的な薬で、ただもう「科学という環境の力」の勝利と言うほかはありません。お父さん、お母さんにとって「歩けることなく死ぬ」と思っていた子がニコニコしながら歩き出すという、信じがたい現象が起こるわけです。
さらに、ご両親の経済的負担なしで治療を受けられるという点では、医療保険制度すなわち「社会という環境の力」の勝利でもあります。なぜなら、この薬は1本1千万円もするのです。さらに、同じ病気に対して静脈注射を1回打つだけで一生治療をする必要のない薬も開発されました。1人の命を助け、長い幸せな人生をプレゼントする薬です。この薬は2億円以上しますが、やはり医療保険制度の対象です。
私がここでお伝えしたかったのは、絶対に治らないと思われていた遺伝子の病気ですら治す時代に入ったという事実、つまり「科学という環境の力」の頼もしさ、そして、ひとりの子どもの命を助け、そのご家族の幸せを守るためには2億円出してもよいと、日本という国が考えているという事実、つまり「社会という環境の力」の寛大さです。
環境が持つ負の力
環境には負の側面もあります。現在、インターネットやスマホが普及し、子どもたちがSNSやネットゲームにハマってしまうことが大きな社会問題になっています。こうしたメディア環境の何が悪いのでしょうか。私は、3つに集約されると思います。1つ目は、会話がなくなる「無言化」。2つ目が、1人でいる時間が長くなる「孤立化」。そして3つ目が「実体験の減少」。
皆さん、無言化と孤立化はお分かりだと思います。例えば、お母さんと中学生の息子が夕食を食べています。子どもは右手に箸を、左手にはスマホ。お母さんは、「学校はどうだった?」なんて会話をしたいのですが、ご自身もテーブルの脇にスマホを置いています。すると、ブーブーとスマホが震えます。「お父さんかな、PTAかも」と見てみると、なんと目の前の息子からLINEです(笑)。どうしましょう。おそらく、お母さんは開きますね。そうしたら、「今日のカボチャ、メチャうま」(笑)。お母さん、嬉しくなってLINEで返信です。「これ、栗カボチャっていって、今が旬なのよ」なんて。無言化の良い例です。
さて、最も大きな問題は、「実体験の減少」です。冒頭でお話ししたように、環境がその力を発揮するには、その環境を実際に体験する必要があります。例えば、保育園でお友だちの顔を引っ掻いたら、お友だちが泣き出した。先生に怒られて、悲しくなって涙がこぼれた。そして翌日、お母さんが呼ばれて、保育園の先生に謝って、お母さんも泣いている……。こんな実体験が非常に重要なのです。「人を傷つけてはいけません」という言葉だけではダメです。人を殴ったらどういうことになるのかを、我が身に染みて体験することが大切なのです。重大な事故は避けるべきですが、私たちは小さな失敗という実体験を積み重ねて、環境の恩恵に浴するのです。
そして帰り道、お母さんが温かい手をつないでくれる。「もうしないね」と約束する。紅葉がきれいで、ちょっと冷たい風が吹いて、とっても気持ちよかった。これが実体験です。そうした経験が、自分の中に取り込まれ、つまり内在化し、結果として想像力が育まれます。そうすれば、初めて直面する問題に対しても解決策を子どもなりに見出すようになります。「こんなことしてはダメだ」と判断する原動力は多くの場合、「こんなことをしたら、お母さんが悲しむ」、あるいは「お父さんに叱られる」と想像する力なのです。
また、「こんなことをしたら、きっと喜んでもらえるぞ」と他人の心に期待する力も実体験によって育まれます。あるいは、「こんなことを言ったら、きっと悲しむな。言わないでおこう」と、想像力だけで、相手が傷つくことを事前に察知できるようにもなります。
多くの実体験に基づいて想像力が育まれていれば、バーチャルリアリティも意味のあるものになるでしょう。しかし、実体験を疎(おろそ)かにして、ありもしないことを体験したかのように錯覚させるのは、少なくとも子どもたちにとっては危険なことです。対戦型ネットゲームを通じて、人は殺しても生き返る、相手を殴ると点数がもらえる、といったとんでもない❝体験❞が内在化してしまいかねません。
母性の欠如がもたらす劣悪な育児環境
母性が欠如した劣悪な家庭環境や、健全とは言えない入院生活の中で、遺伝子の力はどのように負の環境と闘い、子どもたちを守っているのでしょうか。私たちの病院に入院していたある男の子のお話を通じて、一緒に考えてみたいと思います。
その子は、3歳頃から背が伸びず、さらに4歳を過ぎて病院に連れて来られた時、体重は2歳児程度しかありませんでした。病名は愛情遮断症候群。原因は母性の欠如です。
食事は与えられ、家もあるし、寝床もある。お父さんはいません。しかし、お母さんは、その子が自分の子どもだという実感が湧かない。頭では分かっているのに、どうしても愛することができない。この子、何か様子がおかしい。一切、笑わない。考えようによっては、このお母さんは偉かった。よくぞ、病院に連れて来たと思います。
まず私たちがやったことは母子分離、お母さんと子どもを引き離すという治療です。子どもは入院させて面会謝絶、お母さんは外来で医師の治療を受けます。お母さんは一向によくなりませんでした。一方、男の子は、最初は目も合わせてくれなかったのですが、対人関係は徐々に改善し、身長・体重ともにグッと増えていきました。
その間、私たちがしたことは、3食、横に看護師さんか若い小児科医がついて「美味しそうだな」とか「お友だちのベッドで遊んじゃだめだって言ったろ」とか、そんな会話をするだけです。というのも、この子は退屈して、他の子のベッドに行って遊ぶわけです。しかし、感染症対策のために、患者さんが他のベッドに上がり込むことは禁止されているのです。
さて、同じ部屋に、あるお姉さんが入院してきました。お姉さんは女の子らしく母性豊かで優しい。「オセロやる?」と遊んでくれる。楽しくてしかたがないから、また行く。お姉さん「また来たの。ちゃんと、ご飯食べてるかな?」。でも、しばらくすると「今はあっち行って!」「もう、来ないで!」と。じきにお姉さんは髪の毛が抜け、顔面蒼白になり、点滴につながれながら吐き続ける。白血病で入院してきたのですから、いつまでも元気なわけがないのです。これが病院というところです。
また、窓際のベッドには、小学校1年生に上がったばかりの男の子がいました。心臓の大動脈弁膜症で、手術をしなければ余命1年ほどと診断されていました。高度心不全です。一方で、心筋梗塞の既往(きおう)があったので、手術室からそのまま戻ってこられない確率が数%。手術の後、1年を待たずに命を落とす確率が20〜30%という状態でした。その子は「手術は絶対にいやだ」と泣き叫びました。なぜなら、それまでに心臓カテーテル検査や別の手術で何度も痛い目に遭っていて、集中治療室に1週間も2週間も閉じ込められる恐怖を知っているからです。
しかし、日本では15歳未満の子どもにイエス・ノーを決める権利はありません。両親が同意書に署名すれば、本人の意思とは無関係に手術が行われるのです。もちろん、それは子どもの命を考えてのことですし、ある意味で正しいことです。ただ、最近になって私は思うのですが、あの子ともっと話をしておけばよかった。あの子と同じ目線で、あのベッドサイドでもっと話をして、説得を重ねるべきだった。本当に反省し、後悔しています。
そのお兄さんは手術室から帰ってきませんでした。愛情遮断症候群で同じ部屋に入院していたあの子だって気付きますよね。「お兄ちゃん、帰ってこない。死んだんだ」と。あの仲良しだったお兄ちゃんが、そうやっていなくなるわけです。それでも、この子にとって一番辛かったのは、元気になり、お父さんやお母さんが迎えに来て退院していく子どもたちを見送る時です。そういう子たちをたくさん見送って、この子は1年以上、入院していました。我々はこの子に母性を与えることができていたのでしょうか。
劣悪な環境に立ち向かう親思いの遺伝子
その後、すっかり身長も体重も増え、元気に笑う❝普通の男の子❞になり、退院の時が来ました。では、どこへ? 彼は児童養護施設へ行きました。そこで新しい人生を始める。お母さんにも一切会わないまま、小学校の入学式の日も、施設から出かけました。ところが、学校の校門にお母さんが現れたのです。
母親を治療していた主治医が、そろそろ息子に会わせてもいい時期だと判断したのでした。数年ぶりに母親に会った男の子は、驚いたことに、こう話しかけたそうです。「お母さん、よかったね」。実は、男の子を退院させた時に主治医は言い訳をしました。「お母さんは重い病気なんだ。だから、君はまだお家に帰れない。お母さんが元気になるまでは、お友だちと一緒に暮らそう」と。男の子は納得して施設へ行ったのです。
お母さんが校門に現れた、ということは、お母さんの病気が治ったんだ。彼は瞬時にそう理解したのです。だから「お母さん、よかったね」。
皆さん、信じられますか。生まれて4年間、1度も愛されず、母性に触れることもなく、痩せこけて身長も伸びず、そのまま病院に預けられ、そして施設に預けられた。それでも彼は「お母さんは病気だ。今は我慢だ」「お母さん、元気になってほしい」と思って施設で暮らしていたのです。子が親を思う気持ちは、遺伝子の仕業としか思えません。体験に左右されない遺伝子の力に守られて、何があっても子どもは親を裏切らない。なるほど、と思いました。
私がそのような遺伝子の力を最も実感するのは、子どもが虐待の被害者になった時です。足の親指が青あざになって、爪が潰れている子。おそらく、ペンチで挟まれたのでしょう。また、頭を万力で締め上げられた子もいました。黒いビニール袋に入れられて、空気銃で撃たれた子もいました。しかし、これら虐待の被害者である子どもたちは、決して親がやったと口を割りません。ほとんど例外なく「自分でやった」と言い張ります。
殺される前に手紙を書かされた子がいましたね。「自分が悪かった、お父さんは悪くない」と。これは私の推測ですが、ああした手紙は、必ずしも強制されたものではないと思います。きっと洗脳されていたのでしょう。なぜなら、お父さん、お母さんが、自分にこんなことをするはずがないという本能のようなものがあるからです。きっと自分のせいだ、と思い込む。「おまえがいけない。お父さんはおまえを教育するためにやっているんだ」と言われれば、本当にそうだと思うんですね。子どもが親を思う気持ちは、遺伝子の力で守られていて、とても強い。その強くて温かい思いを、大人は決して逆手に取ってはならない。
遺伝の力さえ捻じ曲げる環境の力
一方、かくも強い遺伝の力でさえ、環境の力によって歪められてしまう場合があります。実は入院した時、この男の子の頭囲、すなわち脳は小さかったのです。入院後にグッと大きく成長しました。実は、これは不思議なことです。例えば、アフリカで飢餓に苦しむ子どもたちは、栄養失調で首から下はやせ細っていますが、頭の大きさは正常です。また、妊娠中に胎盤の機能が落ちて、胎児に届く栄養が不足しても、脳だけは正常な大きさで生まれてきます。どんな逆境でも、脳には一番栄養のある血液が流れるようにできているのです。
ところが、母性がない環境では脳が縮むのです。冒頭にお話ししたように、形が作られ、そこに正しい機能が宿る過程は遺伝子の力で守られています。しかし、愛情のない家庭環境が、それすらも捻じ曲げていたのです。少年の脳は、その後の病院生活の中でだんだんと育っていき、入学式の日に、「親思いの遺伝子」が満を持して花開き、「お母さん、よかったね」という言葉を吐かせたのだと思うのです。頭の大きさ、つまり、脳の大きさは、さまざまな物語を私たちに教えてくれました。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |
