【特集:デジタルアーカイブの展望】
福島 幸宏:デジタルアーカイブをめぐる素描
2024/11/05
あらゆるところに存在するデジタルアーカイブ
デジタルアーカイブ。みなさんはこの言葉に触れたことがあるでしょうか? 以前から関心を持ち、いまやそれを主要な研究対象としている私にとっては、世界中のコミュニティや地方政府、また大学や企業がデジタルアーカイブを構築し、運営しているように感じます(もちろんそれは大いなる錯覚であることは承知しています)。しかし、もしデジタルアーカイブという言葉に触れたことがない読者がいたとしても、デジタルアーカイブの構築数は年々増え続けています。そして、その有用性が理解されるようになってきました。
では、デジタルアーカイブとはなんでしょうか? ごく簡単に、そして乱暴に説明すれば、社会にあふれているデジタル情報のうち、長期間のアクセスと利活用を保障する仕組みで提供されている情報の一定のまとまりを、デジタルアーカイブと呼んで差し支えないと考えます。ここで、もってまわったような言い回しをしているのは、デジタルアーカイブに明確な定義は未だにない、と考えるからです。
デジタルアーカイブという言葉は、1990年代前半に、当時東京大学教授であった月尾嘉男を中心とするグループが作りだした和製英語です。海外では、digital cultural heritageと呼ばれているものとほぼ同義と考えます。この時期は、インターネット社会の到来を見据え、アメリカやEUがそれぞれの未来構想を打ち出していた段階でした。その中で、日本の世界戦略の一環として、世界の重要な文化遺産を当時最先端だった日本の技術力と豊富な資金によってデジタル化し保存していこう、という構想に与えられた言葉が、デジタルアーカイブ、ということになります。
現在、日本のデジタルアーカイブはジャパンサーチを起点にすると探しやすくなっています。このジャパンサーチは内閣府知的財産戦略推進事務局と国立国会図書館が運営している「我が国の幅広い分野のデジタルアーカイブと連携し、多様なコンテンツをまとめて検索・閲覧・活用できるプラットフォーム」とされています。ここでは、「図書館、博物館、美術館、公文書館、大学、研究機関、官庁、地方自治体等の機関が所蔵しているコンテンツを探すことができ」、それぞれのコンテンツのページに示されているライセンスに従い、利活用が可能となっています。
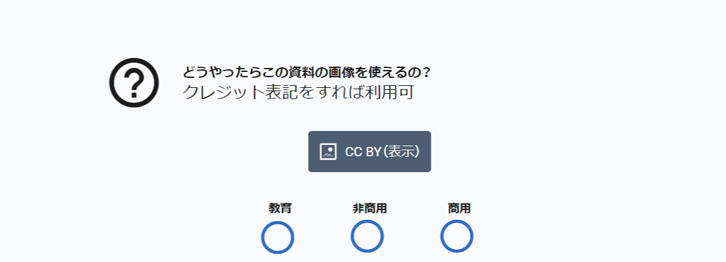
デジタルアーカイブの動向
現在のデジタルアーカイブの状況を検討するとき、大規模災害への備えという観点が重要なものとなっています。どこであっても、東日本大震災のような地域全体の被災の可能性があります。日常的にも火災や水害などで、いままで伝えられてきた資料が消滅するリスクは常にあります。失われた資料を取り戻すことは不可能であっても、デジタル化することによって、その情報のごく一部でも保存し、後世に伝えることは可能です。デジタルアーカイブの構築は、被災後の復興を見据えた防災対策でもあるのです。また、古文書や写真などの劣化しやすい資料をデジタル化することで、現物の閲覧による破損や劣化という資料にとって最大のリスクを軽減することできます。
デジタルアーカイブに関連して、近年注目されている分野の1つが人文情報学(Digital Humanities)です。人文情報学とは、従来の人文学分野に情報科学やデータ解析の手法を組み合わせる新しい人文学の潮流で、より高度な研究が可能になると期待されています。人文情報学の隆盛にともなって、その対象となるコンテンツを提供し、同時に成果公開のプラットフォームとなるデジタルアーカイブの重要性はより高まってきています。
都道府県や大学のみならず、各地の市町村でもデジタルアーカイブの構築と活用が進んでいます。たとえば、地域の歴史資料や文化財をデジタル化して公開する取り組みが各地で行われています。これは、地域の住民に自分たちの歴史や文化について気軽に触れてもらうだけでなく、文化観光や地域教育の資源としても活用されています。
デジタルアーカイブの浸透の結果、ついに閲覧室を持たない博物館が登場するまでになっています。千葉県の大網白里市は、博物館や資料館、美術館などの文化施設がない状況でした。そのため「いつでも・どこでも・無料で文化資源に親しんでいただくことのできる施策」として、「館を持たない自治体が提案する本格的デジタル博物館」をコンセプトに2018年から大網白里市デジタル博物館を公開しました。充実したコンテンツ整備、積極的な学校教育へのアプローチなどを特徴としたこの博物館活動は大きな反響を呼び、2024年3月には、博物館法上に位置付けられた登録博物館の認定を受けました。インターネットを中心に資料を公開している機関としては、全国初の事例となります。従来は、リアル空間に存在する図書館や博物館に収蔵されている資料をデジタル化することがデジタルアーカイブ構築の有力な手法でした。しかし、今後は資料や情報を、収集・保存・活用する、という博物館活動の根幹が護られれば、バーチャル上の博物館であっても、法的な位置付けを得られることになったのです。
デジタルアーカイブのコンテンツは誰のものか
デジタルアーカイブの普及に伴い、デジタルアーカイブに登載されているコンテンツは誰のものか、という問いが浮かび上がってきています。従来は、デジタル化された資料の所有者、もしくはデジタルコンテンツの作成者が、デジタルアーカイブに登載されているコンテンツに対して、その権利を専有するというのが自明のことでした。しかし、デジタルアーカイブは、この位置付けではものごとの整合が取れない段階に来ています。
その動向の背景にあるのは、著作権をはじめとする知的財産権についての理解の浸透です。所有権と著作権を峻別して考えることがデジタルアーカイブ関係者、博物館や図書館の関係者の常識となってきました。その上で、デジタルアーカイブ公開の際には、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスをはじめとする権利表記を同時に行うことも、当然の手続きとなってきています。この結果多くの場合、著作権上の問題がない資料については、そのコンテンツの利活用を大幅に認める方向に作用しています。
また、歴史学は主に専門家や学者によって進められてきましたが、デジタルアーカイブの登場により、市民も歴史の保存や研究により積極的に参加できるようになりました。クラウドソーシングにより行われているみんなで翻刻はその典型例です。くずし字で書かれている前近代の歴史資料を活用するため、文字を現代の活字に直し、データとして扱いやすくする作業(翻刻)を、専門家だけでなく、多くの参加者によって進めているプロジェクトです。この場合、多数の参加者が作成したテキストデータが成長し続けることになります。われわれは、資料が広く公開され、誰でもアクセスできるようになることで、様々な人々が関わって歴史学の共有の財産が日々成長している事態に立ち会っているのです。
これら動向は、現物資料の公共財化の過程と軌を一にしています。信仰や荘厳のための作品、正統性確保のための記録などは、リソースや権力が集中する場で作られ、権力のサークルのなかで引き継がれてきました。しかし、近代革命以降、王家や貴族の財産が解放されて博物館が成立し、また近代市民が互助のために公共図書館を運営するようになります。そうなると、現物資料のなかで、特に公共性が高いとみなされるものは、いま現在の所蔵者に関係なく、公共財として社会全体に拓かれることとなりました。文化財保護法はまさにこの精神に則しています。デジタルアーカイブにもようやくこの波が到達したと言えるかもしれません。
デジタルアーカイブは現代社会における重要な公共財の地位を獲得しつつあります。誰もが参加でき、かつ長期間のアクセスと利活用を保障する仕組みが存在することで、知の循環は促進され、新しいアイデアが連続的に生まれていきます。その構築と活用のサイクルをよりうまく回せるかどうか、この点こそが、社会の知識基盤の強化や持続可能性とダイレクトに繋がっていると考えます。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
2024年11月号
【特集:デジタルアーカイブの展望】
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

福島 幸宏(ふくしま ゆきひろ)
慶應義塾大学文学部図書館・情報学専攻准教授