【三人閑談】
塩の魅力
2023/01/25
-

-

杉本 雄(すぎもと ゆう)
帝国ホテル第14代東京料理長。武蔵野調理師専門学校を卒業後、1999年帝国ホテル東京入社。2004年に同社を退社し渡仏。17年に帝国ホテル東京再入社し、19年より現職。21年に「塩」を主役にしたレストラン企画「「塩」の世界」を開催。 -
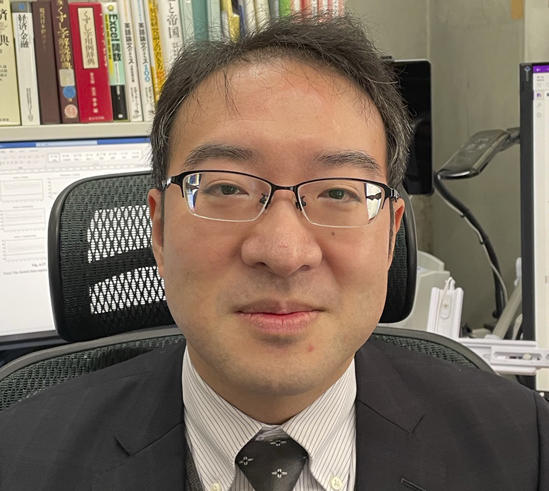
前田 廉孝(まえだ きよたか)
慶應義塾大学文学部准教授。2013年慶應義塾大学大学院経済学研究科後期博士課程単位取得退学。博士(経済学)慶應義塾大学。18年より現職。専門は近代日本経済史・経営史。著書に『塩と帝国―近代日本の市場・専売・植民地』。
塩の世界へ
前田 青山さんはソルトコーディネーターと伺いましたが、どのようなきっかけでこのお仕事に就かれたのですか?
青山 総合政策学部を卒業した後、食の世界に面白みを感じ、カゴメに入りました。商品開発などをやっていたのですが、ちょっと働き過ぎで若干体を壊したのをきっかけに、沖縄に移住をしまして、そこで沖縄のお塩に出会ったのが塩の世界に入るきっかけです。
それがもう19年前ぐらいのことですが、そこで塩の専門事業をやっている会社に転職をして、塩との付き合いが始まりました。2012年に一般社団法人日本ソルトコーディネーター協会という協会を立ち上げ、今年でちょうど10年になります。
前田 塩のどのようなところに魅力を感じられたのですか?
青山 いろいろなことをしていますが、例えば昨年、杉本さんと「塩の世界」というイベントでコラボさせていただいたように、料理と塩についての関係や、世界各地の塩の歴史、あとは美容の面といったところに面白みを感じています。
杉本 塩と料理はもう切っても切り離せないものですね。
私は子どもたちを対象にした食育の授業をする時にも、改めて塩の大切さをひしひしと感じています。子どもたちに旨味を感じてもらうために塩を使います。もちろん、われわれ料理人にとっても塩の使い方はとても重要です。世界各地で塩の歴史があって、それが料理の歴史と結びついている。その他にも塩があってこその発酵の技法が進歩したり、その土地で採れた食材との出会いが新たな料理を生み出して食文化に影響を与えたりと、本当に欠かせないものですね。
前田 私の専門は近代日本経済史・経営史、植民地経済史です。日本の植民地経済史研究では、戦前日本が台湾、朝鮮半島などに進出し、現地で何を引き起こしたのかということが主に議論されてきました。
もちろんその研究も重要ですが、私は近隣地域の植民地化によって宗主国の日本がどのように変わったのか、ということに関心があります。
特に、私は戦前日本における植民地の一次産品供給に着目しています。こうした一次産品の1つとして塩は、両大戦間期の内地における流通量の半分近くが植民地から輸入もしくは移入されていました。それゆえに、戦前日本の食塩市場を考える上で植民地の製塩業は欠かすことのできない存在でした。そこで、塩に関する歴史研究をやっています。
だから、今の塩の流行りなどにはまったく詳しくありません(笑)。
昔は嫌われた天日塩
青山 そのような視点から塩について考えたことはあまりなかったので、とても興味深いです。日本でももちろん昔から塩は作られていたわけで、日本全国で塩田や釜で塩を作っているところは大変な数がありましたよね。
しかし、1905年に日露戦争の戦費調達のため、それまで自由販売だった塩を大蔵省主税局の管理下におく「塩専売制度」が始まってからは、徐々に効率化という名の下に塩田はどんどん減っていってしまった。でもそれまでは、海なし県と呼ばれるような山梨などでも温泉水からの塩作りが行われているので、作っていない県の方が珍しいぐらいでしたよね。
前田 そうですね。
青山 私の知っているところでは、台湾の七股(チーグー)には日本軍が伝えた塩田が今でも残っています。あれも、日本が植民地支配をした時に海外で塩田を作って、それを流入させていたということですか。
前田 軍隊が台湾で塩を作っていたというより、もともとあった塩田を軍が利用したという話ではないかと思います。
台湾では、内地の入浜(いりはま)式塩田とは異なる天日(てんぴ)塩田で塩を作ります。その製法に起因し、台湾領有初期の文献を見ると天日塩はネズミ色の塊状であったそうです。それは白色粉末状の内地塩と異なる形状から「砂利塩」と呼ばれ、内地の消費者から嫌われていました。
例えば、第一次世界大戦期までは塩の用途別工業用消費量で最多を占めたのは醤油醸造用でしたが、醸造工程で塩は水に溶かして食塩水にしてから投入します。それゆえに、塊の塩だと溶けにくい。そこで、天日塩を嫌う醸造家も少なくありませんでした。
杉本 塩の作り方というのは天日塩と入浜式と大きく2つあるのですね。
青山 大きく言うと釜で煮るか煮ないかの違いです。太陽と風の力だけで最後まで結晶させたものが天日塩で、途中まで塩田を使っていても最後に釜で炊いたら煎熬(せんごう)塩になります。釜炊き塩とかいろいろな呼び方があるのですが、専門用語だと煎熬塩と分類されます。天日塩だと、前田さんがおっしゃったように下が土だったり砂利だったりするので、異物が入る可能性が高くなります。
でもお話を聞いていて面白いと思ったのが、当時は灰色の塩が砂利塩だといって敬遠されていたということですが、今だとフランスのゲランドの塩は灰色ですが、ブランド塩としてすごく人気が高いのです。時代が変わると変わるものですね。
杉本 そうですね。ゲランドの塩はミネラルが豊富で、食材が持つ本来の美味しさを引き出してくれますので、料理人からも評価されていると思います。今はスーパーなどでも見かけるようになりました。
青山 最近は消費者の間でナチュラル志向が強いんですね。ローフード(生で食べること)の流行りで、火を通さない食べ物を嗜好する傾向があります。その中で、塩も当然「煎熬」すると100度近くで炊くことになりますので、炊いていない天日塩がいいよね、という流れが強くなったと思います。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

青山 志穂(あおやま しほ)
一般社団法人 日本ソルトコーディネーター協会代表理事。1999年慶應義塾大学総合政策学部卒業。2012年一般社団法人日本ソルトコーディネーター協会を設立し独立。全国各地で、塩の魅力を広く伝えている。