【話題の人】
加藤真平:自動運転のためのOS開発を牽引する
2023/01/16

-
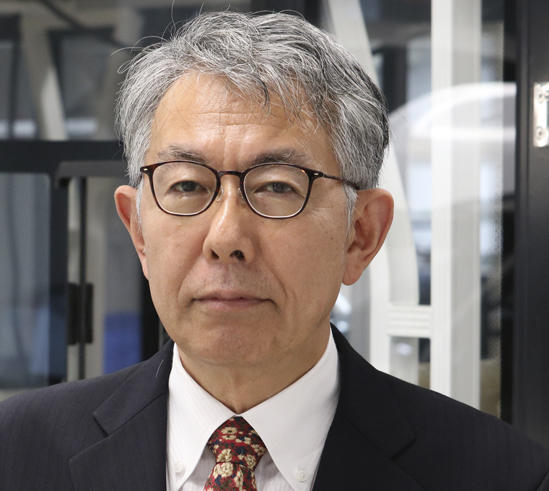
インタビュアー石川 裕(いしかわ ゆたか)
国立情報学研究所教授・塾員
自動運転のためのOSとは何か
──自動車の完全自動運転の実用化に期待が高まっています。自動運転のためのOS「オートウェア(Autoware)について聞かせてください。
加藤 自動運転は専門分野によって見え方が変わる世界です。一般の人には自動車の形を想像されると思いますが、コンピュータ・サイエンスの分野から見るとロボットに近く、私にとっては数多くのコンピュータとセンサーがあり、これらがネットワークでつながっているイメージです。自動車をつくっている感覚ではないですね。自動運転の技術においてソフトウェアの開発は重要部分を担っています。
ティアフォーではこれまでオートウェアの開発を主導してきましたが、OSと言う場合、それが指し示すものは意外と曖昧だと思います。例えば「Windows」はOfficeなどのソフトウェアも含めた総称です。オートウェアもこれに近いものですが、OSはあくまでプラットフォームであり、単体で使うものではありません。いろいろな人がこれにさまざまなものを載せ、テストしているのが現状です。
──コンピュータ・サイエンスの分野では自動運転のソフトウェアは究極のトータル技術でとても魅力的な分野です。
加藤 自動運転にはさまざまな専門家が関わっていますが、きっとそれぞれの分野の人たちが皆そう感じていると思います。そこには実にいろいろな視点が入り込んでいます。
僕の専門領域はコンピュータ・サイエンスですが、自動運転を実用化させるということは、ビジネス的な視点ではマイクロソフトのような会社をもう一つ立ち上げるほどのスケールです。一つ一つの技術にスペシャリストが関わりつつ、すべての分野が頭に入っていないとビジネスとしては成立しない難しい世界です。
──オートウェアの開発にあたって苦心された点を教えてください。
加藤 自動運転を実用化するにはOSにさまざまなものを付け足すことになります。OSだけをつくるのはコンピュータ・サイエンスの知識があればできるのですが、大変なのは何かを付け足す場合に他の分野とのインターフェースを整えるところです。そこで多くの専門家の声を取り入れるために、2018年にオートウェア・ファウンデーションという国際業界団体を立ち上げました。
国際業界団体で開発を進める
──現在はオートウェア・ファウンデーションがオートウェアの開発を手がけているのでしょうか。
加藤 オートウェアはプログラムの設計図となるソースコードを誰もが入手できるオープンソースという仕組みで開発を進めています。そのため、開発にはティアフォーの社員以外にも多くのエンジニアが関わります。オートウェア・ファウンデーションはオープンソースの開発を取り仕切る団体です。
ファウンデーションには、ティアフォー以外にも70を超える事業者や団体が参加しており、これらが開発の中心メンバーとなって意思決定しています。ティアフォーはその一メンバーです。僕は理事長を務めていますが、ファウンデーションには企業から団体や大学などの研究機関までさまざまな立場の人たちが参画しています。slackに加わるメンバーは3千から4千ほどにのぼり、ファウンデーションはこれをすべて取り仕切っています。
──何カ国くらいの企業が参加しているのでしょう?
加藤 20カ国ほどだと思います。このうち、実際にプログラムコードを書く作業に携わっているのは千人ぐらいでしょう。
オートウェアの開発は2013年に名古屋大学で始めたことでした。着手してすぐにあちこちから大きな反響が届き、2015年にティアフォーを創業しました。最初の2年ほどはティアフォーで運営していたのですが、オープンソースは一社に帰属していると真価を発揮しないとわかり、ファウンデーションを立ち上げました。業界団体が母体となれば、万が一、ティアフォーが撤退しても他の参加企業によって開発が継続される仕組みです。
──オープンソースにしたことで「自動運転技術の民主化」と言われることもあります。誰にとっての民主化でしょう。
加藤 直接的には開発者に開かれています。でも結果的にはユーザーも含めた全員ではないでしょうか。誰でも開発できることで、ほぼすべての人たちに自動運転が行き届くことになると考えています。技術を民主化することで多くの人がその恩恵を受けられる。これが最も価値が高い状態だと僕は考えています。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

加藤 真平(かとう しんぺい)
株式会社ティアフォー創業者兼最高技術責任者
塾員(2008 理工博)。自動運転のためのOS「Autoware」をオープンソース化し、開発を牽引。東京大学大学院情報理工学系研究科准教授も務める。