【話題の人】
林善博:「有機味噌」にこだわり 世界へ日本の味を届ける
2019/08/22

-
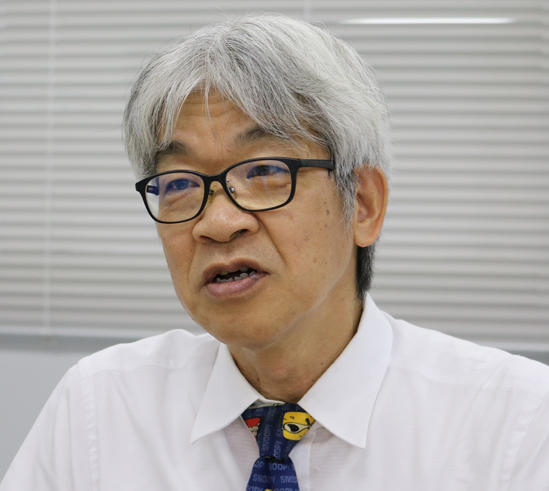
インタビュアー井奥 成彦(いおく しげひこ)
慶應義塾大学文学部教授
後発の会社として出発
──海外事業も好調で、無添加、有機の商品を中心に販売数量シェアで業界3位に躍進した「ひかり味噌」ですが、創業は昭和11(1936)年ということですね。
林 もともと曾祖父は今の新潟県の上越市出身の屋根葺き職人で味噌とは全く関係なかったんです。どうも諏訪大社の屋根葺きのために諏訪に来たようなんですね。
しかし屋根葺き職人は天気が悪い冬場は仕事がない。そこで、1年間稼げる商売はないかと、諏訪の同業から味噌を分けてもらって東京で売り歩いたところ、非常に売れたそうです。当時、すでに「信州味噌」というブランドが確立していたんですね。それで自分でも味噌を作ってみようと始めたのです。
醸造業は歴史的に古く、味噌も保存食で、たんぱく質の供給源なので、例えば伊達藩などは政策的に味噌造りを育成し、仙台味噌という特徴ある味噌が江戸時代の初めからあります。だから、創業200年、300年というのは全然珍しいことではなく、ひかり味噌は、業界の中では最後発に近いんです。
──そうはいっても、会社組織になってからでも80年。経営史学界では100年たったら老舗と言われますからね。
林 まあそうですね。ただ味噌は、国内では、じり貧状態です。ずっと50万トンぐらいの市場規模だったのが、今、40万トン弱でほぼ下げ止まっています。業界団体の一部は、「味噌は体にいい」という啓蒙活動が効いてきたかなと言っていますが、ちょっと手前味噌なところもある(笑)。
悲観的な意見もあります。今の味噌の需要を国内で支えているのは団塊の世代で、ここがいなくなってしまうとガクッと落ちるのではないかと。
──でも、海外への輸出は増えていて、ひかり味噌さんもそちらに力を入れている。決してじり貧ではないのでは、と思うのですが。
林 国内は厳しいだろうと思いますね。少子高齢化と、それによるライフスタイルの変化によって需要はより縮小するでしょう。
一方、確かに海外は乱暴な言い方をすれば、向こう10年間くらいは、毎年2桁成長は確実だろうという、自信めいたものを私は持っています。
日本食の海外事情
──それはすごいですね。昔は欧米の人たちは、味噌汁というと、顔をしかめていたようなところがあったと思いますが、最近では、むしろ好んで飲むようなところもありますね。
林 日本食のステイタスは、今、海外では非常に高い。ロンドン、ニューヨークといった大都市で、彼女を連れて行きたいレストランは高級ジャパニーズレストランなんですね。フレンチよりも、スパニッシュよりも、はるかに上です。
さらにもう1つの流れに、いわゆるB級グルメがあります。例えばロンドンに行くと、「カツカレー」を皆、知っていて、「カツカレーのスープ」というものがスーパーで売っているぐらいです。そして全世界で、今、一番人気があるのがラーメンです。どこへ行っても出店ラッシュ。日本人が関与していない、ラーメンの小売り商品も出てきました。
彼らは「日本食は健康」というイメージがあるものですから、ラーメンに小麦粉ではなく米粉を使う。われわれがラーメンだと思って食べると、食塩値が目茶苦茶低くて食べられない(笑)。それでも売れるんですね。
ですから、われわれも、昔ながらのごはんと味噌汁の定食、というところばかりを追いかけるのは古いんです。大きな変化の中で、味噌をどうやって使ってもらうのかを考えていかなければいけないですね。
──海外の健康志向というのはいかがですか。
林 今、アメリカでは腸内環境をよくすることが人間の健康のもとだと、すごく言われています。そのために「発酵食品である味噌がいい」と最近、特に言われてきている。もう1つは抗酸化作用ですが、総じて発酵食、日本食というのが今、すごく大きな追い風になっていることは事実です。
塩分についても、海外向けは低塩設計にして、日本に比べて最低1割は薄くしています。1日の標準的な摂取量というのは、アメリカでは、FDA(アメリカ食品医薬品局)が規定していて各国にガイドラインがありますので、その中に収まるようにレシピを組むようにしています。
ただ、全部が全部それを守らなければいけない、ということはないのです。結局は、誰に売るのか、チャネルがどこかということになります。 健康志向のお客さんが来るスーパーとアジア系のスーパーでは違うのですね。アメリカというのは大きなマーケットで、いろいろな人種がいて地域差もあるのです。
──やはり、海外ではアメリカに一番力を入れているのですか。
林 そうですね。ほぼ6割がアメリカ向けで、私はアメリカを筆頭に欧米を重視しています。
その理由は、1つは価格水準が高いことです。日本のスーパーの店頭価格の1.5倍からほぼ2倍の値段で現地の小売価格が成立しています。しかも今、アメリカでは全量、冷蔵コンテナを使っているので、日本のスーパーのように、夏は問屋さんで1カ月、30℃、40℃のところに味噌が置かれ、店頭に入ってくるときには赤くなっているようなことはありません。極めて素晴らしい状態で、ピカピカの味噌が並んでいます。
またアメリカでは、今も人口が増えていて、法制・税制も完備されている。さらに、アジア系の人口が多いということも私たちにとって魅力です。
──それはありますよね。
林 アメリカで売り込もうとしたときに、日本食のグロサリー(食料品店)はすぐ採用してくれる。そしてチャイニーズ、コリアのスーパーに来る人たちも味噌を違和感なく買ってくれるので、まずここで基盤を築く。様子が分かってきたら、メインストリーム、つまりアジア人とは関係のない、現地の人が行くマーケットやレストランで売るという、2段階の展開ができるんですね。
ヨーロッパにはアメリカのように大きなアジア系の人口はないので、第1ステップの受け皿がないのです。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

林 善博(はやし よしひろ)
ひかり味噌株式会社代表取締役社長
塾員(1982政)。大学卒業後、信州精機(現セイコーエプソン)入社。1994年家業である、「ひかり味噌」に転職。2000年より現職。