【その他】
【講演録】福澤諭吉『民情一新』と「文明の利器」
2025/03/11
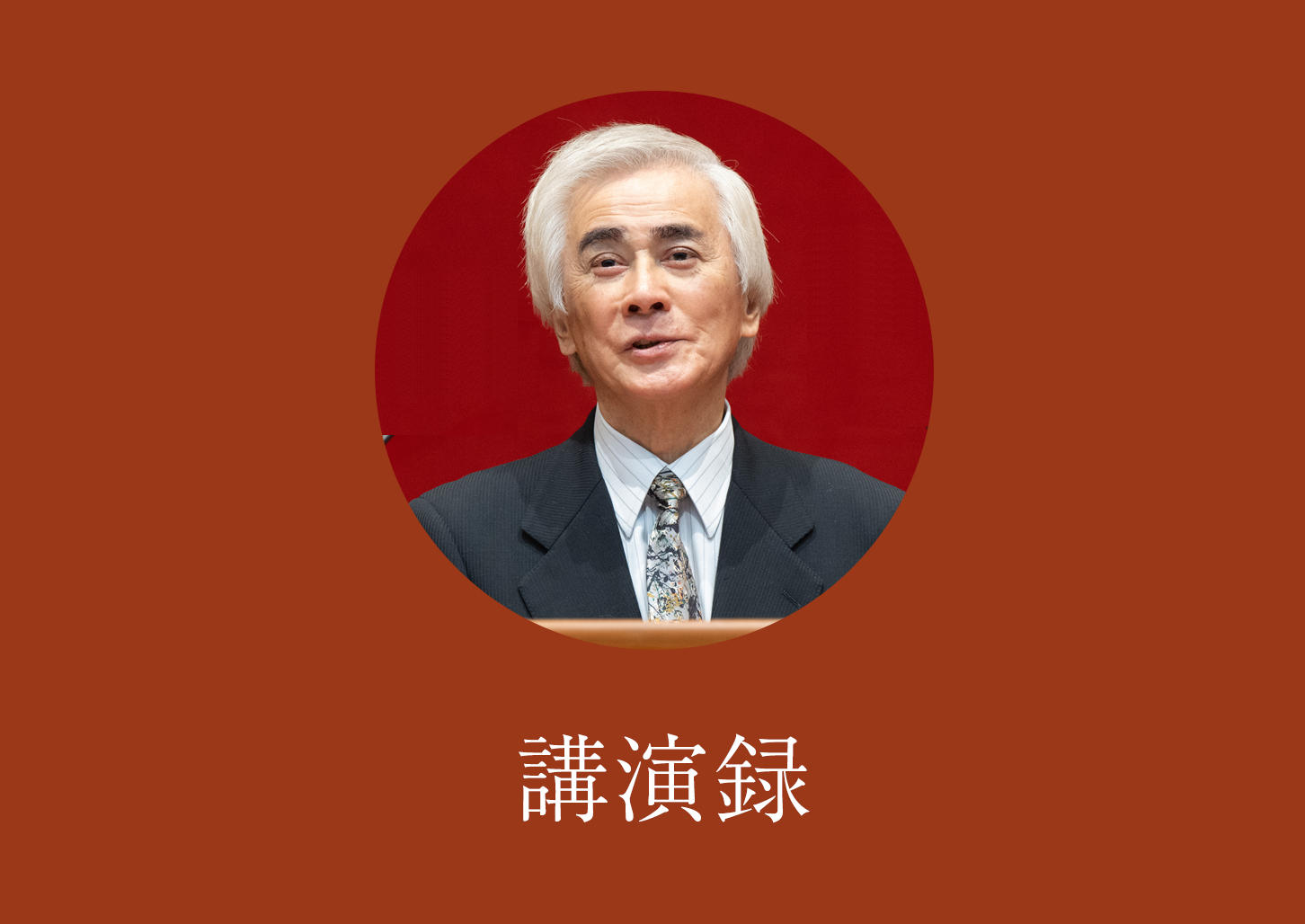
ただいまご紹介にあずかりました杉山です。本日は190回目の福澤先生の誕生記念会の講演にお招きいただき、非常に光栄に思っております。
本年2025年は、戦後ちょうど80年、昭和100年という歴史の節目に当たる年です。私は団塊の世代の生まれですから、同じくらいの人生を前の時代に遡ってみると、敗戦の1945年から80年前の時代は1865(慶応元)年なんですね。私がもう1回遡って生きたのと同じくらいの年数だとそのくらいになるわけです。明治維新の直前です。短いといえば短いですね。そこから太平洋戦争までの約80年は、戦後の80年以上に社会の非常に大きな変化が見られた時期と言ってよいと思います。
私の専門は日本経済史、なかでも日本の産業化と貿易との関係について研究してきました。現役で教えていた頃には、福澤先生の著作をいろいろ読んではいても、つまみ食い的で、なかなかまとまって読む機会はありませんでした。退職したら、『福澤諭吉全集』をちゃんと読もうと思い、ようやくこの数年で読むことができました。そして昨年、慶應義塾大学出版会から『近代日本の「情報革命」』という、近代日本の情報化がどのように進展したのか、明治政府による郵便や電信などの社会のインフラ、情報のネットワークの構築が地方において、実際にどのような影響を及ぼしたかを考察した研究書を出しました。そのなかの1章で、福澤先生の『民情一新』を取り上げたわけです。
福澤の思想を分ける『民情一新』
『民情一新』は、1879(明治12)年、福澤先生44歳の時に書かれた著作です。岩波の『福澤諭吉全集』で60ページ足らず、文庫にしても80ページほどの非常に短いものですが、内容は非常に凝縮されていると思います。
福澤先生というと、『西洋事情』『学問のすゝめ』や『文明論之概略』などがよく知られていて『民情一新』を読んだ方はそんなに多くないと思います。経済史を専門にしている方はそれなりに読んでいる方もいますが、一般的にはあまり大きな評価を得ていないという状況です。
福澤先生の思想は、1880(明治13)年頃を境に大きく前後に分かれると言われています。1880年以前は前期福澤とよく言われますが、その時代は非常に理論的で、抽象的なテーマの著作が多い。一方で80年代以降の後期福澤と言われる時期は、ご存じの通り、「時事新報」の社説や評論などに見られるように、かなり具体的で時事的ななテーマに関して議論をされています。
もちろん福澤先生は一貫して慶應義塾の経営、それから教育者としての役割は果たしているわけですが、思想史的に考えると、前期の、いわゆる洋書の翻訳、翻案によって、西洋文明の輸入と紹介に努めた時期は、啓蒙的思想家の時代と言われます。それが明治14年の政変で大きく状況も変わり、それ以降は「時事新報」を中心にした、いわゆるジャーナリストの時代ということができると思います。こうした福澤先生の思想をちょうど分ける、その分岐点にあるのが、この『民情一新』という作品なんですね。
福澤の歴史に対する態度
皆さんもご存じの通り、福澤先生は非常に多作で筆も速い。書かれているものを見ても、その時々の見解をかなりストレートに表現され、基本的には非常に前向きで楽観的な思考の方だと思います。なかでも福澤先生の発想や考え方は緒方塾(適塾)での経験が非常に大きく、そこで医学や物理学などの自然科学の原書の講読を通じて、当時の世界の最先端の知識を習得しました。ここで科学主義に基づいた論理的、合理的な思考を繰り返しトレーニングしている。これは非常に重要なことだと思います。
逆に、科学的な実証に裏付けられない儒教のようなものは、「虚学」として批判し、いわゆる科学的な実証に裏付けられた「実学(サイヤンス)」を非常に強調しました。
福澤先生は、「学問の要はただ物事の互いに関わり合う縁を知るべし」とおっしゃっています。これは、事物の関係性、因果関係を解明することが非常に重要なのだということです。それは機械のような技術のことだけにとどまらず、社会制度やシステムなどの広いものをも対象にして考察をしている。そういう意味から、福澤先生の考え方は、先ほどの塾長のお話にもあった、今でいう「文理融合」を体現しているものだと言っていいのではないかと思います。
福澤先生自身は歴史家ではありませんから、歴史の見方について、こういう方法が必要だということは述べていませんが、福澤先生の晩年、亡くなる直前に「瘠我慢の説」が刊行されています。これは、もともとその10年前にすでに脱稿していたもので、幕臣の勝海舟や榎本武揚の明治維新後の進退に言及して批判をしています。
「瘠我慢の説」に対してすぐに徳富蘇峰が「国民新聞」で反論をしています。勝が外国の干渉を憂慮して江戸城を明け渡し、それによって日本の危機は収拾され、維新の大業が完成したのだと、蘇峰は勝海舟を擁護し、福澤先生を批判しています。これに対して福澤先生はすぐに反論し、「これを一読するに惜しむべし論者は幕末外交の真相を詳(つまびらか)にせざるがために、折角の評論も全く事実に適せずして徒に一篇の空文字を成したるに過ぎず」と批判しているんですね。
どういうことかというと、蘇峰は1863年、明治維新の直前に生まれていますが、その時すでに福澤先生は外交文書や居留地の新聞などを翻訳するなどして、当時の時代の感覚を共有していました。それに対して、蘇峰は生まれたばかりなので当時のことが記録された史料だけで批判をしている。こういう史料至上主義とでもいうようなアプローチを、福澤先生は「架空の想像」と言っているわけです。
実際に歴史を見る際には、時代の感覚を共有し、時代の雰囲気にどれだけ近づけるかが重要になってくるわけです。もちろん、福澤先生はあまりにも激動の時代に生きていたので、逆のバイアスもあるかもしれませんが、いずれにしてもある時代を遡って考える時、ぼくらはその後の時代のことも知っているので変な先入観が入ってしまう。
さらに、後のいろいろな研究もあるので、いわゆる研究史の解釈に引きずられてしまうことも非常によくあります。こういうことを避けて、その時代の感覚を共有すること、歴史のなかの現在と言ってもいいと思いますが、歴史とはその時点までしかなかったのだ、という時代感覚を共有することが大切だと思うのです。福澤先生の議論は「状況的思考」などとよく言われ、「今」という、特定の時間の特定の場所であることを非常に重要視されていますが、この態度が歴史を見る時、歴史を遡って考える時に非常に重要になってくるのではないかと思います。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

杉山 伸也(すぎやま しんや)
慶應義塾大学名誉教授