【時の話題:変わる日本の土地制度】
十川 陽一:古代日本の土地制度
2025/07/14
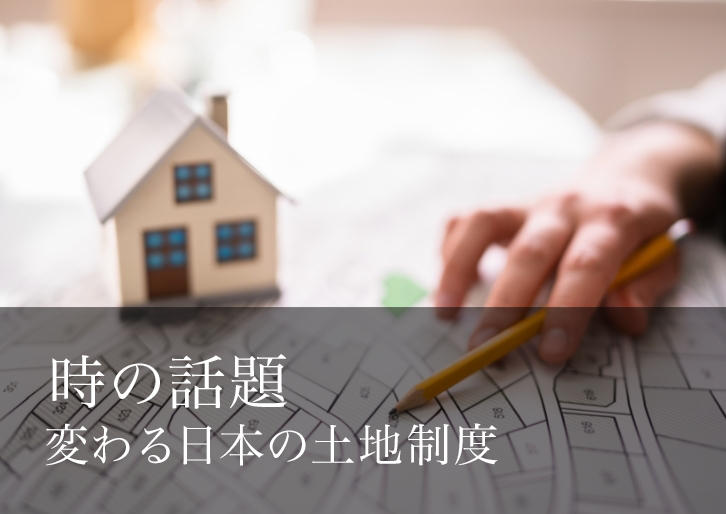
「おおみたから」とは、古代の人々を表す「公民」にあてられる訓である。その意味は「大御田族(おおみたから)」すなわち国家の田を耕作する人々、との説が有力である。日本の古代国家たる律令国家は、全ての人々を戸籍で管理し、
田(口分田(くぶんでん))を分かち与えた。その中には、実態として耕作に従事しない人々や農耕を主たる生業としない漁業者・手工業者なども含まれる。母法の唐令に存在した、手工業者への班田を通常の半額とする規定をあえて継受していないなど、日本令では人と田を結び付けて管理するという理念が強い。
口分田は6年に1度班給され、死亡した場合には次の班田時に収公される、いわゆる班田収授が律令制の原則であった。ただしここには、新たに開墾した田地の扱いが定められてないなどの問題があった。そうした中、天平15(743)年に、開墾した田は一切収公しないものとした墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)が制されることになる。この法は有力王族・豪族などの大土地所有を招き、律令国家崩壊のきっかけとなったと理解されることもあるが、古代史研究者の間では、私田の概念を明確にして国家的な管理下に置くことを定めた、律令国家による土地支配の深化・拡大であるという理解が一般的である。遺産相続について定めた戸令応分条では、701年に施行された大宝令段階では田は相続の対象ではなかったが、757年の養老令では田も遺産相続の対象となる財産として規定された。このことも、私田の存在が明確になったことの反映といえよう。
さて王族・豪族は、律令制以前に私地を所有していたが、これらは律令制下においても国家から給付される封戸や位田といった形で存続している。すなわち理念とは異なり、実態としては必ずしも公地公民ではない面もあった。ただしこれら荘や庄と呼ばれる私有地の収穫物の徴収・納入は、国司・郡司という律令国家の地方行政機構が担当する形式であった。私的な土地所有を国家が間接的に取り込むような形式を取っていたといえる。さらに天皇家の土地も、いわば私的な土地であった。天皇家の土地のうち、9世紀半ば頃には、皇族の日常的な経費を賄うために、勅旨田(ちょくしでん)や後院田(ごいんでん)などが全国各地に新たに設定された。公費を投入して、新規開墾や荒れた田の再開発を行うもので、各地の郡司たちの積極的な協力によってなされた。郡司たちは勅旨田の設定に協力する見返りに、高い地位を得て、地域内での権威を確立していたのである。
また本来の律令制では未開発地や用水権を含む山野の入会利用は公私共利とされ、独占的な私有を排除する空間も一定程度存在していた。灌漑施設等が破損した場合は、国司の管下で人々を動員して修繕する制度であったが、私財を蓄積した富豪層に、高い地位と引き換えに、私財を提供させて行う例が増加する。国家的な土地管理と共益とのバランスは難しい問題であるが、律令国家は地方の有力者たちの力も活用しながら、土地支配を維持していた。
なお重罪を犯した者の動産・不動産を没収する慣行が律令制以前から存在した。すなわち王族や豪族の私有地は、政治情勢などによって収公されるリスクが伴うが、こうした事情による離散を防ぐため、氏寺への土地の施入も行われ、寺領の集積も進んでゆく。仏物となったものは原則として収公の対象とはならず安全であったためである。
ところで有力農民の中には、戸籍に登載されないまま、つまり税などを免れながら私富を蓄積する富豪浪人も現れるようになる。また9世紀から10世紀にかけて、それまで存続していた集落が突如消滅するという傾向が全国的に見出される。気候変動なども理由の1つとみられるが、これら社会の変化によって、戸籍とセットで行われていた従来の土地支配が困難になった。
もともと、口分田からの収穫には租(そ)という税が課されていた。上質の水田でも収穫物の3%程度という低い税率で、郡の正倉(しょうそう)に保管される、地方財源であった。律令制以前から、共同体単位で収穫された稲の一部を神にささげる初穂(はつほ)を起源としたものと考えられている。律令税制は、こうした律令制以前からの共同体を前提として課されていたが、上記のような社会の変化により、戸籍といった帳簿による管理ではなく、実際に耕作されている田に課税し(官物(かんもつ))、必要に応じて諸役を課す(臨時雑役(りんじぞうやく))方式へと転換した。
土地を誰が持っているのか、そこにいかに課税するかは国家にとって重要な問題である。古代の土地支配については現在も多くの議論が重ねられており、本稿で挙げた論点もごく限られたものに過ぎない。ただ律令国家は、有力王族・豪族、さらには地方豪族の力も活用しながら、変化する社会に対応して可能な限りの支配体制を維持しようとしていたといえる。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
2025年7月号
【時の話題:変わる日本の土地制度】
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

十川 陽一(そがわ よういち)
慶應義塾大学文学部日本史学専攻准教授