【時の話題:シニアを愉しむ】
大森 静代:生涯現役脳でいるために──シニアからの学び直し
2025/01/20
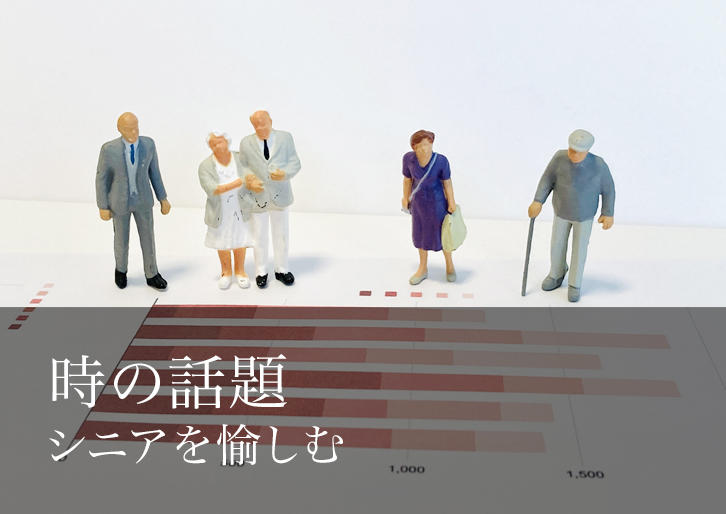
60歳で大学を卒業
活き活きと毎日を送り、生涯現役脳でいたい。機械に油をさし、手入れをしないと錆びて動かなくなってしまうのと同じ。「学ぶ」という油をさし、「実践」という手入れをすれば、脳は活性化して「生涯現役脳」。人生が豊かで活き活きとしたものになる。
大学の通信教育、放送大学、職業訓練校、資格取得の勉強は、それ自体が役に立つ。情報や知恵・経験などが詰まった引き出しが増えれば、必要な時に必要なものを取り出し、役に立てたり困難を乗り越えるのに使ったり、危険を回避したりできる。何歳になっても学ぶのに遅いということはない。学べば学ぶほど能力や脳力を高めることができる。「無限の可能性」は人間だけが持っている特権。
私は、高校生の時に大病で長期欠席し、成績は低迷。家の事情もあり、大学進学をあきらめ就職した。48歳の時に、やはり大学で学びたいと慶應義塾大学の通信教育課程に入学した。通常はテキストでの勉強。学校で授業を受けられるスクーリングの日に校門をくぐると18歳の青春に戻った。通信は老若男女が集い職業もいろいろ。70歳を過ぎた人の学ぶ意欲に感動した。学生証で映画館・美術館等は学割がきくので大いに利用した。
離婚していた私は、仕事・子育て・勉強の3本立て。「私には無理かも」と思いながら5年が経った。一時は退学するつもりでテキストを処分しようと思ったが、払った学費が惜しかったのとすんなり英語の単位が取れたことで勉強を続けられ、60歳で卒業した。
卒業するコツは、「周りに公言すること」。そうすれば挫折できない。初めは「できない」と思ったのが、「やってみよう」となり、「できた」に変わる。そして念願の大学卒業が叶い、自信がついた。諦めない力、考える力、先を見通す力が身に付いていた。
通信の教育レベルについての誤解
通信教育課程の内容があまり知られていないために、「通信生は簡単に入学できてレベルが低い」「通信生が卒業に年数がかかるのは頭が悪いから」などの誤解がある。通信教育課程は通学課程と同じ教員に学び、学生は所定の単位を修得すれば、慶應義塾大学の卒業生として学位(学士)を取得できる。学位記(卒業証書)は通学課程と同様のものが授与され、「通信」の文字はない。通学課程は入学するのが狭き門、通信課程は卒業するのが狭き門というだけである。
通信の卒業所要年数の平均は私の入学当時、普通課程で8年、学士入学で5年。卒業率はわずか3%だった。年数がかかるのには理由がある。
通信教育で学ぶ苦労と喜び
通信教育の学習方法は、通信授業(テキスト)と面接授業(スクーリング)の2つ(現在はインターネットによるメディア授業もある)。通信授業は配布されるテキストで学習を進め、レポート提出後に科目試験を受ける。両方合格して初めて単位取得となる。通信生は人数が多いので、事務処理とレポートの採点に時間がかかるのではないか、とも学生の立場からは感じられる。また、不合格を繰り返すと新しいテキストに変わってしまい、新しい課題で学び直すことになる。すると当然、卒業までの期間は延びていく。通信生が卒業まで時間がかかるのはこのような事情もある。
大学の通信教育課程はほぼ独学。一生懸命勉強するだけでは卒業できない。卒業は登山で言えば頂上に立つこと。装備とルートを間違えると頂上にたどり着けないのは学問も同じ。この経験から著書『働きながら60歳で慶應義塾大学を卒業した私の生涯学習法』(合同フォレスト)を出版した。生涯学習法としての大学の通信教育他、いろいろな学び方(教育だけではない)とそのコツを書いた。
慶應義塾大学の通信教育課程で学んでいることを公表してから、多くの方の応援があった。塾員のYさんには私を「孫がいる歳なのに通信で勉強している感心な人」として、新宿中村屋創業者である相馬愛蔵・黒光夫妻の孫にあたるSさんを紹介していただいた。私の卒業論文は「木下尚江研究」。相馬夫妻は木下尚江と親交があった。Sさんには木下尚江に関する資料を提供していただき、木下のお孫さんを紹介して下さった。中村屋で卒業祝いもしていただいた。この他、木下尚江ゆかりの土地を案内してくれた人、資料を探しては送ってくれた人。ある会で主催者(慶應関係)からの卒業祝いは慶應義塾の元応援指導部団長からのエール。感動の涙が溢れた。
中学、高校の先生は我がことのように喜んでくださり、子どもは「頑張ったね」と卒業祝いと還暦祝いをしてくれた。入院中の母は卒業証書を周りの人に嬉しそうに見せていた。母へのたった1つの親孝行になった。
通信教育課程で学ぶことは大変だったが、大きな喜びとたくさんの人との繫がりが生まれた。「できないは、やってみてから言う言葉」「“やっておけばよかった”より、“やっておいてよかった”の人生を」の言葉が浮かび、私の信念になった。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
2025年1月号
【時の話題:シニアを愉しむ】
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

大森 静代(おおもり しずよ)
生涯学習アドバイザー・活き活きLifeアドバイザー・塾員