【福澤諭吉をめぐる人々】
藤原銀次郎
2024/10/28
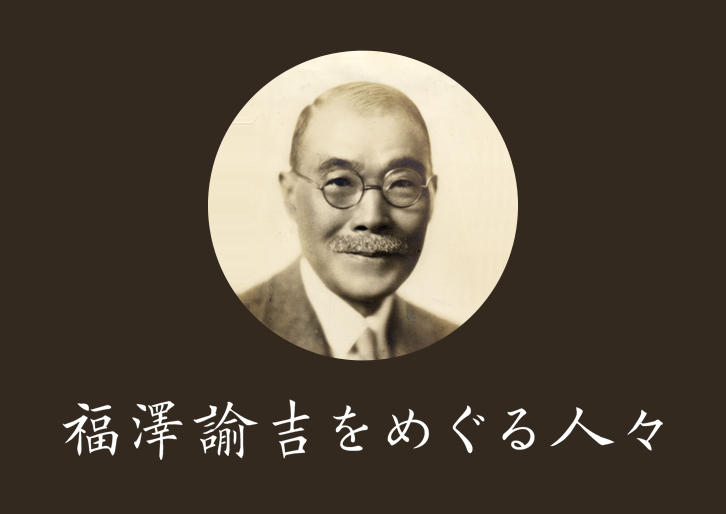
「三井財閥の立て直しに尽力」「国務大臣としての時代」「一世一代の製紙王」「藤原工業大学の設立」「慶應義塾への大学の寄付」等、財界人としてのみならず、政界や教育界等、様々な分野に於いて活躍した人物として、藤原銀次郎(ふじわらぎんじろう)は、その名が知られている。
藤原は、福澤の門下生として、福澤の教えや言葉を直接受けた人物である。昭和35(1960)年に90歳でその生涯をとじるまで、福澤の教えが、大きな支えとなり、それに影響を受けていたことは言うまでもない。
同郷の先輩との縁
藤原は、明治2(1869)年に、長野県安茂里平柴の大地主藤原茂兵衛の3男2女の末っ子として誕生した。藤原本人は自身の少年時代のことを、「まことに静かな、おだやかな生活で、人間というものは贅沢さえしなければ、生活に困るようなことはないものだと考えて、生長して来ました」と自著(『福澤先生の言葉』)の中で述べている。しかし、社会に出てからの藤原は、少年時代に描いていた人生の夢とは程遠い、多くの苦難に遭遇することとなるが、その苦難を乗り越え、その経験を力としていった。
少年時代から非常な勉強家であった藤原は、東京の学校で学びたい旨を父に伝えると、医者になることを条件にようやく許可がおりた。しかし上京して、同郷の先輩である鈴木梅四郎を訪ねると、鈴木が学んでいる慶應義塾に入ることを勧められた。やはり同郷で後に貿易商として成功する赤尾善治郎からも慶應義塾に入れと勧められた。そこで藤原は、医者になることをやめて、慶應義塾に入ることになった。鈴木は、後年、低所得者の為に社団法人実費診療所を作り、医療の社会化運動の先駆的役割を果たした人である。
経営者としての藤原
藤原は義塾を卒業後、明治23(1890)年に時事新報の伊藤欽亮の推薦で、島根県の松江日報に主筆として就職した。しかし、経営状態は惨憺たるもので、26年には社長も兼ねざるを得なくなった。「世の中に貧乏ほど苦しくつらいものはない。世の中は決して子供のときに考えていたほど、のんきな、あまいものではないと、心の底から痛感させられたのでした。この時の経験と自省は、私の一生に実によいクスリになりました」と後に、前述の回想に続けて、対照的に語っている。
明治28(1895)年、藤原は三井銀行に移った。 三井銀行は、立て直しが必要な時期であった。福澤の甥の中上川彦次郎は、経営危機に陥っていた三井銀行の改革をすることとなり、その際、義塾出身の人物を多数招聘していった。招聘されたメンバーには、本欄でも既に紹介した朝吹英二、池田成彬をはじめ、藤山雷太、日比翁助ら後に財界でも著名な人物が名を連ねているが、その1人として、藤原も招聘されたのである。
藤原に声をかけたのは、藤原が慶應に入学するきっかけとなった時と同じで、同郷の鈴木梅四郎とも言われている。藤原は、松江日報を辞めて三井銀行に入り、滋賀の大津支店で1年間銀行業務全般を経験し、東京深川支店の主任という立場で、様々な新しいアイディアを出し銀行を拡大していった。
この働きぶりにより、藤原は新たに大きな仕事を任されることとなる。明治30(1897)年に、藤原は、富岡製糸場の支配人となり、製糸場の工員達の不満解消に努め、不平等さを無くし経営を立て直した。さらに明治44(1911)年には、王子製紙の専務となり、経営不振の立て直しにも着手することとなった。多くの苦境にあっても様々な改革でその経営危機を乗り越えた藤原は、昭和8(1933)年、王子製紙と富士製紙、樺太工業の3社合併を実現し、王子製紙は、日本国内の大半の製紙・パルプ製造を占有する巨大製紙企業となった。藤原は、この新生王子製紙の社長として再建を果たし、「製紙王」と呼ばれ、経営者として不動の地位を築き上げた。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

白井 敦子(しらい あつこ)
慶應義塾横浜初等部教諭