【福澤諭吉をめぐる人々】
北里柴三郎
2024/07/05
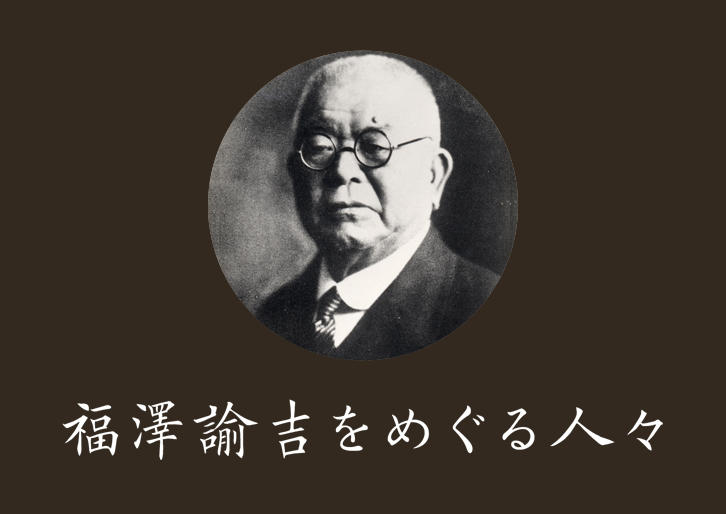
「嗚呼(ああ)、我が科学の扶植者たる及び余が事業の保護者たる先生は今や即ち亡し。余は衷心、実に師父を喪いたるの感あり。然れども先生の偉業は依然として我が眼前に存し、先生の遺訓は歴然として余が脳裡にあり。余不敏といえどもまたその偉業を守りその遺訓を体(たい)し切磋研鑽以て万一の報恩を期せんとす。嗚呼悲哉。」
明治34(1901)年、福澤諭吉の葬儀の前日の2月7日、北里柴三郎が『細菌学雑誌』に寄せて記した「福澤先生を吊う辞」の結びである。「余はこの際に臨み特に嗚咽歔欷(おえつきょき)(すすり泣くこと)に堪えざるものあり何ぞや。我が科学の扶植者たる及び余が事業の保護者たる先生に永訣したること是なり」とも記している。北里にとって福澤がどのような存在であったかをよく示す文である。
長与専斎、ローベルト・コッホ
北里と福澤が出会ったのは、明治25年、福澤満57歳、北里満39歳の時のことである。しかし、その伏線は、早くに敷かれていた。
肥後国の小国郷北里村に生まれた北里は、明治4年から熊本医学校で学び、8年、東京医学校(今日の東京大学医学部)に転じた。校長は福澤と適塾以来の親友の長与専斎であった。そして、16年、卒業すると長与が局長を務める内務省の衛生局に入ったのである。
当時は、赤痢やコレラ等の伝染病対策が喫緊の課題であった。北里は衛生局からドイツに派遣され、19年から、ベルリン大学の細菌学者ローベルト・コッホの下で研究することになった。
約5年の滞在中、北里は精力的に研究に没頭し、破傷風菌の嫌気性純培養、免疫血清療法の開発など、多大な成果を挙げた。北里には、欧米各地の大学や研究所からの招きもあったが、断って25年5月に帰国した。
ドイツ滞在中には脚気論争もあった。今日では脚気はビタミンB1の欠乏によることがわかっているが、当時、帝国大学の緒方正規は脚気の患者の血液から病原菌を発見したと報告した。オランダのペーケルハーリングも脚気菌の報告をした。これに対して、北里は脚気菌病原説を否定する見解を発表したのである。北里にとって緒方は先輩であり、留学前に細菌学を学んだ師でもあった。そこで、後に東京帝国大学総長となる加藤弘之は「師弟の道を解せざる者」と北里を非難し、森鷗外は「北里は識を重んぜんとする余りに果ては情を忘れしのみ」と非難した。北里は、「私情」をも抑え「公平無私の情」で研究に従事しないと真理を究めることは出来ないと反論している。このような学者としての誠実さは、コッホの下で意を強めたものでもあった。
福澤の支援
帰国した北里は、前述のような経緯もあって文部省や帝国大学から冷遇され、なかなか研究の環境が得られないでいた。その状況を見かねた長与は福澤に相談をした。福澤は早速、いずれ子供達の為にと用意していた芝御成門近くの借地を提供、良き理解者であった実業家森村市左衛門の協力も得て伝染病研究所を設立した。そして以来、生涯に亘って北里を支援することになった。
伝染病研究所は、間もなく大日本私立衛生会の支援も受けることになった。国の補助等も受け活動を拡大しやすくしたのであるが、この大日本私立衛生会も、もともと日本の衛生環境の改善や健康思想の普及を進める為の民間団体として作られたもので、その主要なメンバーは長与専斎、松山棟庵、長谷川泰、後藤新平ら福澤に近い人達である。
翌26年には、国の補助も得て愛宕下の土地に、移転拡張することになった。しかし、地元から反対運動が起こった。福澤はその沈静化にも尽力する。例えば、細菌が恐ろしいものではないことを実地に示す為にと、次男捨次郎の住居を隣に新築した。また、福澤が創刊した時事新報では、「伝染病研究所と近辺の住民」などの記事を掲載すると共に、「伝染病研究所に就いて」と「伝染病研究所の始末」の論説を執筆掲載した。中でも後者は、北里の長文の辞表を収めたものであるが、実は福澤の手によるこの辞表が人々の心を打ち、反対運動はようやく鎮静化、北里は所長のまま無事に愛宕下に移転することができたのであった。
以後、伝染病研究所は順調に発展した。研究所の1人、高野六郎は著書の中で、次のように記している。
「伝染病研究所はわが国伝染病予防の参謀本部である。北里は防疫の参謀総長の観がおる。防疫の事務は内務省衛生局によって行われるが、その学術的指導は北里がこれにあたった。当時の衛生行政の主要部分は防疫であったから、形式上の衛生局長は大手町におるが、本当の衛生局長は愛宕下におるといわれた位である。事実日本の伝染病の予防は北里の思いのままになり、国内の防疫職員は北里の門下生であった。」
当時の日本は、夏には腸チフス、赤痢、コレラ等が、冬にはジフテリア等が流行した。そのワクチンの研究、製造も研究所の業務となった。また、全国各地にあった病原不明の風土病の研究と予防も研究所が担った。
福澤のもう1つの支援が、明治26年、白金三光町の自らの土地に作った結核の専門病院「養生園」である。福澤自ら土地の拡張、建物の建設まで陣頭指揮して創った。そして、経営面では、塾員田端重晟(しげあき)を事務主任に据えた。開園後の様子を後に田端は、「北里先生の雷名を慕って集まる患者のため、門前たちまち市をなし、六十余の病室も常に満員で増築又増築、満員又満員の盛況を呈しました」と述懐しているが、福澤は、その後も、最晩年まで頻繁に立ち寄っては助言を与えていた。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

山内 慶太(やまうち けいた)
慶應義塾大学看護医療学部教授