【福澤諭吉をめぐる人々】
フランシス・ウェーランド
2024/05/15
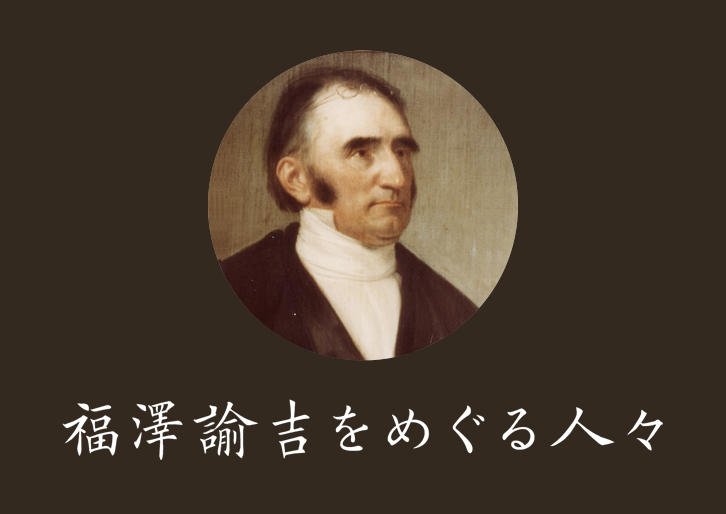
ウェーランドから浮かび上がる塾生たち
フランシス・ウェーランド(Francis Wayland)は、日本においてあまり語られてこなかったかもしれないが、慶應義塾においては福澤諭吉の時代から今日に至るまで大きな影響を与えてきた。面白いことに、ウェーランドを媒介として、福澤の思想や周囲の人物が次々と浮かび上がってくる。ウェーランドの二大著作と言えば、The Elements of Moral Science(『道徳科学綱要』、初版1835年、以下Moral Science)とThe Elements of Political Economy(『経済学綱要』、初版1837年、以下Political Economy)である。福澤はこの二つの著作には大いに関心を示し、「眠食を忘れ候程面白きもの」と述べている。のちに、Moral Scienceは門下の塾生であった阿部泰蔵(「福澤諭吉をめぐる人々」2023年6月号)により『修身論』(1874年)として翻訳されたし、Political Economyは後の塾長となる小幡篤次郎により『英氏経済論』(1871〜77年)として翻訳された。とりわけ、阿部の『修身論』は、日本各地の小学校へ教科書として普及していった。こうしてウェーランドの思想は本塾関係者らの手によって、全国へ伝わる素地ができていたのである。
現代の慶應義塾生たちにとって、もっともなじみが深いのはPolitical Economyかもしれない。Political Economyは、福澤の2回目の渡米(1867年)で手に入れ、日本に持ち帰った経済書である。『福翁自伝』で福澤自身が語っているように、1868年5月15日土曜日、上野の戦争中、立ちのぼる煙には目もくれず、福澤は塾生とともにアメリカから持ち帰ったばかりのPolitical Economyの講義を続けたという話がある。当時の慶應義塾の日課では火・木・土曜日の朝10時から「エーランド氏 経済書講義」となっており、担当は福澤自身だった。この話は安田靫彦による掛け軸に巧みに描写されているとともに、危機の時代にあっても学びを止めなかったというエピソードとして、塾内では21世紀においても、東日本大震災、コロナ禍などで脈々と語り継がれてきた。本塾では、この5月15日を「ウェーランド経済書講述記念日」として定め、1956年以降、毎年5月には「福澤先生ウェーランド経済書講述記念講演会」が開催されている。会場となる三田演説館にはウェーランドの肖像が掲げられる。
医師、聖職者、教育者
ウェーランドは1796年に敬虔なバプティストの夫妻の間に生まれた。ウェーランド誕生以前の20年間は、独立宣言、合衆国憲法の起草、ジョージ・ワシントン初代大統領の就任というように、まさにアメリカの輪郭が徐々に描かれようとする時代にあった。
ウェーランドが何者であったかを一言でいうのは難しい。医師、聖職者、思想家、教育者、学者、学長など様々な言い方ができるだろう。彼はユニオン・カレッジを卒業後、医師免許を取得した。医師という選択は家庭内の経済的困窮も一因であり、本来は聖職者を目指したかったのであった。1816年にアンドーヴァー神学校へ進むことになり、聖職者への道を歩み始めた。しかし、経済状況が厳しくなり学業の継続が危ぶまれたところに、母校ユニオン・カレッジより1817年からの講師のポストが提供され、古典語・化学・数学・修辞学など様々な科目を担当した。1821年には念願であった牧師にも就任することができた。
1826年9月よりユニオン・カレッジの教授に就任した矢先、ウェーランドは、ロードアイランド州プロビデンスにあるブラウン大学(今日のアイヴィーリーグの1つ)の第4代学長に30歳ほどの若さで選出された。その後1827年から1855年に至るまで、四半世紀以上にわたり学長職を務めることになる。当時の学長担当科目である道徳哲学のほかに、精神哲学、修辞学、文芸批判、生理学、経済学までも担当した。なかでも道徳哲学のための教科書として、自作の教科書をわずか半年で執筆したとされる。それがちょうど福澤の生年にあたる1835年に出版されたMoral Scienceなのである。福澤は当初Political Economyの講義を担当していたのだが、その講義を1年ほどで小幡篤次郎に譲り、自身はMoral Science の講義を担当するようになった。『福澤全集緒言』によれば、Moral Scienceは米国から持ち帰ったものではなく、1868年、小幡篤次郎が散歩中に書物屋で見つけてきた古本で、これに関心を示した福澤は横浜の洋書店丸屋(後の丸善)に60部注文し、塾生たちが読めるようにしたという。
伊藤正雄による研究で分析されているように、福澤の『学問のすゝめ』(『すゝめ』)は、Moral Science から強い影響を受けている。1874年に出版された『すゝめ』第八編の冒頭と、Moral Science第2巻Practical Ethics(実践倫理)のOf the Nature of Personal Liberty(個人の自由について)というセクションの冒頭を並べてみてみよう。
亜米利加の「エイランド」なる人の著したる「モラルサイヤンス」と云う書に、人の身心の自由を論じたることあり。その論の大意に云く、人の一身は他人と相離れて一人前の全体を成し、自からその身を取扱い、自からその心を用い、自から一人を支配して、務むべき仕事を務る筈のものなり。(『すゝめ』第八編)
Every human being is, by his constitution, a separate and distinct and complete system, …[一人一人の人間は生まれつき、独立した別個の完全な存在であって…](Moral Science)
福澤は第八編の内容がMoral Science を典拠としていることを冒頭で明示している。福澤はMoral Scienceを入手してからわずか5~6年ほどで、自身の著書にウェーランドの考えを取り入れているのである。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

佐々木 貴久(ささき たかひさ)
慶應義塾高等学校教諭