【福澤諭吉をめぐる人々】
高石真五郎
2019/02/26
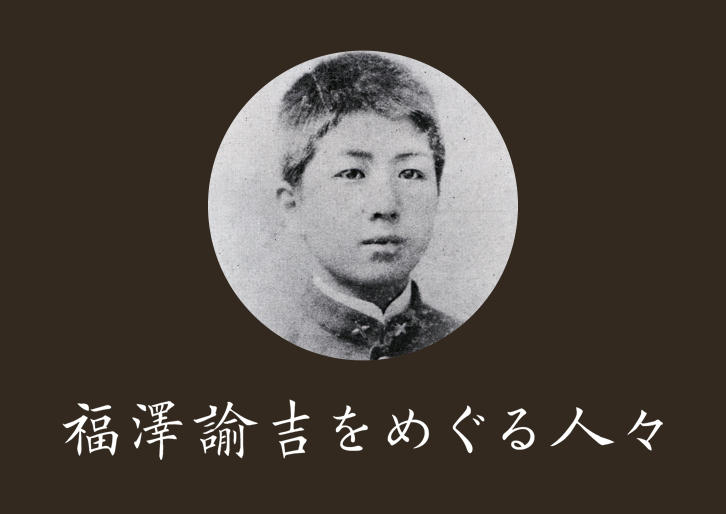
札幌五輪招致の隠し球
札幌オリンピックミュージアムに1本の音声テープが保管されている。
My friends, please forgive me for interrupting you at this time…
このように控え目に始まる高石の肉声を録音した2分余りのメッセージは1966(昭和41)年4月のローマでのIOC総会で、特に許可を得て流された。1972年の冬季五輪に立候補していた札幌は形勢不利と伝えられていた。IOC委員だった高石は、病気で出向けないことを断った上で、札幌の歴史とパイオニア精神、1940年の東京五輪と共に札幌の冬季五輪が幻となったことを経て、1964年の東京大会が成功したことを述べ、札幌にも同等の名誉を、と静かに訴えた。この音声が終わると、会場は拍手に包まれ、ニュージーランド代表から高石へのお見舞い電報の提案があり、それに応えて時のブランデージ会長が「高石への最上の見舞いは札幌大会だ」と発言、大勢は札幌に決まったと伝えられている。
1958年のIOC総会で東京五輪開催支持を発言したときにも「私は高齢だが、東京大会実現までは死にません」と発言、デンマーク代表が「高石を死なさないために、東京大会開催に反対を」とジョークで返し爆笑になった一幕も語り草となった。ブランデージに「young man」と渾名されたという高石の、この日本人離れした振る舞いはどこから生まれたのであろうか。
堂々たる塾生ぶり
高石真五郎は、明治11(1878)年9月22日、千葉県市原郡鶴舞町(現市原市)に生まれた。高石家は呉服商であったが、東京にいる兄の勧めで明治26年5月に慶應義塾に入学、大学部法律科へ進学して34年3月に卒業した。
在学中、福澤が身体鍛錬のために日課としていた「米搗き」の様子をそばまで見に行ったり、演説を聴きに行ったりすることはあったが、それ以上に深入りはしなかった。しかし、同級の友人が、踊りの稽古をしているという理由で退学処分を受けた際、その退学撤回を求めて福澤に直談判に行き、当時の塾長の顔を立てながら円満に復学させてくれた、細やかで親切な福澤の姿を、後に繰り返し語っている。
彼は在学中に同人誌の編集長をやり、各種スポーツにも参加、また下宿屋の玄関には芝浦方面の女性たちの赤い鼻緒の下駄が一杯並び、帝大生が遊び方の「秘伝を教えろ」と押しかけたと伝えられる派手な塾生時代を送っていた。あるとき福澤が、名前を書いて『福翁百話』をくれたことがあり、何故自分の名前を知っていたのか「今もなおその疑問が解けない」と晩年にうそぶいているが、ただならぬ塾生だったに違いない。当時普通部生だった小泉信三も、高石の姿は「子供心にも目についた」と語っていたという。
恐れ知らずの若手記者
「私は裏口というか、横手のくぐり戸というか、そういったまともでない入口から新聞社にはいった」と本人が語るように、高石の『大阪毎日新聞』(現在の毎日新聞。以下、大毎)入社は異例だった。卒業試験の最中に教頭の門野幾之進から声をかけられ、大毎社長小松原英太郎の社説執筆を手伝う私設秘書となったのである。
慶應義塾と新聞というと福澤の創刊した『時事新報』の印象が強いが、『大毎』も関係が深く、初代社長渡辺治、2代目高木喜一郎と塾員が続き、原敬を挟んで4代目の小松原も塾員であった(この人は官途に進んだやや毛色の違う人だが、かつては過激な民権思想で逮捕歴もあり、社長当時も義塾と関係を有し、門野に頼んだのであろう)。ちなみにその後を継ぐ5代目が本山彦一でこの人も塾員である。
小松原は、初対面で法外の月給50円を要求した高石に、それでも破格の40円で応え、明治34年4月より社長宅住み込みで3カ月間手伝わせた後、月給据え置きで正式な社員に編入した。こうして外国通信部に籍を置くこととなったが、外国人の取材で英語力不足を痛感、小松原社長に留学希望を申し出る。小松原は、留学費用は出せないが、月給は出しても良いと応じたので、高石は不足分の金策に奔走、三井家が何の条件もなく金を出すと聞きつけて3千円を「ちょうだい」して、入社翌年の12月にロンドンに到着した。援助に世話を焼いたのは、面識のあった三井銀行常務理事波多野承五郎(塾員)らであったという。
ロンドンでは記事送信の義務もなく、単なる貧乏書生として下宿、「寺子屋」から英語の勉強を始めて、1年後にはロンドン大学のスクール・オブ・エコノミックスの聴講生としてウェッブの講義を聴いていたという。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

都倉 武之(とくら たけゆき)
慶應義塾福澤研究センター准教授