【Researcher's Eye】
金沢篤:鉛をかじる数学者
2022/12/27
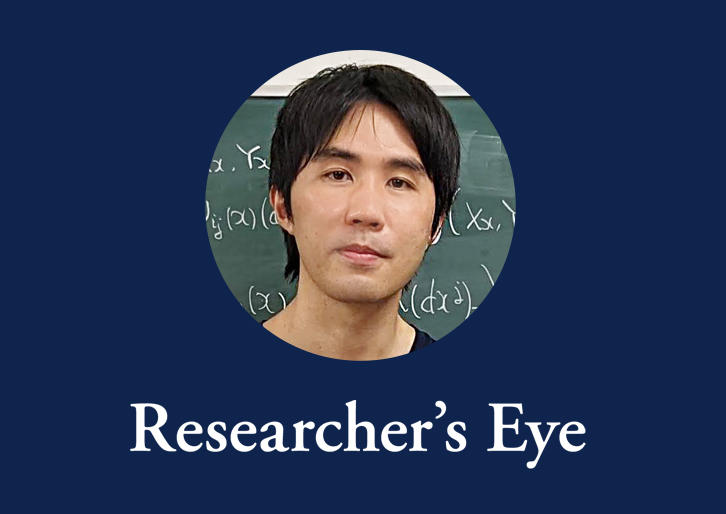
数学を教えるのは大変である。理由はいろいろあるが、その一つに、将来役に立ちそうにないから勉強しても無駄だと考える学生が多いことが挙げられる。
そんな話を非常勤講師の宮地恵美先生にしたところ、寺田寅彦の随筆「鉛をかじる虫」を教えていただいた。この随筆は鉛を食べて鉛を排泄する奇妙な虫と、それから連想される事柄を綴った作品である。この一見無駄な行動をする虫の類比として、教育が挙げられている。我々は学校で学んだことの大半を忘れてしまうが、忘れなかった僅少な一部がその人にとって重要な意味を持つ。無駄を嫌っては何もできない。
私はいわゆる碁キチであり、囲碁から多くのことを学んだ。最も重要な学びの1つが実利と厚みのバランスである。厚みの概念の説明は難しいが、人間としての厚み、深み、面白みに通ずるところがある。厚みは活用が難しいため、無駄になる可能性もあるが、乱戦・長期戦になればなるほどその価値は増す。人間の厚みも同じであろう。
ところで「無駄」とは馬に荷物を乗せずに歩かせるのはもったいないという意味である。一方、似た単語の「駄目」は囲碁に由来し、「打つ価値のない場所」と「石の呼吸点」という対照的な2つの意味を持つ。例えばダメヅマリは周囲にダメが少ない石が身動き困難になる様子を指す。ダメの詰まりは身の詰まり、ヘボ碁にダメなし、とも言う。
そもそも無駄なく仕事をすることは不可能である(熱力学第2法則)。一方で、無駄なことも必要なのであれば、それは無駄ではないのだから矛盾しているのではなかろうか、と数学者は思うのである。そんな屁理屈ばかり言う私の話を妻はいつも右から左に聞き流しているが、これも無駄ではないことを願っている。
話を元に戻すと、学生時代は長い人生の序盤なのだから、無駄を恐れず色々勉強して厚みを蓄えておくのが良い。そんな説教じみた話を学生にしても煙たがられるだけだと思うかもしれないが、今しがた説明した理屈によると全くの無駄ではなかろう。
そんなこんなで今日も私は数学書という鉛をかじっては、何も残らないような気がしつつも、少しでも賢くなることを夢見ている。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

金沢 篤(かなざわ あつし)
慶應義塾大学総合政策学部准教授
専門分野/ 数学・数理物理