【その他】
【KEIO Report】『小幡篤次郎著作集』完結を迎えて
2025/09/10
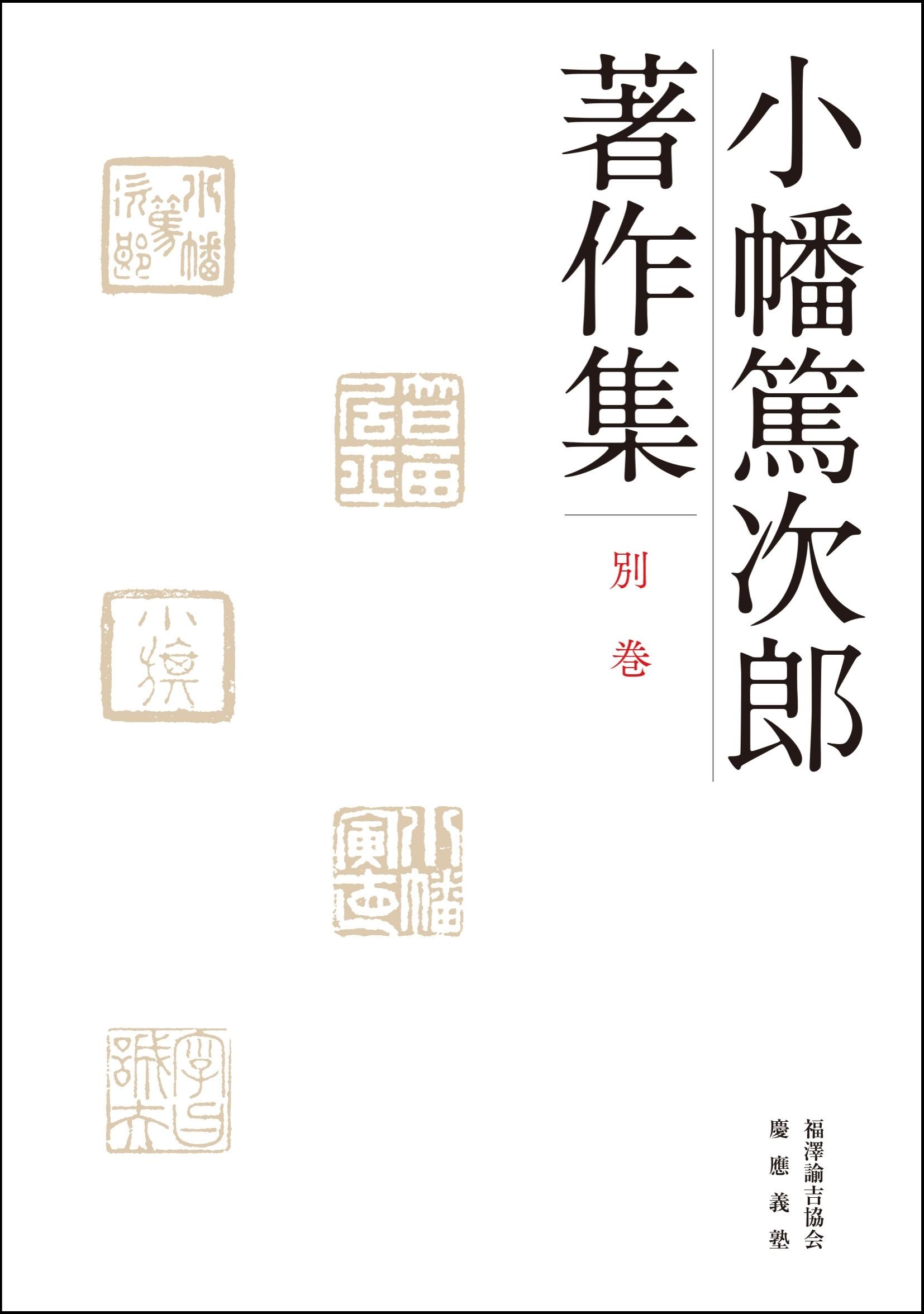
2020年に慶應義塾と一般社団法人福澤諭吉協会の共同事業として編集が始まった『小幡篤次郎著作集』は、昨年11月までに単行本や諸文集、書簡を収めた第1~5巻が刊行され、小幡宛書簡や参考資料、年譜、索引を収録した別巻が、遂にこの7月に発刊となった。しかし初の著作集は遅すぎて、『三田評論』の多くの読者の方にとって、いまだ小幡篤次郎は馴染みがないままかもしれない。
福澤諭吉はアメリカやヨーロッパの文明に直接触れる機会を得て、自身の塾を本格的な学塾に発展させたいと考えた。それにはまず人材である。江戸へ出て6年目の元治元(1864)年、帰省した福澤は周囲の人びとに助言を求め、そこで異口同音に推薦された人物が小幡篤次郎であった。
福澤の求めに応じて入塾した7歳年下の小幡は、その期待に応え、ABCを覚えるところから始めて2年後には、なんと学業優秀をもって幕府開成所に英学の教師として雇われるまでになった。福澤の塾においても、自ら学ぶ傍ら、学習上の疑問点から生活面まで、入塾生たちの面倒をよくみた。慶応年間から明治初期に在籍した塾生たちの回想録を読むと、彼の働きぶりがわかる。
慶應義塾と命名され明治を迎えた後も、彼は常に福澤の仕事を支え続けた。教育活動に止まらず、三田演説会も交詢社も時事新報も、小幡がいなければ、現在私たちが知りうるような成果は残っていなかった。それは同時代人の小幡評から窺い知ることができる。
曰く「小幡君の如き漢洋西籍を渉猟せし人を得るにあらざれば、恐らくは三田大先生の名を今日に全ふすることを得ざるべし」(明治14年6月『新聞投書家列伝初編』)、「小幡君にして無くば、慶應義塾の結果、蓋し今日の如き美を見る能はざる也。然れば即ち、今日政治界に立て世事を是非する者、多くは小幡氏の薫陶に依るものなり」(明治15年3月『自由官権両党人物論第二編』)、「慶應義塾あることを知るもの、必ず小幡篤次郎君あることを知り、福澤翁の名を知るもの、誰か君の名を記せざらん」(明治23年3月5日付『朝野新聞』)。
しかしながら現在小幡の知名度は、慶應義塾の中ですら低い。世間一般となるとなおさらで、誰もが知る『学問のすゝめ』初編で、福澤の左隣に「同著」者として名前があがっているにも拘らずである。長年にわたり小幡は「女房役」と位置づけられ、いつの間にか彼の業績は福澤のそれと一体化してしまった。
明治20(1887)年、小泉信吉を慶應義塾総長として迎えるにあたって、周囲は小幡の心情を慮った。それに対し福澤は、要らざる心配で、小幡を棄てる訳ではなく、二人して大店の隠居になるだけと述べている(明治20年10月1日付中上川彦次郎宛書簡)。だが周囲の反応は当然で、若い時から福澤は小幡を頼り、様々な局面で小幡の負担を増やすことで乗り切って来ていた。
福澤はしばしば無茶なことも言う。たとえば、一度教員に採用したAをやっぱりBに変えたいからAは断れという。小幡はすでにBの推薦者に先約の者に決定したと告げていたが、Bにするので仲介してくれと頼まなければならなかった(明治15年2月17日付小幡宛福澤書簡、2月18日付山田要蔵宛小幡書簡)。また奥平家から手当を切られた某について、可哀そうだから元に戻すよう口をきいてやれという。自分が話したいが多忙で「恐縮ながら清襟を煩はす次第」とは本当なのか(明治17年12月30日付小幡宛福澤書簡)。
ふと、太宰治の『駆込み訴へ』を思い出す。苦労して集めてきたパンを、奇蹟が起きたかのように人に与えてしまう主に、怨みつらみを述べるユダの話である。しかし決して小幡は福澤とは決別しない。それは小幡に、近代社会に対する確固たる展望があるからである。ただ福澤に追従しているのではなく、三田演説会にしても、交詢社にしても、もちろん慶應義塾にしても、彼の中でその果たすべき役割は明確で、自身がめざす社会を構築するために、福澤という先達を得て行動しているのである。
小幡は明治初期から、社会の安定には学問が必要で、すべての日本人が智恵を磨くべきであるという。また西洋文明について、風土の異なる土地で長い年月や努力を経て「千磨百練」した結果の種を、日本の地に持って来てやみくもに植えたところで育ちはしない。日本で根付き育つよう、改良が必要であると訴える。彼は外国語を学習する時間がなくても、西洋の情報を得られるための橋渡しを考え、雑誌や演説会、また交詢社という、近世には存在しなかった新しい形の組織で、世務諮詢のネットワークを広げていく。
『小幡篤次郎著作集』を眺めると、翻訳家として、教育者として、経済学者として、貴族院議員を務める政治家として、様々な小幡の姿が見えてくる。それは、明治の知識人のひとつのあり方を示し、日本の近代を考える上で考察は欠かせない。福澤の影として見ていては理解することができない、近代日本の一側面が存在する。私は小幡の著作集は、必ず近代日本研究に寄与するものと信じている。ぜひ手に取っていただけるよう、図書館にリクエストしていただきたい。むろんご購入いただければ、この上ない幸せである。
蛇足にひとつエピソードを。福澤は故郷中津からの入塾生に学費捻出のため、自身が翻訳した英字新聞の記事を筆写させていたが、翻訳の労を執る自分より筆写生の仕事が遅いことを常に怒っていたらしい(昭和2年2月『福澤諭吉伝』第1巻)。一方小幡は、『時事新報』発刊時に慣れずに遅れがちになる植字工の作業を、夜な夜な手伝っていた。大男が一人交って仕事をしているので、誰かと思ったら小幡であったという(明治38年5月20日付『時事新報』)。上司にするなら……。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

西澤 直子(にしざわ なおこ)