【その他】
【書評】『福澤諭吉の思想的格闘──生と死を超えて』(松沢弘陽著)
2021/06/18
一
『福澤諭吉の思想的格闘──生と死を超えて』は、幕末明治期政治思想史研究の碩学松沢弘陽(まつざわひろあき)氏が、1979年から2012年に執筆した14編の論考を収録した論集である。そのうち11編は直接福澤諭吉ないし福澤研究史に関するものであるが、残る3編のうち2編は明治前期の天賦人権論の流れについての論考であり、1編は丸山真男思想史論である。しかし、この天賦人権論に関する2編は、第三章で福澤の自然権と社会契約論を考察する時の参考材料となっている。また、丸山真男思想史論が、福澤研究史に関係してくることは、丸山の研究対象として福澤が大きな比重を持っていたことを考えれば当然である。
このように本書は、著者が、30年以上にわたる期間に執筆した、直接・間接に福澤諭吉に関する論集である。しかし、単なる寄せ集めの論集ではなく、全編を貫く骨太な関心が伏在しており、1つのまとまった著作といえる。
二
本書を貫くその関心は何か。福澤の思想を考えるときに、彼が抱えていた課題は大きく2つに分けられる。1つはいかにして独立した個人を確立するかという課題であり、もう1つは、その独立した個々人が、いかにして社会を形成するかという課題である。そのうち著者が、福澤の思想の核心として析出しようとしているのは後者である。
著者によれば福澤は、「国民国家の形成における、国家─統治機構の創出ではなく国民の形成を自己の課題とした」(59頁)。その「国民の形成」は、個々人が交際し社会を形成することの上に成り立つ。著者は、この社会形成の基盤として福澤が考えたのは、「社中」という名で呼ぶところの「自発的結社」(9、22、56、85、140、145頁)、「自発的自治的結社」(143頁)、「自治的諸団体」(114、138頁)、「「私立」の自発的諸集団」(114頁)だとしている。具体的には、学校、研究団体、報道機関、企業、業界同業団体、クラブ、ボランティア団体など多様な民間団体である。「自発的結社」「自治的諸団体」などと表現は異なるが意味内容を一にするそれらの用語は、本書全体をつらぬくキーワードと言ってもよい(注 本書評では、説明の簡便を考え、以下「自発的結社」と統一して記す)。
この自発的結社に関連して著者が最も注目しているのは、福澤が『学者安心論』で論じている「人民の政」である。著者は自身の福澤研究を振り返り、「私の心に最も響いたのは……『学者安心論』である。福澤はここで「政府の政」に対する「人民の政」という新しい構想を示す」と述べている(308頁)。また本書の中で最も長い引用は、第四章における『学者安心論』からの引用である(142─143頁)。それらの点からも、そこに、著者が析出したい福澤の思想の核心があると言える。
『学者安心論』からの著者の引用箇所で、福澤は次のように論じている。「国政」にかかわるというのは、なにも官僚や政治家になることだけではない。人民が民間で行うことも「国政」であり、それは学校、学術、新聞、弁論演説、農業経営、貿易、内国物産、開墾、運送、商社から人力車挽の仲間まで、「政府の政」の何倍もある。それらを担い運営・経営することが「平民の政」「人民の政」であり、それは思いの外に有力なもので、「動(やや)もすれば政府の政を以て之を制すること能(あた)わざる」ものである。この「平民の政」「人民の政」が繁盛して、はじめて「民権の確乎たるもの」も確立する。
この引用部分で福澤は、経済などの民間活動も、ネーションを担うという意味で「国政」であると言う。その主旨は、当時の若者の過度な政治志向を批判し、民間諸活動への積極的な従事を推奨する所にあったとも取れる。しかし著者は、より深く洞察し、そのような民間の諸活動を「固有の公共的機能を分担する自発的自治的結社」の活動ととらえ、福澤は「このような自治的団体を政治以外の領域に創り出すことを当面の課題とした」(傍点は筆者:以下同様)のだと判断している。また、「当面の課題」というのは、その課題を果たすことが「結果として政府と国政に影響する」と福澤が考えていたからとも見ている。そのような点で、狭義の政治の真の変革のために、福澤は「平民の政」を唱えていたというのが著者の捉え方である(143頁)。
同様の視点から第四章では、福澤は「議会という制度が、その固有の機能を発揮するための前提条件として」(115頁)上記のような自発的結社の多様な形成を考えていた、としている。議会政や民権体制ができたとしても、自発的結社を形成するような「人民の政治文化」(同)が無ければ、それらは形式的な制度にすぎず、真の国民国家の形成とはならないと福澤は考えていたというのである。
三
福澤が、西洋文明の基盤に自発的結社があると考え始めたきっかけとして著者が注目しているのは、『福翁自伝』に書かれている福澤の西欧体験である。文久2(1832)年に幕府使節団の一員としてロンドンに滞在していた時、福澤は、英国のある「社中」が政府に出した建言書を目にした。それは、英国の政府や公使による日本に対する無法な対応を厳しく批判する建言であった。その経験が、福澤にとって後に『自伝』に記す程の大きな驚きであったことを、著者は重視している。また、その観点から、第Ⅰ部では、『自伝』に出てくるこの英国の「社中」と差出人と建言書の内容を、可能な限り詳細に発掘し調査している。
しかし、福澤の思想の根幹としての「自発的結社」というテーマに関して、本書の中核となっているのは、なんといっても第Ⅱ部である。そこに描かれている福澤は、政府の「過強」に対する「平均」の機能を多様な自発的結社に求めた(114頁)。また、自発的結社の活動をささえるものとして、「仲間」の間での相互の意思疎通と合意形成を滑らかにする、「交際」「演説」「衆議」の習慣を形成することにも取組んでいた(83頁)。それは一国民全体にわたる「演説と討論の「始造」という課題」でもあった(118頁)。また、学問に関しても、集団の中での進歩を考え、「本読み中心」から「口頭のコミュニケーション重視」に「学問観の革命的転換」を行った(119頁)。
このような福澤の思想の析出を行いながら、同時に著者はそこに、本書の題名となっている「福澤諭吉の思想的格闘」を見ていることも忘れるべきではない。福澤は、自発的結社の広範な形成により「国産の文明史を「始造」」(174頁)するため、「「異説争論」の間から合意を作り出す」という「切実な課題」(176頁)を担い、「演説と討論の「始造」」に取り組み(118頁)、「学問観の革命的転換」(119頁)を行わなければならなかった。ここで、著者が「始造」や「革命的転換」を、きわめて困難な事業と捉えていることはいうまでもない。しかも、福澤は一方で、「人間および人間の関係における合理性の限界」をはっきりと自覚し(126頁)、日本において討論を成り立たたせることの「困難について誰よりもよく自覚していた」(128─129頁)のであるから、福澤の格闘は一段と凄まじいものであったことになる。また、いち早く率先して独立の道を選んだ福澤にとって、新たな社会形成の手段となるべき演説や討論の「工夫」は、「死中に活を求めるように選びとった方法」(137頁)であったとも、著者は福澤の苦闘を表現している。
さらに福澤は、以上のような日本の「文化の改革」が本来の課題であることを認識しながらも、『民情一新』においては、「近時の文明」がもたらす人民の「不満の感情の激化」と「官民の軋轢」という問題に向き合わなければならなかった。そのため同書では、「文化の改革」という本題を一時後回しにして、早急な議院内閣制を「対症療法」として提示しなければならなかった。そこにも著者は、「アンビヴァレントなもの」とならざるを得なかった福澤の思想的格闘を見ていると言えるだろう(207─208頁)。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

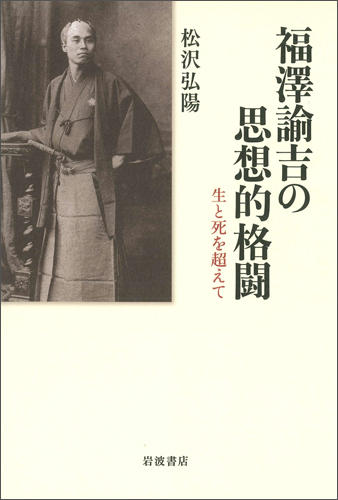
小室 正紀(こむろ まさみち)
慶應義塾大学名誉教授