【福澤諭吉をめぐる人々】
尺 振八
2025/10/16
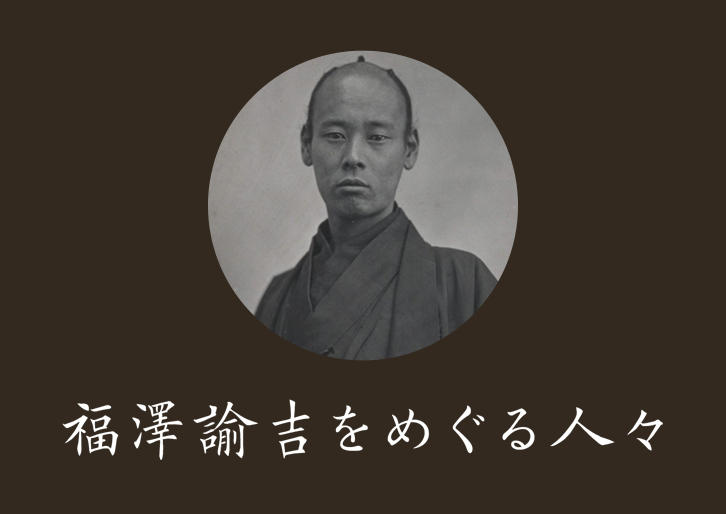
幕末・明治に外国語を学習する者にとって翻訳作業は困難を極めた。1862(文久2)年に幕府の洋書(蕃書)調所が出版した『英和対訳袖珍(しゅうちん)辞書』は、初めての本格的な英和辞典であったが、英蘭辞書をもとに翻訳したことも影響して使い勝手は良いとは言えなかった。
明治半ばに発行された尺振八(せきしんぱち)の『明治英和辞典』は、正確でかつ使いやすいという画期的なものであった。加えてスペンサーの教育論を訳した『斯(す)氏教育論』は、明治の教育に大きな影響を与えた。さらに当時慶應義塾と並んで評価の高かった「共立学舎」を創立し、経済学者田口卯吉(うきち)(鼎軒(ていけん))らを輩出した人物でもある。そして幕末の困難な日米の交渉は秀でた語学力を持つ振八の存在なしには成し得なかったのである。これらの功績から、振八は「現代英学の祖父」や「一流の英学者」、「英学の先達」などと称されている。「先達」という表現は、尺次郎氏(「縁あって尺家を継いだ」「振八四代目の子孫」)による振八の伝記、『英学の先達 尺振八 幕末・明治をさきがける』(1996年、以下『英学の先達』)で使われている。しかし、英学者、教育者、翻訳家、通訳として高く評価されているにもかかわらず、同時代の洋学者や教育者ほど知られていない。福澤とも親交のあった振八は、どのような人生を歩んだ人物なのだろうか。
振八の生涯については、振八の死後、生涯の友である乙骨太郎乙(おつこつたろうおつ)が『大日本人名辞書』の中で執筆した「乙骨太郎乙所選略伝」(以下、「略伝」)に詳しい。
尺次郎氏によると、乙骨の振八評は、「自尊心・意志は強いが、一方、思いやりが深い。そこで政府の偉い人だからといって、見下した態度を取れば、胸を張り負けずに対応する。その一方、普段付き合いがない人でも、篤い志をもって何かをしようとしていると聞けば、全力を挙げて面倒をみる。そういう人物である」(『英学の先達』)という。
激動の時代の中で洋学の道を選ぶ
振八は、1839(天保10)年8月9日、下総高岡藩医鈴木伯寿(はくじゅ)の子として江戸で誕生した。乙骨によると振八は、まず儒学者の田辺石庵(せきあん)、藤森天山(弘庵)に学んだとある。その際知り合った石庵の次男、太一は、遣欧使節にともに随行した振八の「終生の友」である。また同志社を創立した新島襄とも親交を結んだ。のちに新島は、振八を「江戸の親友」と記している。
尺次郎氏は、振八と洋学との出会いは田辺石庵の長男、孫次郎が関係していると述べる。孫次郎は、砲術家の高島秋帆に学び、田辺塾では蘭学についての議論が盛んだったようだ。
その後昌平黌に入ることになるが、その直前に「尺氏を冒し」と、振八が尺家を継いだことがわかっている。詳細は不明だが、幕臣で漢学者の尺兼次郎の弟として尺家に入ったことで、幕臣の子弟に限られた昌平黌の寄宿寮に入ることができたようだ。しかし、病のため数年で退寮し、悩む振八は、田辺太一の「国家に尽くそうと思うものは、一日も早く西洋の学問を学ぶべき」(『英学の先達』)という言葉で、洋学の道を決意する。20歳のことである。
振八は、1860(万延元)年、中浜(ジョン)万次郎に方を学び、さらに西吉十郎(成度(なりのり))にも師事し、文法も学んだ。血のにじむような努力によって、略伝には「期年ならずして、語学大いに進む」とある。
外国方通弁就任、福澤との出会い
1861(文久元)年8月、振八は、矢野二郎、益田孝、津田仙とともに、外国方通弁(通訳)に任命された。また生涯の友、福澤とはここで初めて顔を合わせた。振八らはすぐに麻布山善福寺のアメリカ公使館に勤務することになった。攘夷論が高まっていた当時、公使館関係者であることは危険な立場であった。しかし振八らは臆せずに公使館員や通訳から英語を習い、自身の語学力に磨きをかけ、さらに約1年間横浜運上所で勤務し、その合間に通訳の立石斧次郎の教えも乞うた。
語学力を磨いた振八らは、1863(文久3)年の第2回遣欧使節団(横浜鎖港談判使節団)に西吉十郎らと随行し、ついに他国の地に足を踏み入れた。洋装で写真を撮影した振八は、帰国後に処分を受けている。ほどなくして、振八らは外国方を辞め、振八は1865(慶応元)年にアメリカ公使館の通訳となった。幕末の困難な交渉の場に語学力に秀でた振八がいたことは、日米両国の大きな助けとなった。
『福翁自伝』(以下、『自伝』)では、この頃の2つのエピソードに振八が登場している。1つ目は、第2回遣米使節団の際に酔った福澤が「幕府を倒せ」と公然と発言し、同席していた振八が、冷静にたしなめたことが書かれている。『慶応三年日記』によると、帰国後謹慎となった福澤のもとを振八が泊まり込みで数回訪ねている。森川隆司氏は米国で購入した洋書は、振八の助言で選んだのだという(「英学者・尺振八とその周辺」1978年)。2人の親しい関係がわかる。
2つ目は、振八がアメリカ公使館の通訳をしていた頃に、明治政府の旧時代的な行いがアメリカにまで伝わっていることを「大笑いではないか」と話す振八に対して、「苦々しい」気持ちとなった福澤の感想が残されている。
また『故社員の一言今尚精神』では、戊辰戦争時に振八は公使館が証明書を発行すれば塾生を保護できると福澤に提案している。振八は塾生のためにわざわざ公使と交渉し、福澤のもとを訪ねたのであった(塾生の小幡甚三郎が申し出を断った)。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

川内 聡(かわうち さとし)
慶應義塾中等部教諭