【福澤諭吉をめぐる人々】
雨山達也
2025/09/24
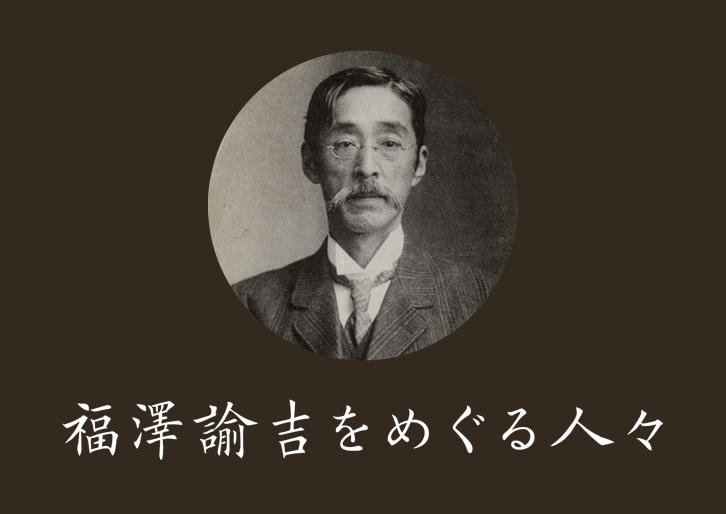
「既に門閥のない」福澤に驚く
「先生が何か藩の重役に話をせられることがあって、ある日私の家にお出でになり、藩の家老78名が2列になって私の家の書院に列座しているその間を悠々と通り抜けられ、床の間の中央から下へ向われて座に着かれ、その席から一同へ話をしていられた現場を目撃して、私は子供心にも先生の眼中既に門閥のないのを看取し、さてさて偉い人であると思いました」
『福澤諭吉伝』にある雨山達也(あめやまたつや)の談話である。明治3(1870)年11月のことであるが、雨山は安政3(1856)年4月15日生れであるので、満14歳の時の一齣である。
これは、『福翁自伝』で「藩の重役に因循姑息説を説く」と見出しの付いた「ソコでわたしが明治3年、中津に母を迎えに行ったことがある。ところがそのときには藩政が大変なことになっていまして、福澤が東京から来たから話を聞こうではないかというようなことになって、家老の邸に寄ばれて行った。ところが藩の役人というあらんかぎりの役人重役が皆そこに出ている」の場面である。
達也は、豊後佐伯藩の家老戸倉六郎兵衛の二男として生まれ、明治2年頃、奥平図書(ずしょ)の養子となった。そして、維新の際に雨山と改姓した。
中津藩主奥平には、江戸時代より前から「七族五老」と呼ばれる重臣がいた。その子孫は江戸時代の最後まで「大身衆(たいしんしゅう)」と呼ばれる特別な存在で、家老はこの中から務めていた。雨山家の幕末の石高は2600石で上士の中でも突出している(因みに福澤家は13石2人扶持)。
住んでいる場所も上士のエリアでも特別な三ノ丸であった。雨山家の屋敷は大手門から入って生田(しょうだ)家の屋敷の西隣にあった。生田の屋敷は、明治4年に慶應義塾の分校のような位置づけの洋学校「中津市学校」になった。今は、そこに中津市立南部小学校があるが、西側に生田門が移設保存されており、その道を挟んだ一帯が雨山家であった。
これらのことを考えても、達也が冒頭の談話で「普通ならば先生は自分の父などとは同席することさえ叶わない身分であるにもかかわらず」と記している通りで、福澤の悠然とした態度には相当驚いたに違いない。
慶應義塾に学び教員となる
福澤の中津滞在は、雨山の生涯にとっても大きな転機となった。養父図書は、達也の幼少期の漢学の師と話した際に、「漢学は到底時代と伴い難し、御子息を学ばしめんには、須らく英語を採られよ」と助言を受けたという。そこで、福澤の中津帰省の好機に、慶應義塾への入塾を願ったのであった。
義塾の入社帳によれば、達也は明治4年2月29日に入学している。「等外」から順次進級を重ねて、明治7年12月、「正則第五年生」を修えて卒業した。慶應義塾が「卒業」の制度を設けた最初の年の卒業でもある。そして、翌8年から義塾の教員となった。
義塾での長い教員生活の間、明治28年11月から33年8月の間は、宮崎県延岡の亮天社(りょうてんしゃ)に赴任した。亮天社は旧延岡藩主の内藤政挙(まさたか)が設立した私立中学校である。内藤自らが義塾で学んでおり、教員の多くは義塾出身者か中津市学校出身者であった。そして、亮天社の要請を受けて、校長兼教師として雨山が派遣されたのであった。
当時の亮天社については、30年から4年間派遣された若手教員田中一貞が『三田評論』の前身、慶應義塾学報に「亮天社およびその学風」を寄稿している。田中は後に、義塾の社会学の先駆となり、図書館長も務めた人である。
田中は、自身の赴任についても「慶應義塾に在りて温厚にして品格高く、20年間その教育に従事し社中人望浅からぬ雨山君の招聘せられて現に同社に長たる如きは、予を吸引するに預て最も力ありし事は固より論を待たざるなり」と述べている。
また、亮天社にとっても、「雨山君の招聘は同社の歴史に一新起源を為すもの」と記した。実際に、雨山は教則を改め、また、早速に英国人教師を雇い、発音の教育等にも効果を発揮していた。また、英書の「翻読に至りては五行並び下るとも言うべき雨山君あるなり」であった。雨山の英語については、後に法学部長を務めた板倉卓造も「私の普通部時代」の中で、「この方は温厚な学者で英語の達人でした。八行ならび下るとよくいわれ、英語を一ぺんに八行ずつ読んでいったといわれています」と似た表現で語っている。
亮天社の気風も義塾と通じるものがあった。田中は、教員達は「皆その(内藤の)義気に感じて、世の官立学校の如く、役人風の教授をなし、営利的私立学校の如く、切売的の教授をなすが如き事は、夢にも想像する能わず」であり、「学校は一家庭の如し」であったという。教員は「教育界今日の大弊たる形式主義を嫌いて」いたとも報じた。
それだけに、明治32年、設置者、教員に教員免許状を有すること等を求めた私立学校令が出た時には、雨山は「国家教育の為に一身資産を捧げて子弟の教育に従事するもの幾人かある。然るに文部当局者は窮屈なる規則を設けて教育に熱心なる人物を拘束せんとす。その意私立学校の改善を計るに非ずして寧(むし)ろ継母根性に出るや明らかなり」と文部当局者を痛罵する文章を日向から慶應義塾学報に寄稿している。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

山内 慶太(やまうち けいた)
慶應義塾大学看護医療学部教授