【福澤諭吉をめぐる人々】
柳河春三
2025/07/15
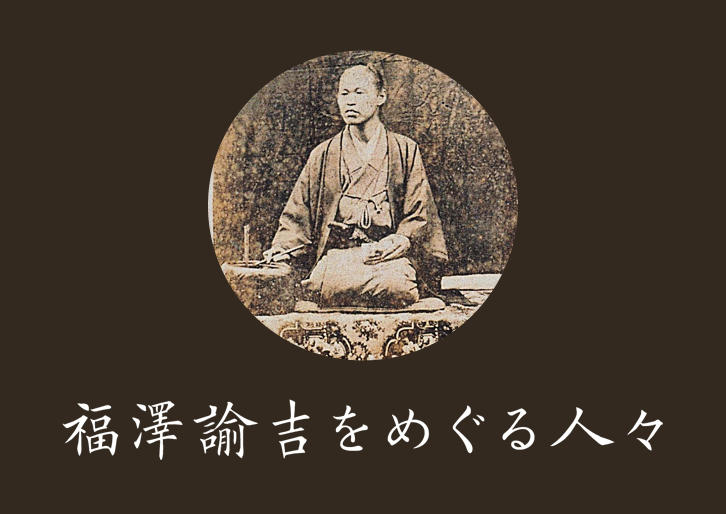
幕末から明治初めのこの国に、数々の伝説逸話を残した俊才がいる。その人の名は柳河春三(やながわしゅんさん)。多芸多才で博覧強記、諧謔自虐を織り交ぜて、混ぜっ返すが面倒見はよく、周囲の仲間を手伝いながら西洋の学問知識、制度・文物の導入に力を注ぎ、数々の分野で先駆的な仕事をした。とくに『西洋雑誌』『中外新聞』などの刊行で中心的役割を果たしたことから「新聞雑誌の創始者」(尾佐竹猛(おさたけたけき))と評されている。
福澤諭吉は『福翁自伝』に、柳河春三の名を一度だけ記している。明治政府が出来て、江戸の洋学者で最初に呼ばれたのが、神田孝平(たかひら)、柳河そして福澤の3人だったという箇所だが、2人の間には面識も共通の知友もあった。柳河の生涯を駆け足で記し、福澤との関係についても少し記してみたい。
柳城(りゅうじょう)に奇異の童子あり
柳河春三は天保3(1832)年2月25日に、尾張名古屋の大和町(現中区丸の内)で知多屋武兵衛の子として生まれた。はじめの名を栗木辰助といい、のち西村良三と改めた。
辰助は2歳に至らぬうち教えもせぬのに文字を書き出し、驚いた両親は、書家で藩祐筆(ゆうひつ)の丹羽盤桓子(にわばんかんし)につけて書を習わせた。話は藩侯徳川斉温(なりはる)にも聞こえて、3歳の時に御前へ召された。何枚も揮毫(きごう)した末に殿様から一幅を求められると、「もういやになった」と大書して人々を驚かせたという。斉温は、これは神童だ、僧にしたなら後日必ず超凡抜群の善知識(ぜんちしき)になるだろう、と言い、『金鱗九十九之塵(こんりんつくものちり)』という書物にも書家の扱いで、「此(この)小児は学ばずして能(よ)く書(しょ)し、習わずして書を読(どく)す奇異の童子なり」と紹介された。
その後、尾張の蘭方医で本草学者の伊藤圭介と、砲術家の上田帯刀仲敏(たてわきなかとし)に就いて学問を積んだことで、この子の才能は大きく開花した。天保12年、伊藤が出した『洋学篇』で栗木辰助改め西村良三は、伊藤の長子圭造と共に参校者となった。それが数えで10の年。22の時に出版された上田帯刀の『西洋砲術便覧』には補筆者として名を連ねたが、真の作者は良三であったという(成島柳北「柳河先生逸事」)。さらに翌安政元年には、伊藤の訳書『硝石(しょうせき)篇』(安政元年)の参校を上田と分担した。なお、伊藤からは医学も学んだ。同2年の良三の著作「颶風(ぐふう)病考」は、疫痢を論じたものである。
加えて彼は和漢の学も十二分に修めた。その詩歌も文も、筆跡と共に立派である。友人成島柳北は「其(そ)の最も長ずる所は国学に在り」(「柳河先生の略状」)と評価した。それもそのはず、丹羽盤桓子は国学者・鈴木朖(あきら)の門人、上田帯刀は妻の甲斐子(かいこ)と共に本居大平(おおひら)門下で、みな国漢兼学だから、存分に学ぶことができたのだろう。この時代の知友には、まず上田帯刀の下に生涯の友となる化学者宇都宮三郎がいた。伊藤のところへは上田夫人の実家・千村(ちむら)氏の許から、英学者となる千村五郎、また典医の子で博物学者になる田中芳男と弟の大介が学びに来ていた。良師益友に囲まれた尾張時代といえる。
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

大久保 忠宗(おおくぼ ただむね)
慶應義塾普通部教諭