【その他】
【社中交歓】読
2025/10/30

囲碁と読み
ある有名プロ囲碁棋士に記者が「貴方はどれだけ先を読みますか?」の問いに「一(ひと)目で1,000手、50手先までを20通り」と。ところで1959(昭和34)年、我が囲碁部は北海道、関東、中部、関西、九州、中国四国の6地区代表による日本囲碁学生団体戦にて全国優勝2連覇を果たした。当時の囲碁部は久保弘、山下功、根橋輝一の三羽烏に次いで山内健至、安井信之、小林清一郎、野村正雄らで、いつも練習局後の検討会は、お互いの意見交換で実に楽しい一時で、今にして思えば「読みの浅さへの反省会」であった。
一流棋士でも一生の正式対局は1万局。それらの対局分析から良い手、悪い手を反省するが、AIの出現で一変した。膨大な対局集計から勝ちにつながる良い手を瞬時に特定、また、従来では悪いとされていた手がむしろ良い手では? と判定する、「四角の三三入り」が如し。AIに教わった「読む幅・深みは無限なり」と。囲碁(以後)大いに読まれたし!
読む以前の話
-

山口 文彦(やまぐち ふみひこ)
豊田工業大学工学部教授・1993理、1995理修、2001理博
小学生の終わりにプログラミングに出会い、義塾で学問としての計算機との付き合い方を学び、情報系の大学教員となった。縁あって、考古学上の未解読言語に情報科学の手法を適用する研究をしている。
主な研究対象はイースター島で木の板や棒に刻まれたロンゴロンゴと呼ばれる記号の列である。
計算機を使って失われた言語を解読する、と言っても間違いではないのだが、計算機が解読してくれるのではなく、解読の道具となるプログラムを作っている。似た図形が同じ文字かどうかを推定するために形状によって図形を分類したり、記号の個数を数えたり、現地の言葉との対応を調べたり、計算機を使ってできるのは、そういう作業の自動化である。こうした作業が解読につながると信じてはいるが、この文字を刻んだ人々の意図を汲み取ることはおろか、文書のジャンルを推定することすら難しい。
ヒトが文書を読む前に発揮している認知と認識の能力の高さを感じながら、どんな人々が文字を作ったのだろうと思いを巡らせている。
読唇技術の医療応用
-
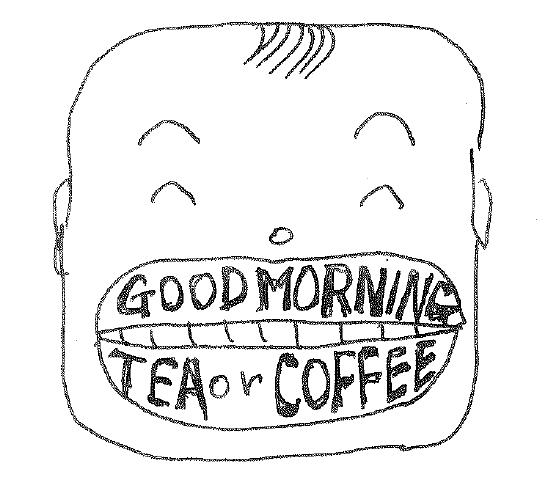
富里 周太(とみさと しゅうた)
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室助教
理工学部の満倉研究室と共同で、人の唇を読みとり、読み上げてくれるデバイスを開発しています。機械学習を応用した読唇技術を用いて、唇の動きをカメラで読み取り言語に変換します。変換した言語を、テレビのニュースでも使われる合成音声の技術を用いて、音声に変換するというデバイスです。口を動かすだけで声が出せる、いわば声を出さずに声を出すことが可能になります。
この不思議なデバイスは、喉頭癌などで声帯を失った方の声を取り戻すことができます。もし声帯を失う前の録音があれば、元々の声を再現することも可能です。喉頭癌の他にも、吃音、場面緘黙(かんもく)、発声障害、失語症など、声とことばの疾患をお持ちの方々のコミュニケーションを手助けできると考えています。
近視のある方が眼鏡をかけ、難聴のある方が補聴器をかけるように、声とことばにお困りの方がこの読唇デバイスを使っていただけたらと思います。ただし、完成のメドはまだ読めませんが。
教室でない教室
-

岩井 祐介(いわい ゆうすけ)
慶應義塾幼稚舎司書教諭
私が好きな写真集に『読む時間』という作品がある。これは20世紀を代表する写真家アンドレ・ケルテスが世界のあちらこちらで「読むこと」に夢中になっている人々を撮影したものである。原題は『ON READING』。日本語版『読む時間』には谷川俊太郎氏の「読むこと」という詩が巻頭に掲載されており、次のようにはじまる。
「黒い文字たちが白い紙の上に整列しています 静かです」
私たちは1人でいる時でさえ、SNSなどを介して誰かと繋がっている。けれども1人でいることや孤独であることで、人は気持ちを落ち着かせ、自分と向き合うことができる。本を読んでいる時間はそんな時間だ。それは子どもも大人と同じだろう。慶應義塾幼稚舎の児童図書室は「教室でない教室」「みんなのひろば」というコンセプトで1976年に開室した。慌ただしい子どもたちの生活の中でも、ゆっくり自分と向き合うことができる場所として、これからも環境を整えていきたい。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

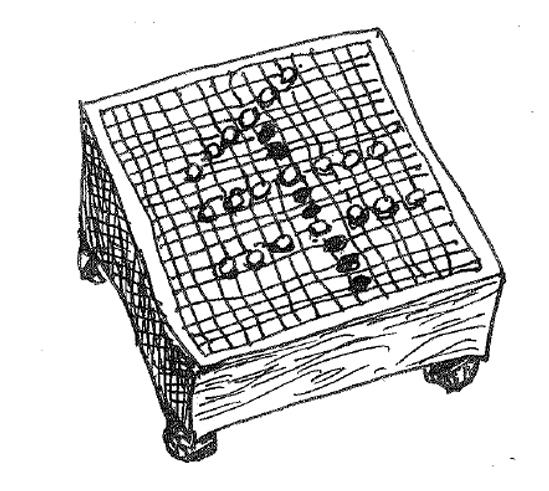
安井 信之(やすい のぶゆき)
ブラザー精密工業(株)監査役、囲碁三田会会員・1960政