【その他】
【社中交歓】にんにく
2025/09/01

にんにくの話
青森県は、りんご生産高日本一として知られていますが、実は、にんにくとごぼうの生産高も日本一なのです。にんにくは、中央アジア原産と言われますが、日本には中国を経て8世紀頃もたらされました。日本では長く薬や強壮剤として使われ、戦後の食の西洋化、多様化に伴い次第に食材として用いられるようになりました。
青森県産にんにくは、全国生産量の8割を占め圧倒的なシェアを誇っています。その理由は次の3つが挙げられると思います。①夏涼しく冬厳しい寒さという気候が独特の甘味と辛味を醸成。②収穫、乾燥後、定温倉庫に保管し、年間を通して出荷できる体制が構築されている。これは、りんごの出荷体制に倣ったものです。③福地ホワイト六片やたっこ一号等の白く大粒で旨味と香ばしさのある品種を作り出したことです。
私の会社は、100種類を超えるにんにく関連商品を扱っていますが、黒にんにく(熟成にんにく)、にんにく煎餅、チップス、ラーメン等が好評です。
プロヴァンスはニンニクの香り
-

佐藤 篁之(さとう ひとやす)
編集者・1982文
「フランスの田舎」として、世界的に愛される地中海沿岸のプロヴァンス。街ごとの匂いを感じる海外で、プロヴァンスの香りといえばやはりニンニクが絡む。南フランスの風土にはそれだけこの野菜が根付いているのだ。
代表的な料理はトマトなどの野菜と溶きたまごのスープ:トゥーレン、海沿いなら魚をすりつぶしたスープ・ド・ポワソンで、こちらは日本でも結構食べられる。どちらもニンニクをオリーブオイルなどで炒めてベースを作る濃厚なスープだ。カットしてこんがり焼いたバゲットを浮かべるのも同じだが、パンには生ニンニクをすり込んでさらに風味を付ける。だいたい地中海沿岸がフランスになったのは、ルイ11世(15世紀)の頃。当時まで南仏人はパリの料理を味気ないとくさし、北では彼らを「ニンニク臭い奴ら」と呼んでいたという。
さて、そのスープは飲むものではない。啜る代わりにスプーンを縦に使って舌に載せれば、耳障りな音もでないというのはみなさんもご存じの通りだろう。
酒と肉とニンニクと
-

廣瀬 直記(ひろせ なおき)
明星大学教育学部准教授・2003文
中国中世の宗教文献を読んでいると、酒と肉と並んで五辛(ごしん)(ネギ、ニラ、ニンニクの類)が禁じられているのをよく目にする。仏教では、それを口にすると、ムラムラ、イライラするとされ、道教では、体が臭くなって「神」が去ってしまうとされる。「神」とは精神のことであり、また人の体内に宿る神々のことでもある。道教の修行では、体内に神々を宿すこと(思い描くこと)が求められる。そうすることで、肉体の死気が神々の生気に入れ換わり、不死の仙人になれるとされた。
一方、当時の医薬書は、ニンニクには腫れ物や風邪を治す効果があるとするが、そこに道教の道士が辛辣な注を付けている。「俗人どもは刻んでなます肉といっしょに食べているが、寿命を縮めるのにこれよりひどいものはない」「魚の塩漬けと合わせて食べると黄疸ができる」。翻って思うに、こんなごちそうがあったら、お酒が欲しくなるに決まっている。そう想像してみると、五辛が酒肉と並んで禁じられている意味がよりよくわかった気がするのだ。
『ドラキュラ』のにんにく
-

武藤 浩史(むとう ひろし)
慶應義塾大学名誉教授
長じて『ドラキュラ』の本を書くことになる私がにんにくの力なるものを初めて自覚したのはずっと昔の話。通学途中のラーメン屋で採り放題のおろしにんにくをたっぷり入れて食べるのが何よりの楽しみだった。体に力がみなぎった。活臭!
『ドラキュラ』の原作は映画ではなくアイルランド出身の作家ブラム・ストーカーによって書かれた19世紀末の小説。表向きは東欧に住む吸血鬼がたくらむ英国征服を阻止する単純な話だが、様々な仕掛けがある。にんにくに関して言えば吸血鬼対策として世界中にあったが、この小説ではこれがカトリックの儀式と繋げられているのが特徴である。原作の吸血鬼ハンターは、にんにくや杭と共にミサで使う聖餅や十字架や神へのラテン語の祈りを武器にドラキュラに立ち向かう。その中で、にんにくの活臭が悪臭を放つ吸血鬼退治に貢献する。
匂いは宗教儀式と繋がり、実はプロテスタント国イギリスとカトリック文化の強いアイルランドとの複雑な関係を反映する。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

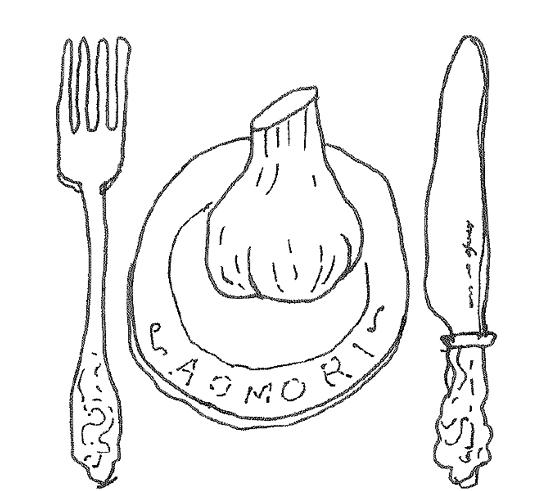
沼田 廣(ぬまた ひろし)
青森三田会副会長、青森県物産株式会社代表取締役社長・1973政