【その他】
『慶應義塾大学産業研究所60年史』発刊に寄せて
2025/08/27
本年3月、『慶應義塾大学産業研究所60年史』(以下『60年史』という)が、取りまとめられ刊行されました。慶應義塾やその諸機関の慶事は、四半世紀ごとに記念する伝統を踏まえると、やや変則的なタイミングでのお目見えとなりましたが、本書は、産業研究所の設立以来、半世紀以上にわたる研究活動やその知的伝統を記述する初の試みといい得るものです。
もともと『60年史』の編集・刊行は、当研究所の草創期を知り、かつ最初の専任所員でもあった佐野陽子先生(慶應義塾大学名誉教授)の発案と呼びかけによるものです。先生から呼びかけがあったとき、当研究所に関わってこられた多くの先生たちがすでに引退され、場合によっては鬼籍に入り、往時のことを知る手がかりが年々少なくなっている状況にありました。佐野先生は、このような状況を心配しておられたのだと思います。
『60年史』は、まず、年表とともに産業研究所の設立初期の様子や特色について記されている「産業研究所のあゆみ」と、これにつづき、経済、法律および社会心理・行動科学の研究各部門における研究の特色の紹介や、当研究所にさまざまなかたちで関わった研究者たちが、その時々の社会・経済状況の中でどのように問題を認識し、これらの社会的・経済的課題に向き合ってきたのかを振り返るエッセイで構成されています。その意味で、この『60年史』は、当研究所で起こった出来事を網羅的に取り上げたものでもなければ、それらを順序立てて記述した編年史でもありません。
このような編集方針をとったのは、『60年史』刊行の目的が、当研究所の研究活動に携わってきた人々に自らとの関わりを文章として寄せてもらい、当研究所が紡いできた社会科学に関する知的伝統を記録としてまずは書き留めていくこと、また、当研究所の保管庫に積み上がった文書や資料をこの機会に整理し、慶應義塾の公式記録との整合性を確認することだと考えたからでした。
したがって、『60年史』の編集にあっては、年を経るにつれて減っていく手がかりを、現時点で可能なかぎりかき集めることに注力しました。たしかに、網羅的で順序立ってはおりませんが、『60年史』は、読み物として興味深いエピソードが数多く記されています。機会があれば、ぜひ手にとってご覧いただきたいと思います。
なお、最後に『60年史』の表紙と裏表紙について、付言しておきたいと思います。
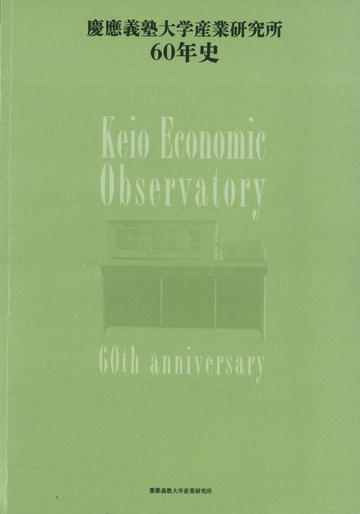
本書の薄い緑色のマットな光沢のある表紙の中央には、エンボス加工が施された1台の機器が配されています。これは、1962年、当研究所が他の学部や研究所に先駆けて導入したメインフレーム(大型汎用コンピュータ)「アイビーエム1620」です。アイビーエム1620は、鳥居泰彦先生(元塾長、1936-2019年)が萩原吉太郎氏(はぎわらきちたろう)(北海道炭礦汽船社長〔当時〕、1902-2001年)の支援を受け導入したものです(本書、新井益洋「産業研究所とコンピュータの変遷」pp.61-66、詳細は、鳥居泰彦『回想 慶應義塾』(2013年、慶應義塾大学出版会)pp.425-437 参照)。このメインフレームの導入は、その後、当研究所が実証研究を展開していく重要な契機となっていきます(なお、1979年、当研究所の初期の研究を支えたアイビーエム1620は、国立科学博物館に寄贈されています)。
また、本書の裏表紙には、ベージュ色の地に薄いグレーで何やら不思議な表が一面に印刷されています。これは産業連関分析における「三角表」と呼ばれるものです(1969年に、産研・生産構造分析プロジェクトの一環として作成されたものです)。産業連関表は、生産部門間の取引をマトリクスに配置し、この部門の配列をより多くの部門から供給を受ける部門の上の方に、より多くの部門に供給する部門を下の方に配置することで、産業連関表の対角部分より左下半分に取引を記録していくものです(「三角化」)。これを各部門の技術特性を考慮に入れながら、素原材料系統ごとにブロック化し再配列したものが「三角表」です。これにより、今流でいうところの「サプライチェーンの可視化」が可能になるわけです。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

石岡 克俊(いしおか かつとし)